企画展示

『シドニー号』【注0】をめぐる最近の事件では、我々が現時点で状況を把握している限り、日本政府は賢明に行動したとは言えないとの確信を表明せざるを得ない。我々は高陞号【注1】問題を論ずるに当たっても、同様の信念を表明した。戦時にはどんな文明国も、国際法を一字一句まですべての細部にわたって、絶対的に遵守しているわけではないということは、ある程度までたしかなことである。完全無欠の行動は、これを各国の政府に期待し難いものであることは、個々人に期待し難いのと同然である。
人を行動に駆り立てると考えられる最も激しい衝動は、戦闘という衝動である。そして、この衝動はしばしば、戦時国際法によって引かれた線を越えた行動に駆り立てる。さらにまた戦時国際法は、時には無意識的に違反される、ということも認めなくてはならない。戦時国際法は複雑であり、完全にマスターするには、長期の特別な勉強が必要である。そして、どんな提督、どんな将軍も、今日では、あらゆる状況に際して法律熟達者であることは望むべくもない。
—
1894年11月10日 土曜日 神戸—
『ノースチャイナ・デイリー・ニューズ』紙がハウイの捕虜宣誓書問題に関して取った態度に対して、我々は非常な驚きの念を表明せざるを得ない。
一、二週間前、我が同業『ノースチャイナ・デイリー・ニューズ』紙は、はじめ日本の新聞に掲載されたハウイに関するある記事に反駁する評論を掲載した。この報道記事とは、ハウイが本来は日本に敵対する役務にはつかないとしてその捕虜宣誓書を提出しておきながら、その後、威海衛で清国軍に就役しているところを発見され、威海衛で捕虜となった他の外国人たちは釈放されたのに、ハウイは日本軍によって拘束されて日本に連れ帰られ軍事法廷で裁かれ、無罪釈放されたが、無罪にもかかわらず国外追放された、という記事である。
— 1895年7月12日 金曜日 神戸 —
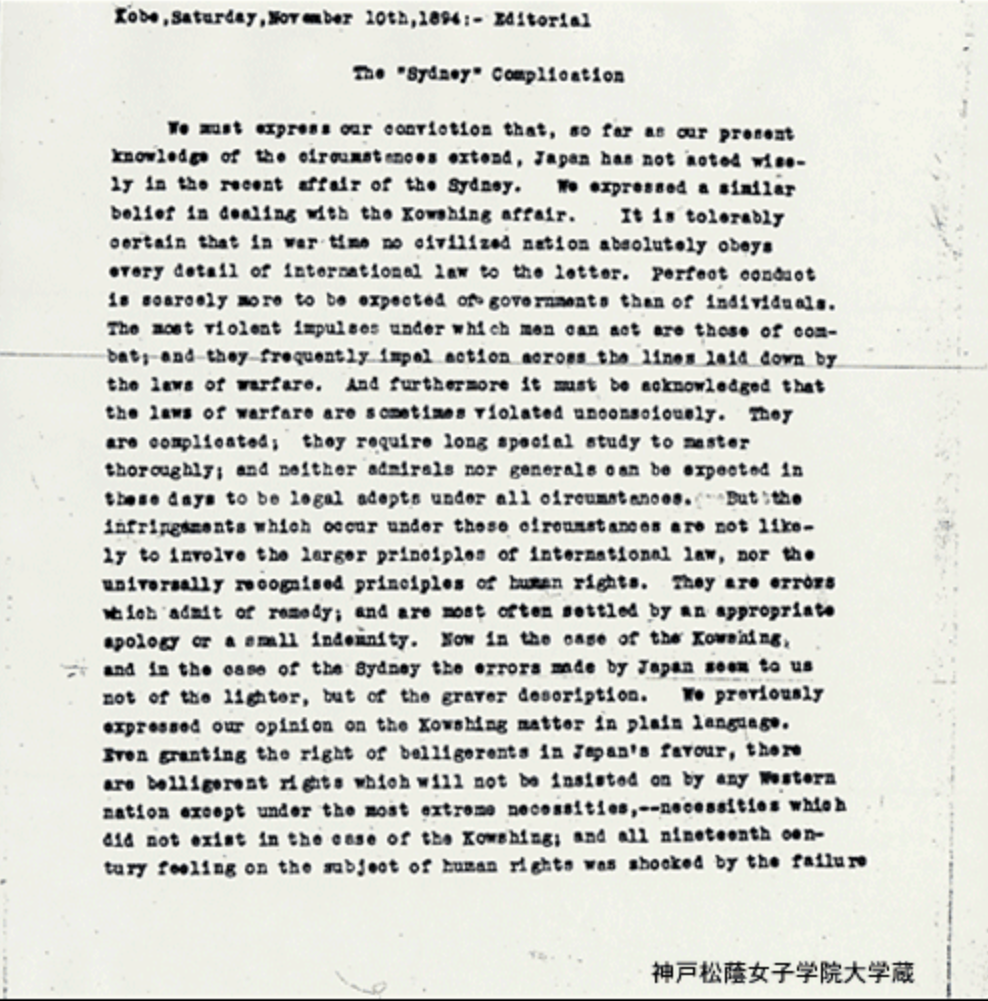
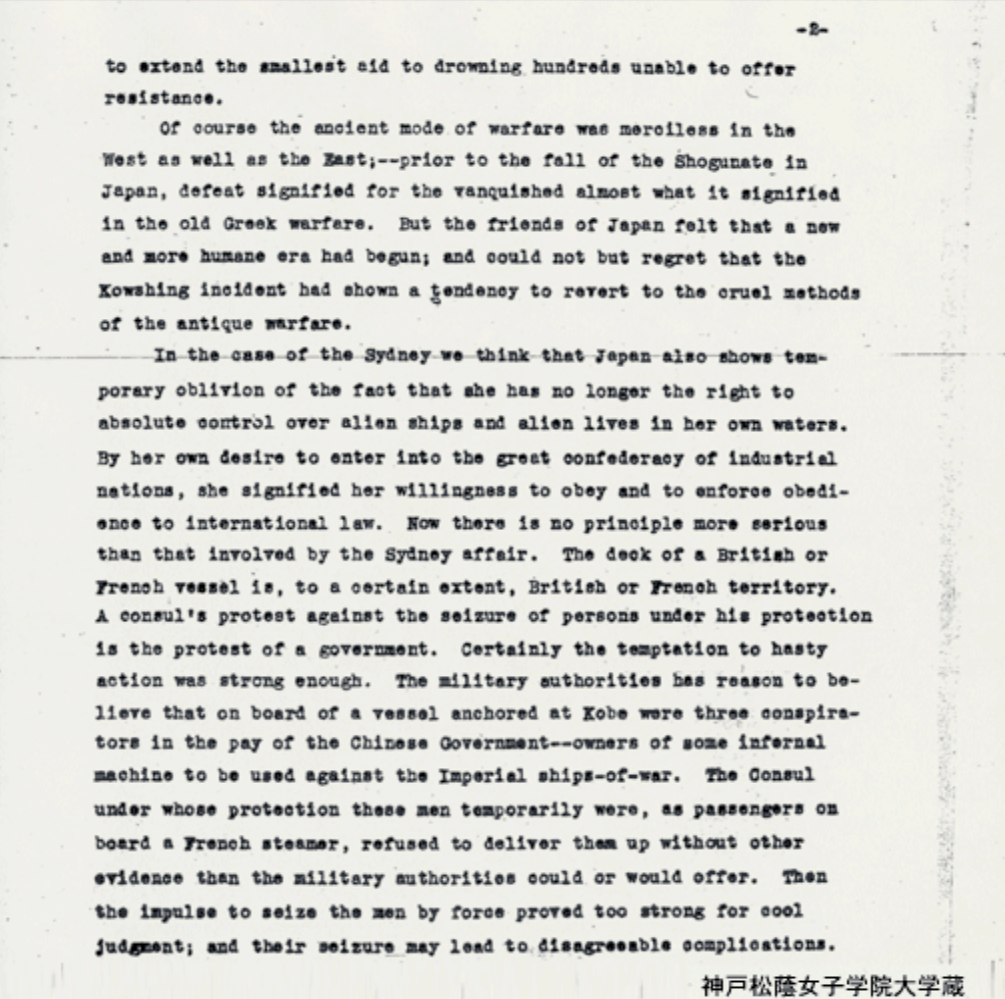
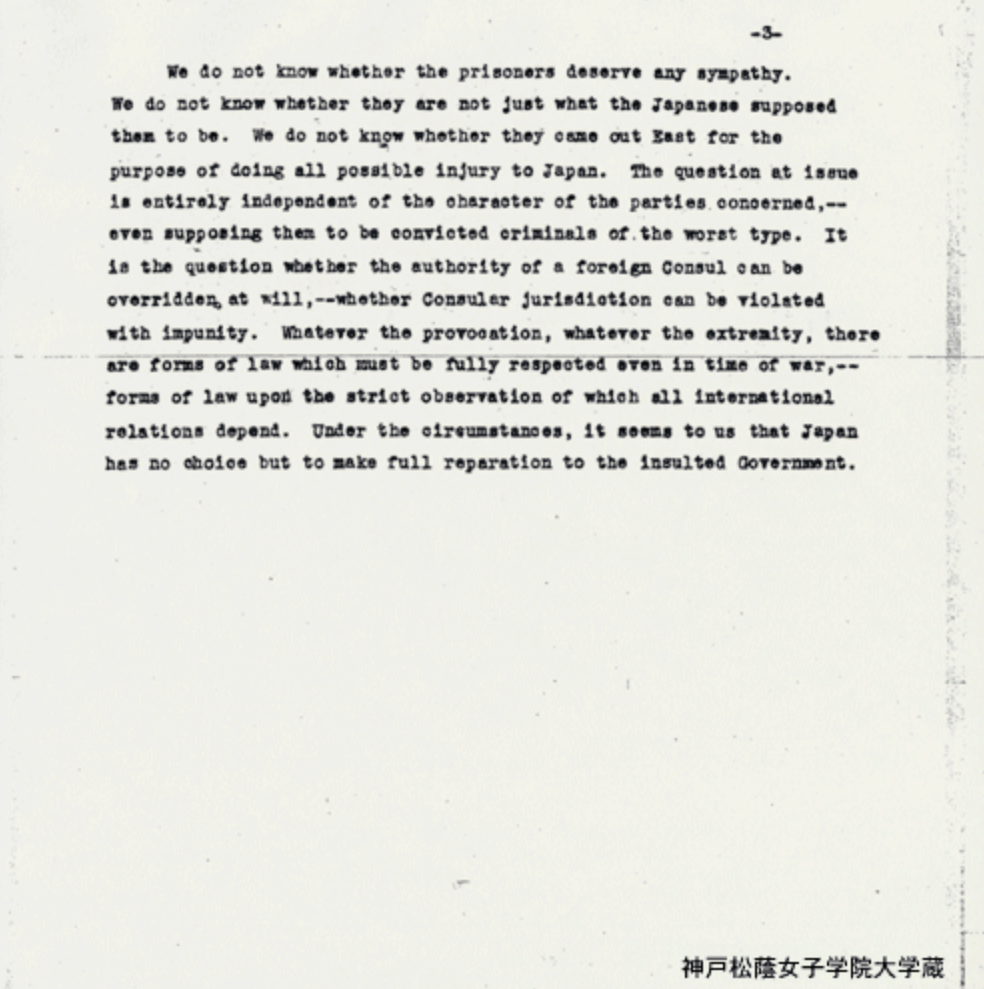

ジョゼフ・ヒコ氏の『ある日本人の物語』【注1】の第二巻であり完結編によって、過去三十年にわたる日本史に幾つかの興味ある側光があてられている。この興味ある著作の第一巻に目を通した人はすでにご承知の通り、ヒコ氏はごく年少の時にアメリカへ行き、そこで数年を過ごし、合衆国の帰化市民になるという巡り合わせを経た日本人である。
彼は最後には、日本の歴史の最も重大な時期に日本に帰り、そこで、封建制から立憲制度へと過渡期の騒々しい出来事や、外国の方式を導入したいと願う人々とそれに反対する人々との間の争いの目撃証人となることができた。外国教育を身につけ、また日本語の完全な知識をも持っていたので、彼は観察し理解できるという非常に好都合な立場にあった。
— 1865年7月1日 月曜日 神戸 —
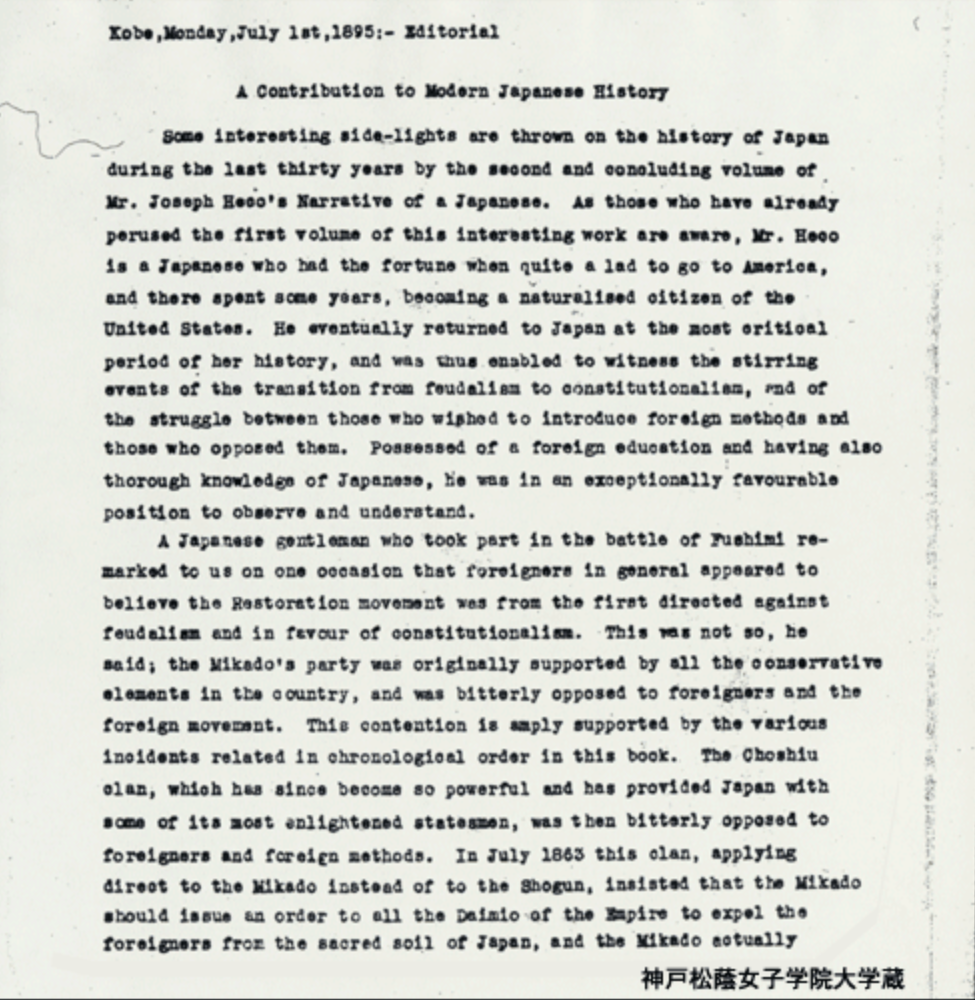
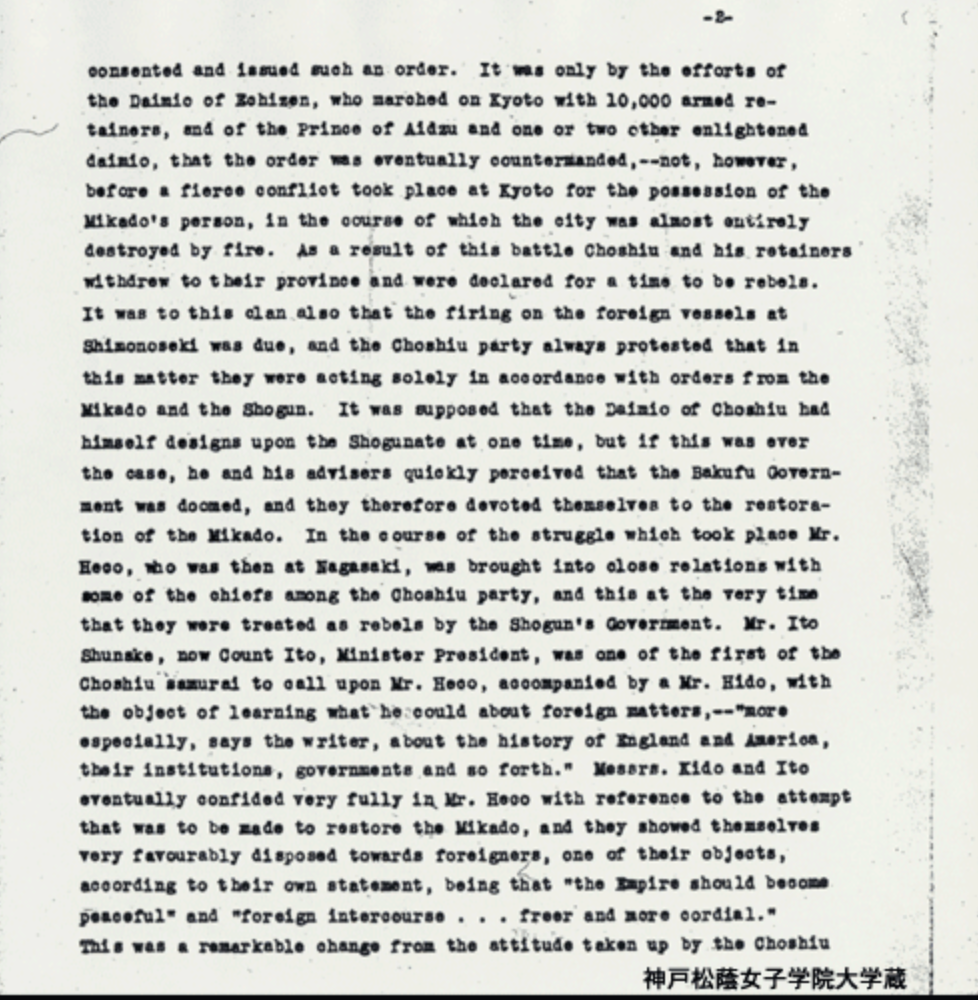
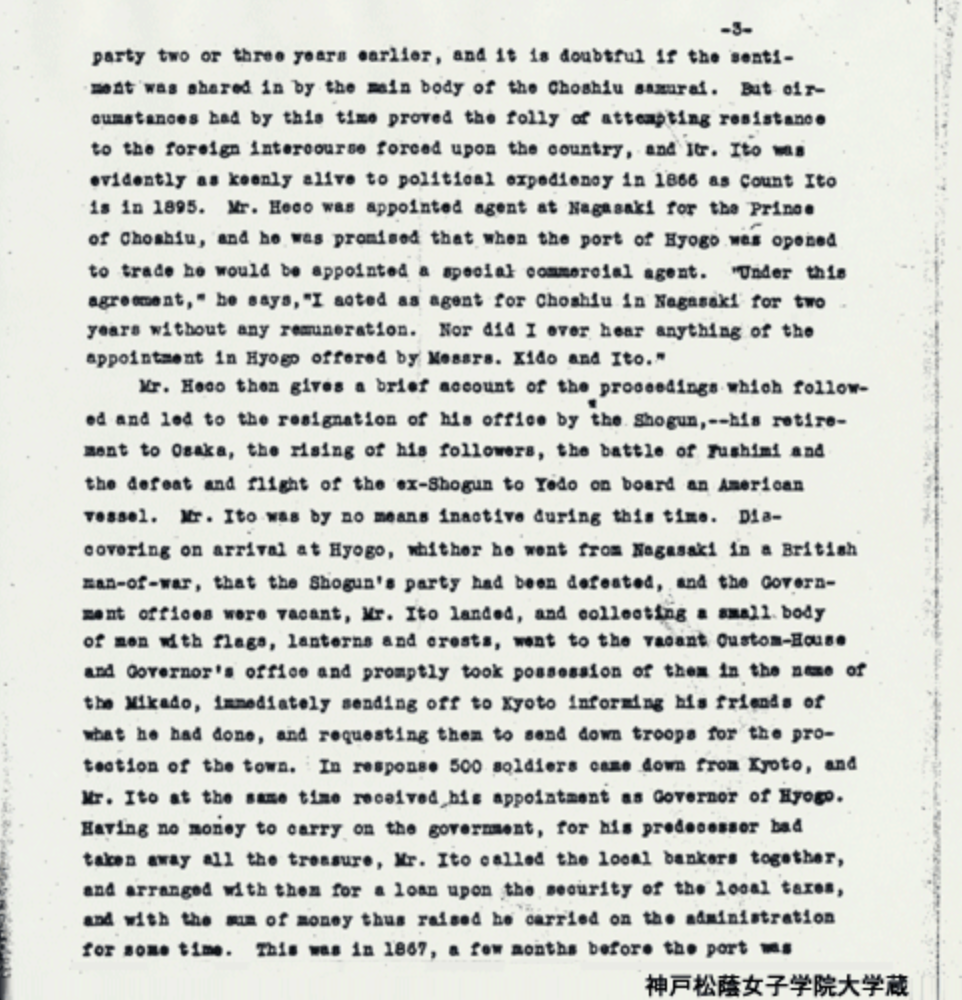
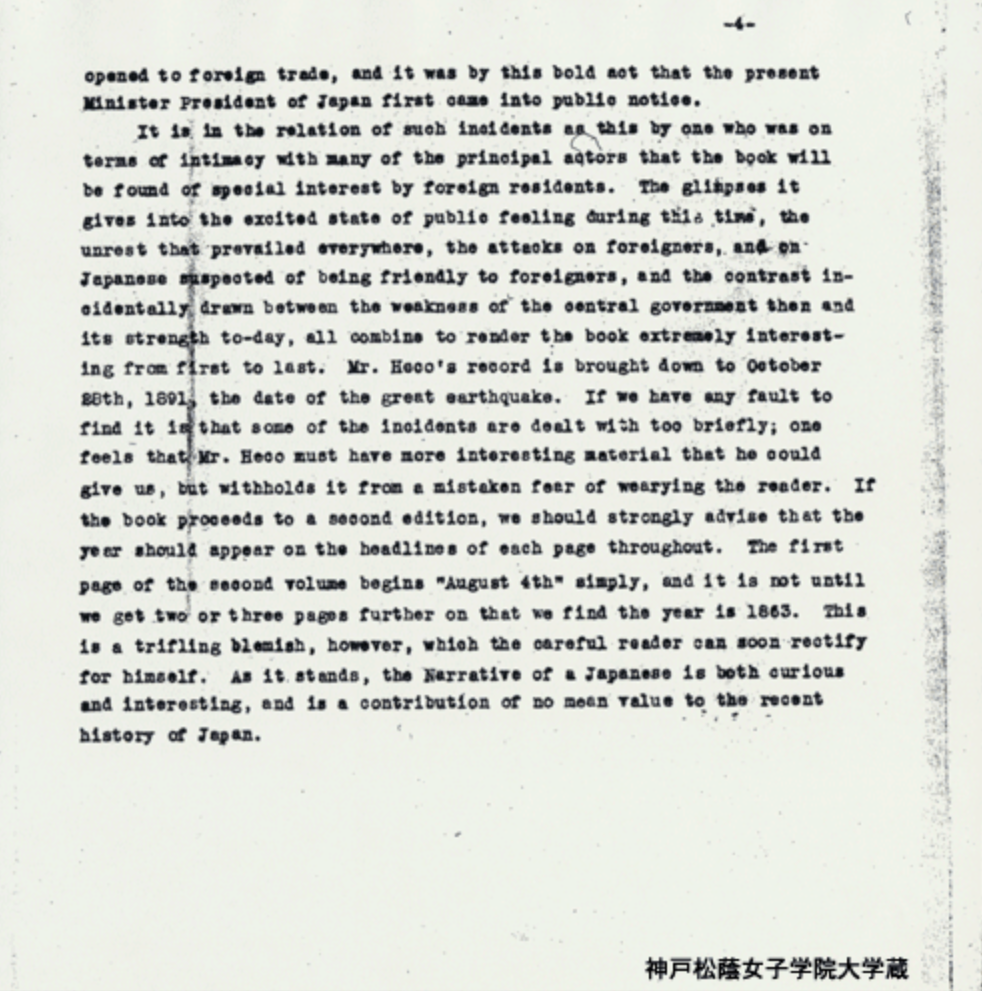

次の文は、神戸の一住民【注1】によって近く出版予定の日本に関する新しい作品の見本刷りから採録したもので『柔術』と題する一小論の結論である――
以上の小論は二年前に書かれたものである。その後の政治的出来事や新条約の調印が、昨年、これを書き改めざるを得なくさせたが、さらに今、手元でゲラ刷りに目を通している間に、清国との戦争事変がさらに数語の書き加えを余儀無くしている。
一八九三年【注2】には誰も予言出来そうもなかったことを、一八九五年【注3】には全世界が驚きと称賛を以て承認している。日本はその柔術に於いて勝利したのである。日本の自治権は事実上回復され、文明諸国間に於けるその地位は保障された。日本は西洋の監督からは永遠に離脱したのである。
—
1894年12月18日 火曜日 神戸 —

1894年12月18日 火曜日 神戸
次の文は、神戸の一住民【注1】によって近く出版予定の日本に関する新しい作品の見本刷りから採録したもので『柔術』と題する一小論の結論である――
以上の小論は二年前に書かれたものである。その後の政治的出来事や新条約の調印が、昨年、これを書き改めざるを得なくさせたが、さらに今、手元でゲラ刷りに目を通している間に、清国との戦争事変がさらに数語の書き加えを余儀無くしている。
一八九三年【注2】には誰も予言出来そうもなかったことを、一八九五年【注3】には全世界が驚きと称賛を以て承認している。日本はその柔術に於いて勝利したのである。日本の自治権は事実上回復され、文明諸国間に於けるその地位は保障された。日本は西洋の監督からは永遠に離脱したのである。
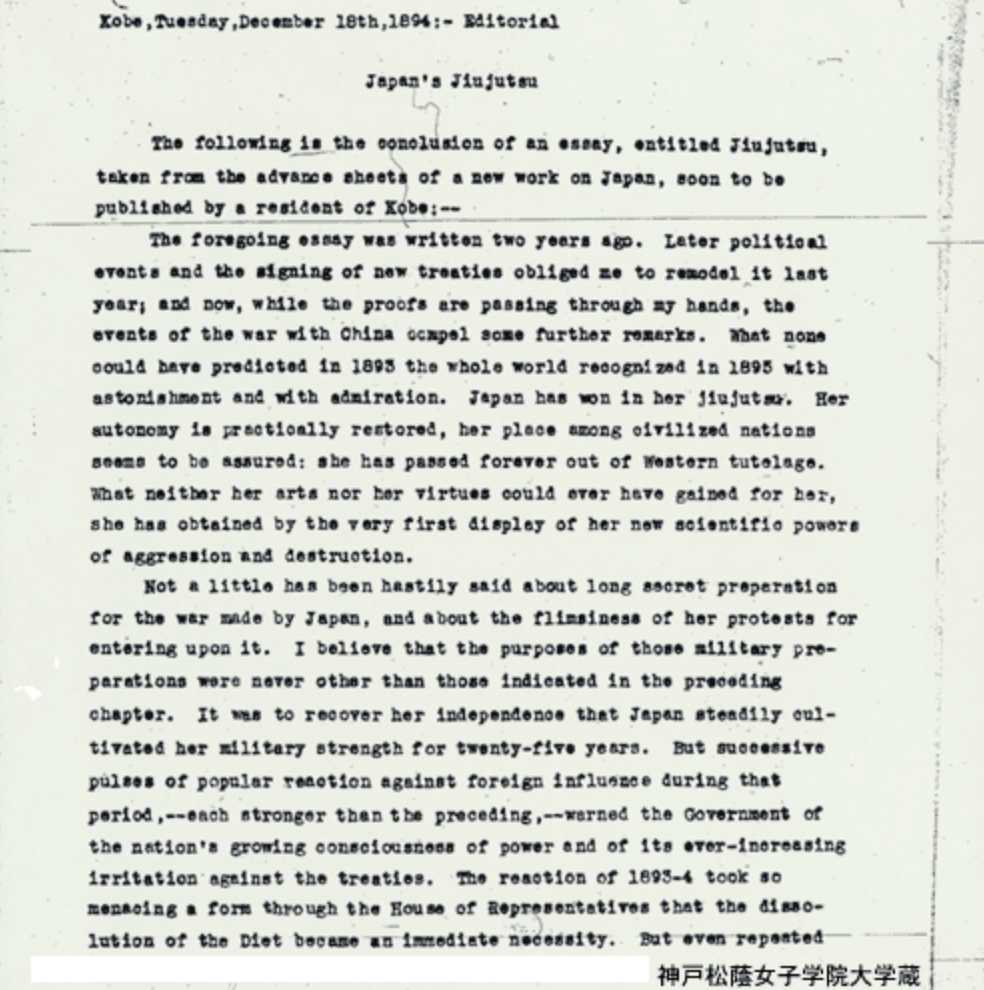
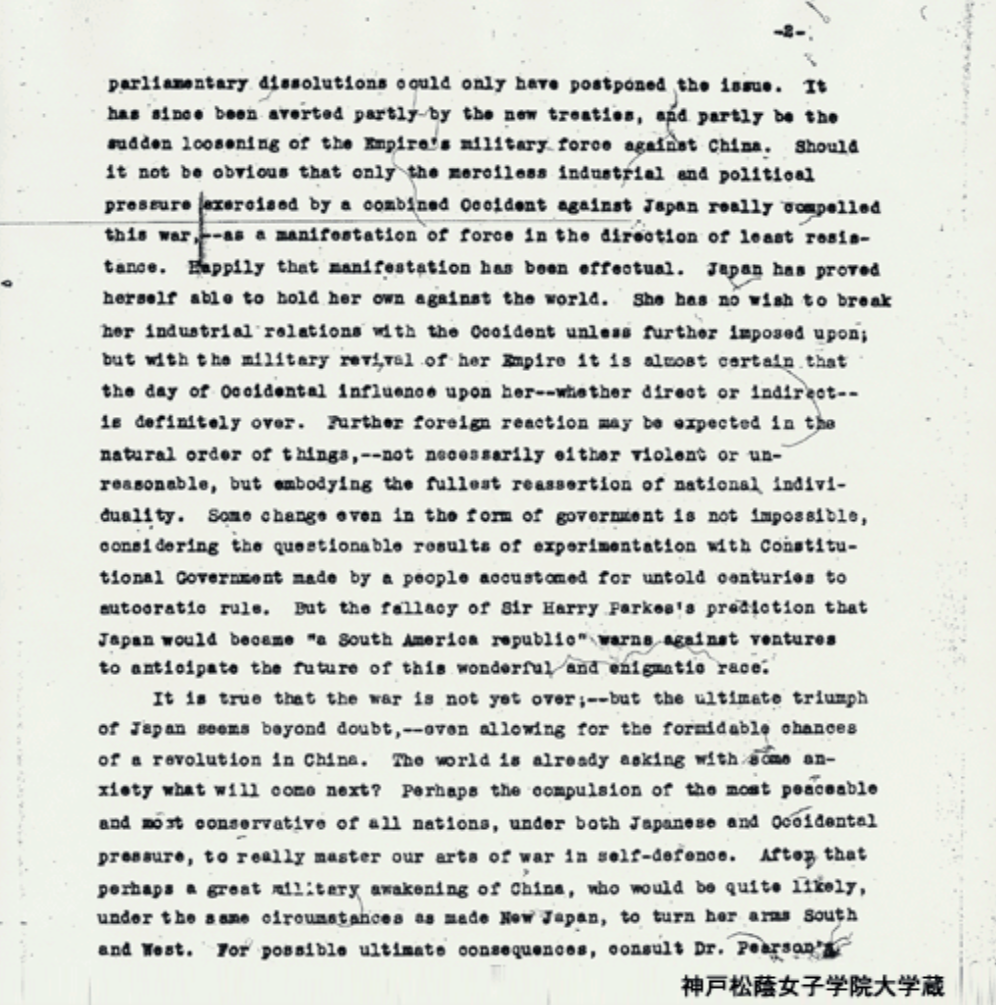
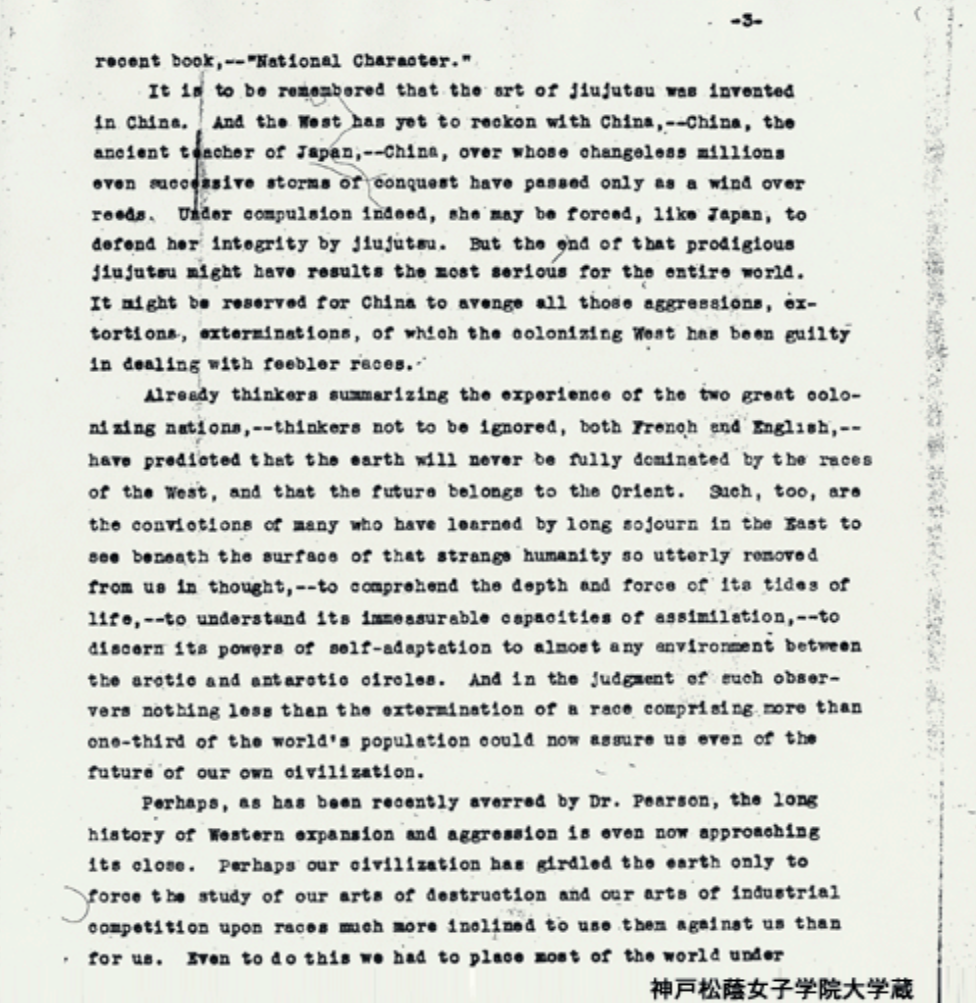
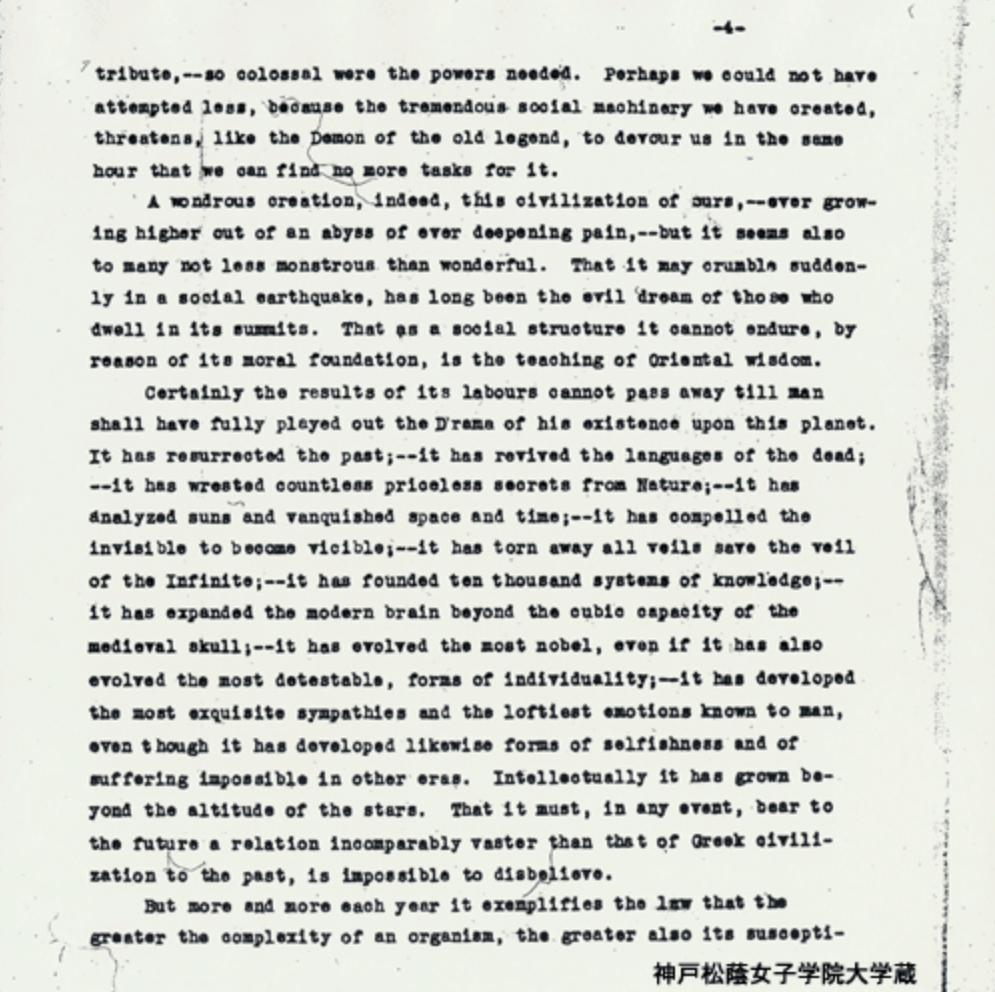

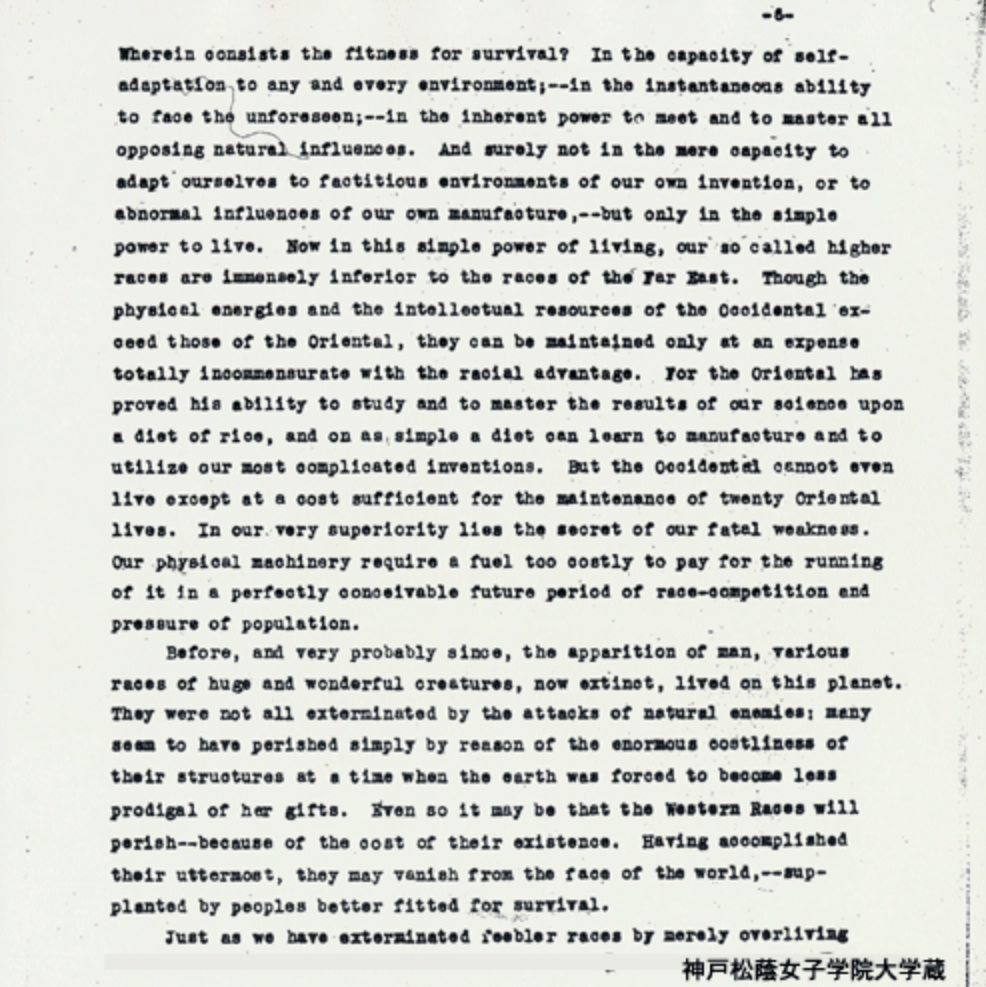
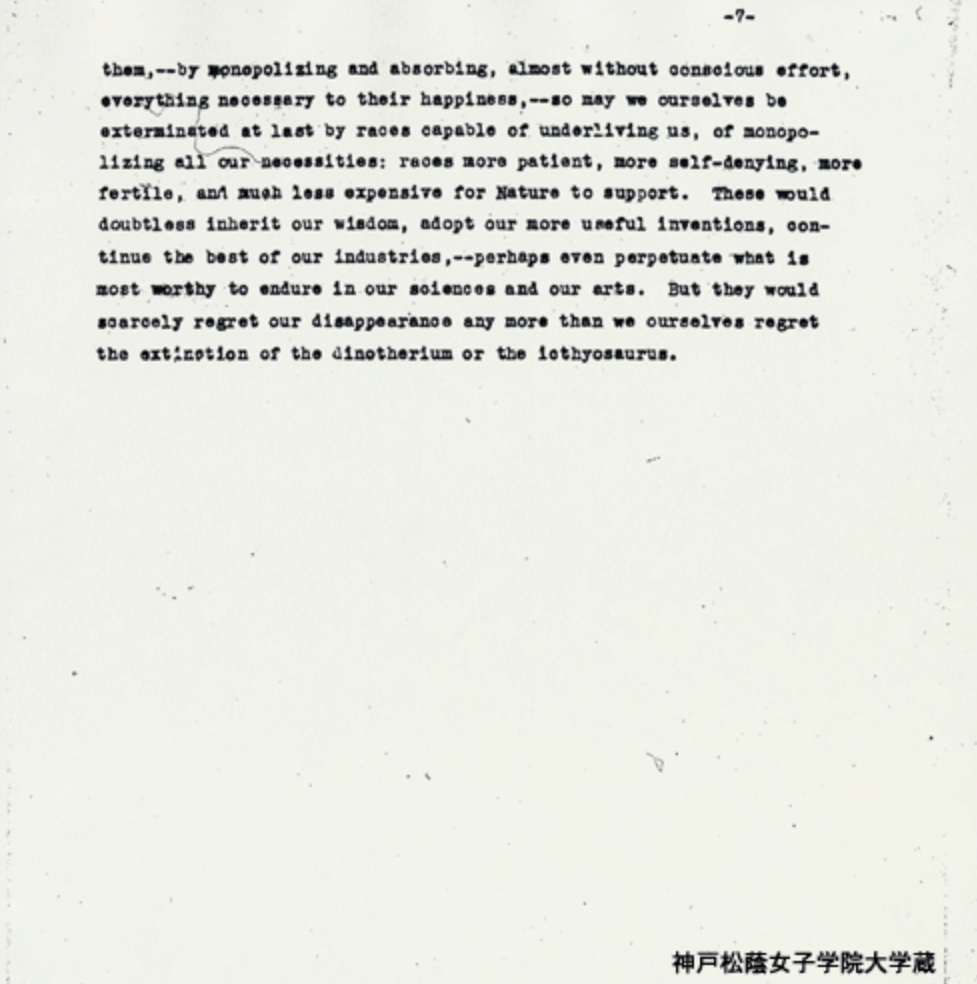

不利な状況に逆らって戦っている個人にとっても、国家にとっても、敵の意見のほうが、しばしば、友人からの励ましよりもいっそう値打ちがあるものである。友人はなし終わったことを称賛する。敵はしばしば、その批判の際の不公平さが考え抜かれた末のものであることから、つかみ取るべき機会、避けるべき失策を知らせてくれる。
日本の勝利についての『サタデー・レビュー』誌、九月二十二日発行号での無作法な言説は、日本の真の力が明らかになるずっと前のものだが、敵意のある批判に付き物の特別な値打ちを持つように、我々には思える。
— 1894年12月7日 金曜日 神戸 —
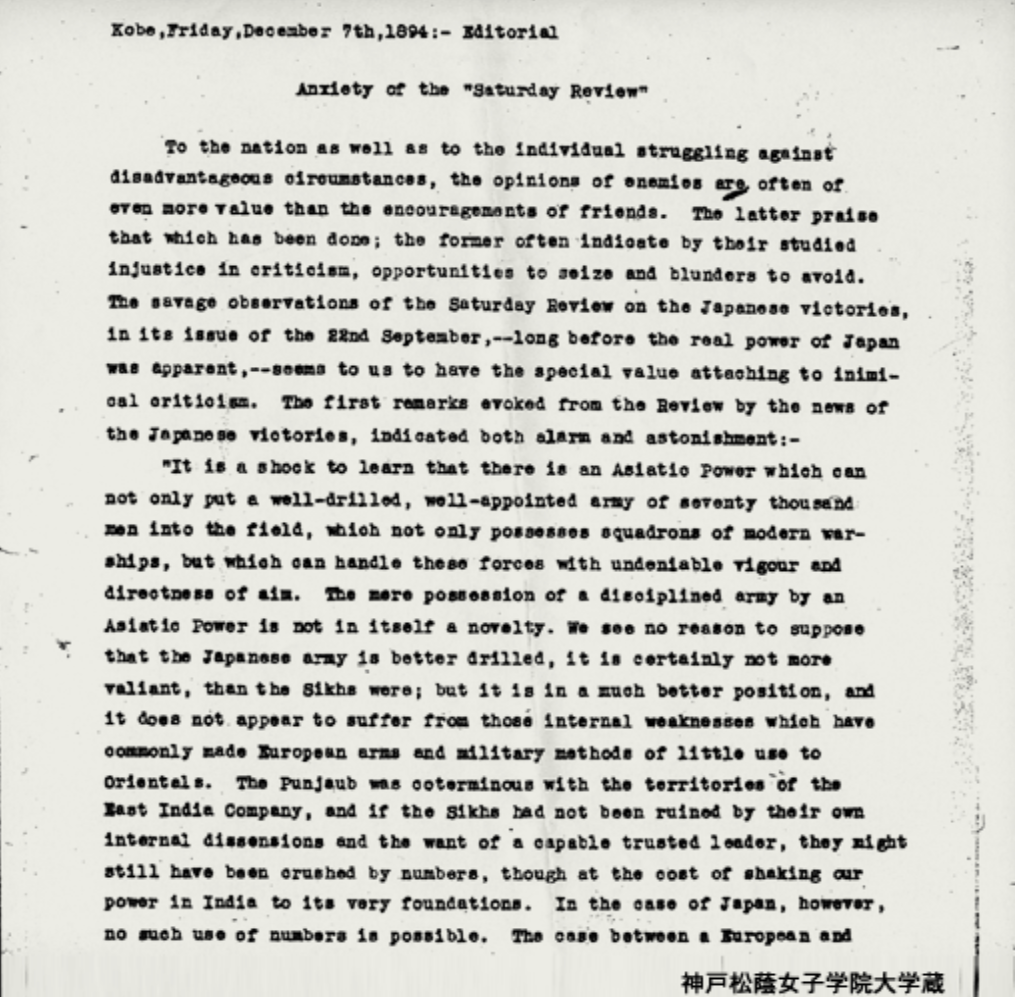
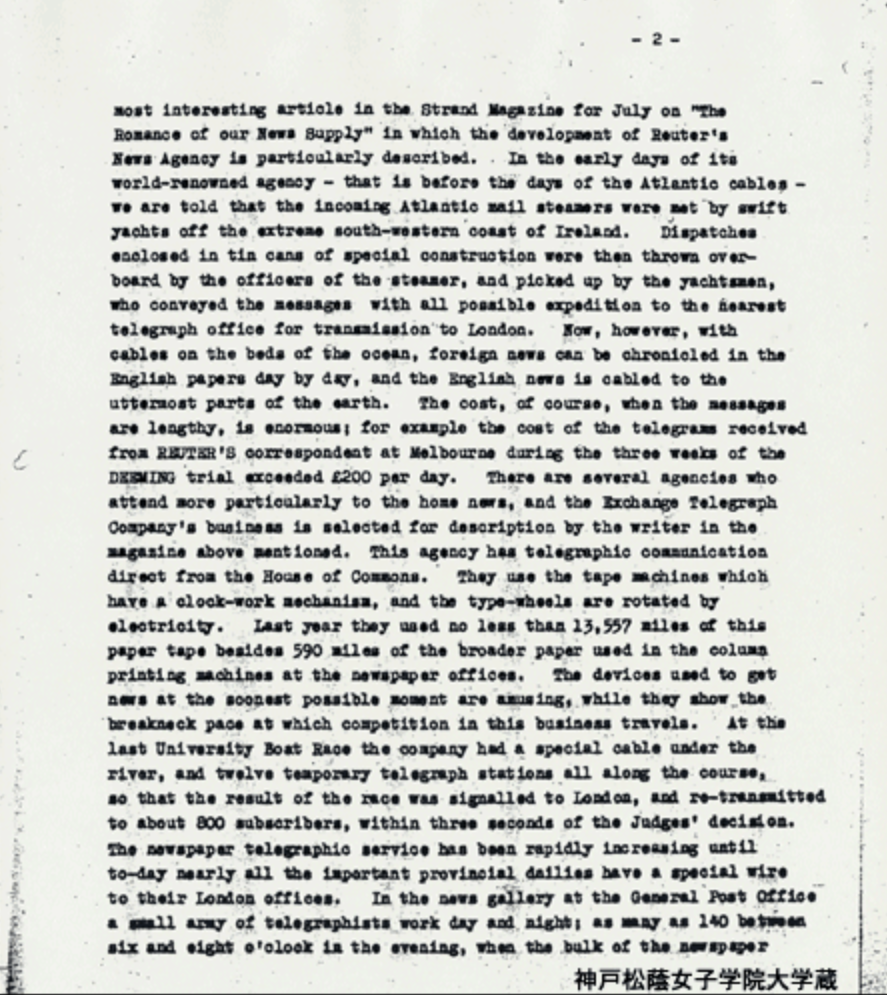
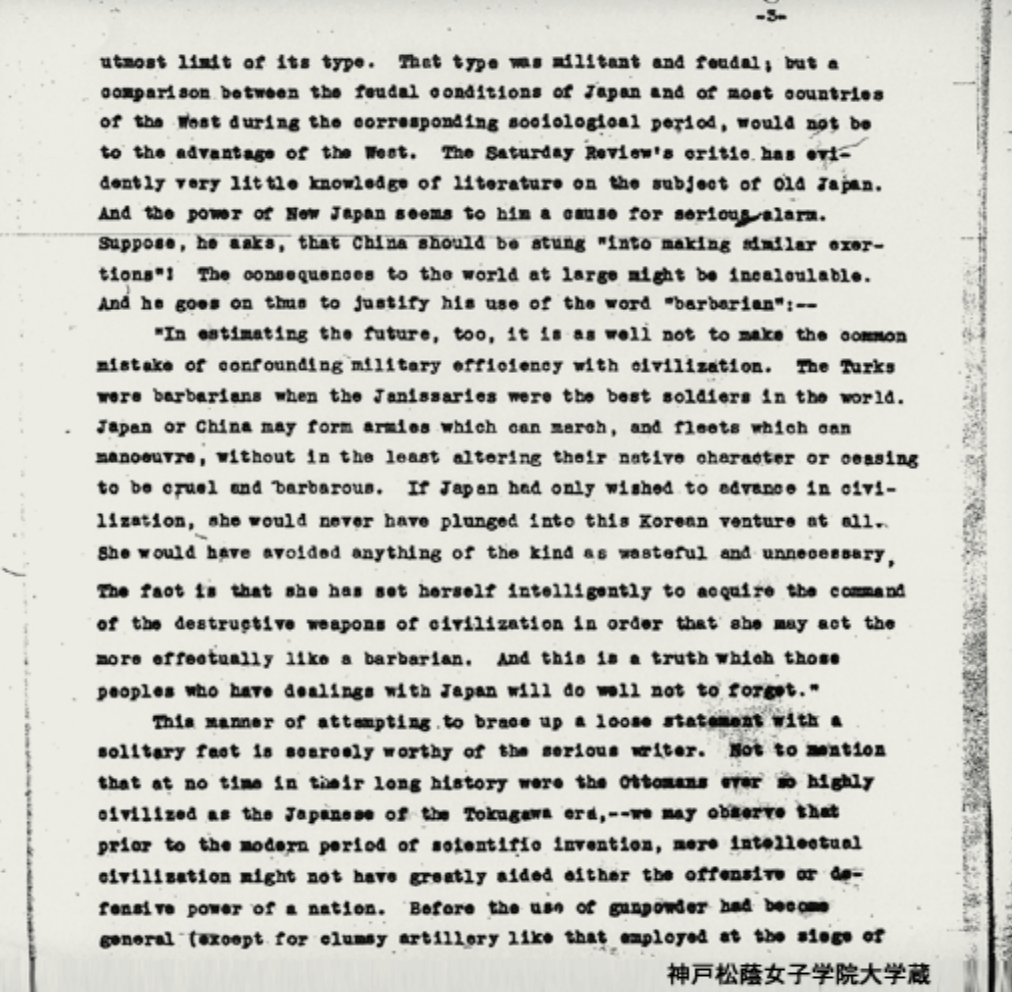
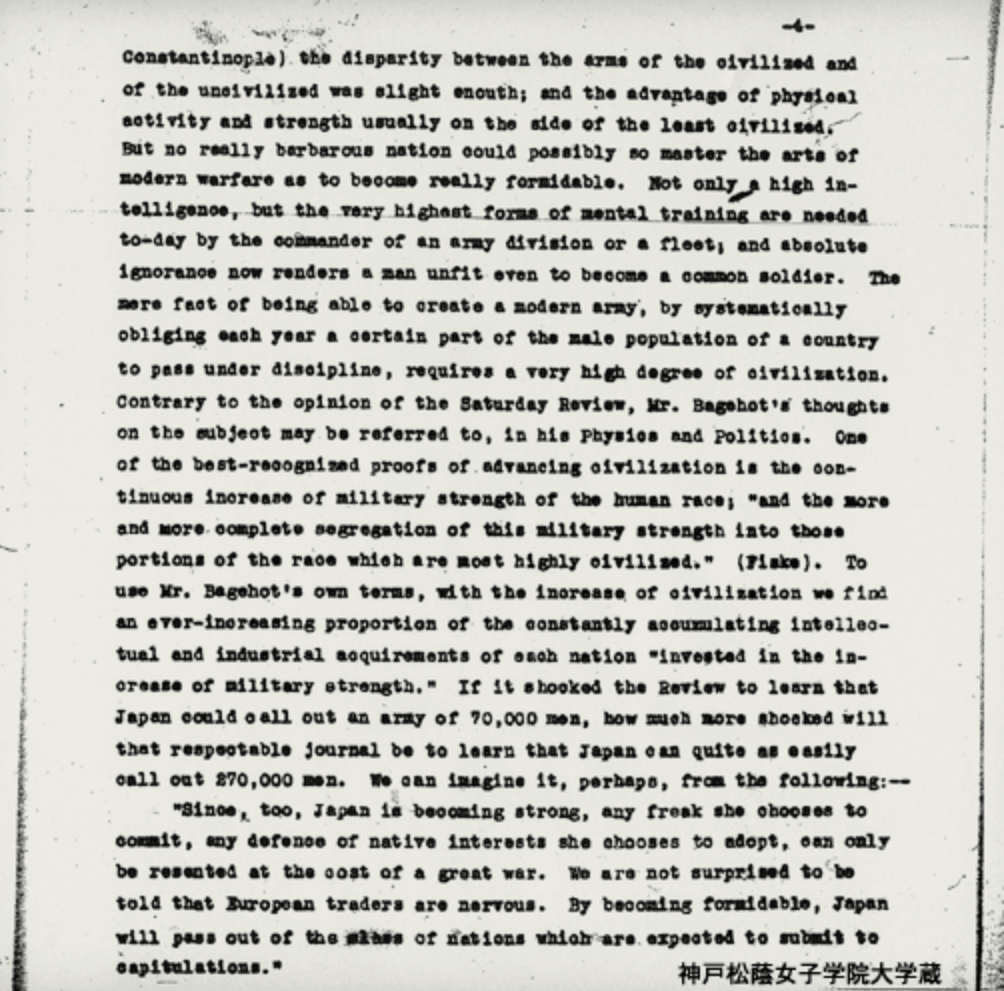
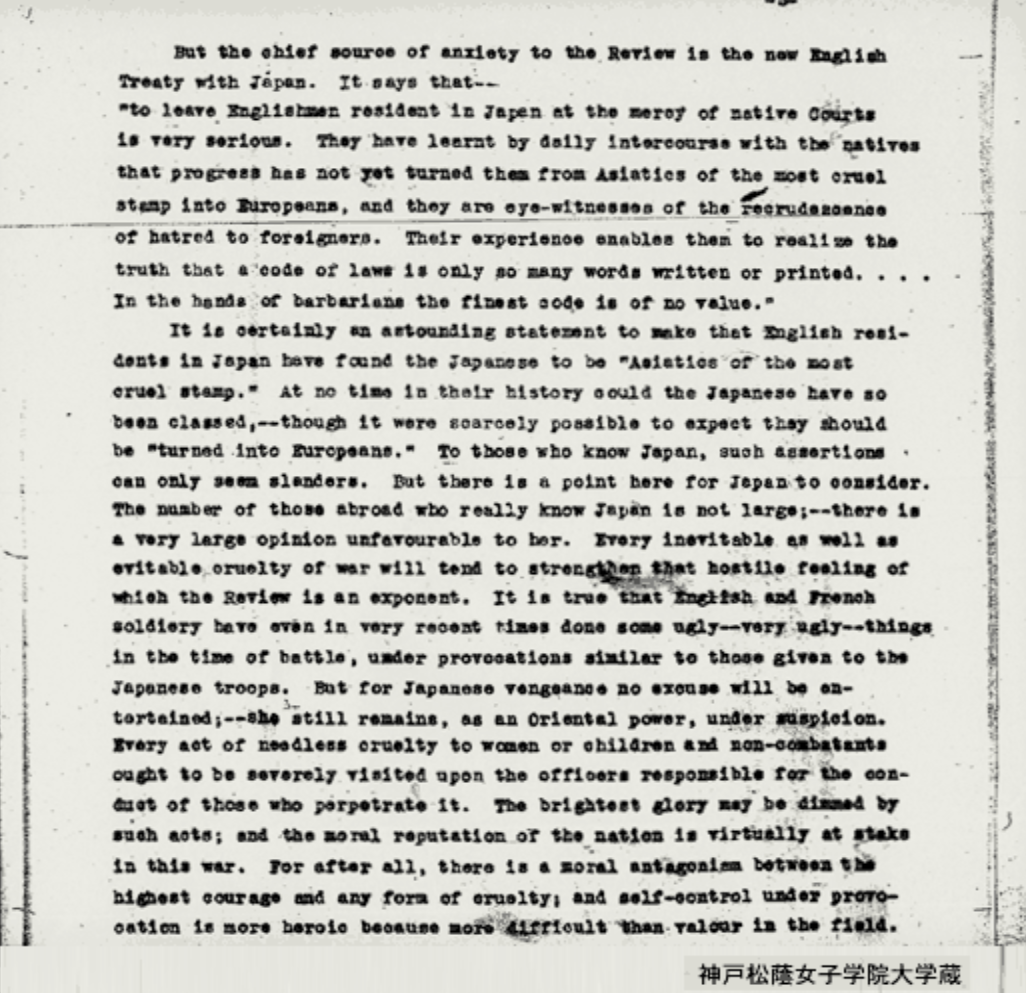

一般の旅客をば、その旅客が時折それに案内を願ひそれに助力を乞ひ或はそれに低廉な乗り物を頼まなければならぬ人達に瞞着されないやう、どう保護すべきか、これは極めて古い問題であつて、そして西洋のどの国でも未だ完全に解決されてゐないものである。例へば、倫敦でのまた巴里での辻馬(キヤツブ)車に関する規定は事件を非常に改善したかも知れない。しかしそれは決して外来人に、種々様々な瞞着にかからぬ保証を与へては居らぬ。法定賃金は一哩につきいくらといふことを知つて居ることは、その都市の地形を知つて居る者にだけ価値のあり得るもので、稍々正確に近く距離を見積もることが出来る。ところで一時間いくらといふ直段の制定は、自分は正しい方向指して乗つて居るのかどうか判からない人達には、殆ど何の利益にもなり得ない。
— 1894年11月11日 土曜日 神戸 —
手紙原文の英文は、
「The Writings of Lafcadio Hearn in Sixteen Volumes, Houghton Mifflin Company, 1922」「The Life and Letters of
Lafcadio Hearn by Elizabeth Bisland. Houghton Mifflin
Company」から採り、和訳は監修者による。ハーンの年譜は主として恒文社刊「ラフカディオ・ハーン著作集・全15巻。生誕130年記念出版」に拠っている。「注」とあるのは監修者による補足・説明である。
— 1894年12月7日 金曜日 神戸 —
「ハーンが書いていた頃は、このデイリー版で発刊されていた。」
参考:神戸クロニクルウィークリー版




ギリシャに生まれ、欧米を経て日本に辿りついたラフカディオ・ハーン、日本では横浜から松江、熊本を経て神戸にやって来ました。
※クリックすると詳細が見れます



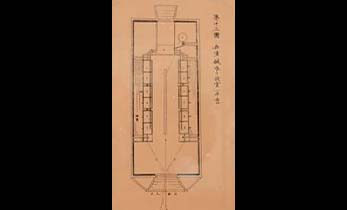












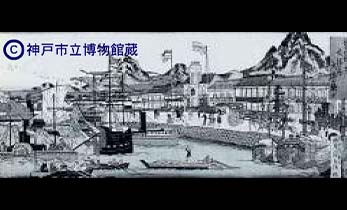





ラフカディオ・ハーンは、一八五〇年六月二十七日、ギリシャ西岸のイオニア海に浮かぶ小島レフカダに生まれた。ラフカディオという珍しい名は、この島の別名ラフカディアあるいはレフカディアに因んでいる。
父のチャールズ・ブッシュ・ハーンは、いわゆるアングロ・アイリッシュつまりアイルランド生まれのイギリス人で、陸軍軍医として当時、英国の保護領であったチェリゴ島に駐屯していた。母のローザ・カシマチはこの島に生まれたギリシャ人で、二人はここで知り合った後、チャールズの転任にともない近くのレフカダに移り、式を挙げた。
ハーンは、父のチャールズが英領西インド諸島に赴任した後に生まれたので、二歳までこの島で母と二人きりで暮らした。この頃の思い出は、おぼろ気ながらも生涯でもっとも幸福な時代の記憶としてハーンの心に深く刻みこまれたようである。
やがて母子は、アイルランドのダブリンにあるチャールズの家に身を寄せるが、言語・習慣・宗教・気候すべてが違う生活にローザはどうしても馴染めず、精神的な安定を欠くようになる。それは夫の帰還後も好転せず、一八五四年、チャールズがクリミアに出征している間に、ふたたび身重になったローザは、四歳のラフカディオを残し、ギリシャに帰国してしまう。この後、ハーンは二度と母親に会えなかった。
それ以前からダブリンでのローザの淋しい境遇に同情し、不在がちで無神経な夫に代わり、母子の面倒を見ていたのがチャールズの叔母サラ・ブレナンで、ローザの帰国後、ハーンはこの人に引き取られた。
クリミア戦争から帰還したチャールズは、別の女性と再婚するため、帰国中のローザを一方的に離婚し、一八五七年、新しい妻を連れインドに赴任した。(四年後、チャールズの後妻はインドで病死し、さらにその五年後、チャールズも帰国途上の船で病死した。母のローザは、ギリシャで再婚し、一八八二年コルフ島で病没するが、ハーンはローザの正確な消息はもちろん、生死すら知らなかった。)幼い頃に父母と生き別れになったことは、ハーンの心に生涯、癒しがたい傷を残した。
ブレナン夫人は、子供のない裕福な未亡人だったので、ハーンを立派なカトリック教徒の跡取りに育て上げようとした。一八六三年、十三歳のハーンは、イングランドのダラム州アショーにある聖カスバート校に入学する。そこでの厳格なカトリック教育には反発したが、その一方で周囲からは、奇抜な悪戯をする明るい少年と見られていたらしい。学校では読書と作文を愛した。そんなハーンにふたたび不幸が襲いかかる。まず十六歳の時、遊戯中、ロープの結び目が顔に当たり、その結果、ハーンの左眼は醜く白濁し、視力も失うことになる。つづいて翌年、ブレナン夫人が親類の投資の失敗により大部分の財産を失い、ハーンは学校を退学する。
なお、このカスバート校在学の前か後に短期間、フランスの寄宿学校に入れられていたらしいが、その時期も場所もはっきりしていない。また、十七歳から十九歳まで――学校をやめ単身渡米するまでの行動についても、大叔母の元女中の家に寄宿し、ロンドンをあてどもなくさまよっていたらしいこと以外、詳しいことは分かっていない。
いずれにせよ、ハーンの少年期は凄まじいほどの不幸の連続だった。四歳で母と生き別れ、七歳で父に棄てられ、莫大な財産の跡取りとして育てられながら、身内の者の奸計により一夜にして文無しの浮浪児同然の境涯に落とされた。純真な愛への渇望と強烈な猜疑心、それに加えて左眼の失明は、残った右眼の視力を蝕んだだけでなく、性格的にもハーンをいっそう内気で感じやすい少年にした。
そうした幼少の頃に受けた心の傷をなまなましく語った手紙が三通、残されている。そのうち二通は、日本に渡る直前に、実弟ジェームズ・ハーンに宛てられたもの、もう一通は、熊本時代に異母妹ミニー・アトキンスンに宛てて書かれたものである。
この三通の書簡が重要なのは、弟や妹の記憶を引き出そうと、ハーンが、いわば呼び水を注ぐような形で思い起こせるかぎりの出来事を書き綴っているからだが、しかし、その語り口の熱っぽさとは裏腹に、内容自体は、驚くほど貧弱で誤りも多く、はたして実際の記憶と見なしてよいのか疑わしい箇所もある。
ハーンは母親の旧姓がローザで、再婚後はスミルナへ渡ったものと信じていた。そして遙か以前にコルフの島で亡くなっていることも知らなかった。一枚の肖像写真すら所持せず、容姿については、黒い髪、浅黒い膚、野生の鹿のように大きな眼を覚えているだけだった。
ハーンがそんなおぼろ気な記憶にこだわりつづけたのも、母だけは本当に自分を愛してくれたという思い――厳密に言えば、きっと愛してくれたはずだという思いこみのためであり、さらには、ダブリンのハーン家の人々は、父にせよ大叔母にせよ、結局は自分を邪魔にし見捨てたという事実のためだった。かりに母の旧姓はカシマチで、離婚ののちはチェリゴ島に暮らしたと知り得たところで、それはハーンが物心ついてから絶え間無く反芻していた悲哀をいささかも和らげてくれなかったろう。
したがって、これら幼年期の回想は、たんなる伝記資料としてよりも、むしろハーンの文学に底深く流れる悲調の源を見きわめようとするとき重要になってくる。この三つの手紙が教えてくれるのは、唯一の愛の対象を奪われた幼い頃の心の傷跡が、すでに中年にさしかかった作家の胸に、これほどの怒りと悲しみを与えていたという、信じがたいような事実なのである。「厳格で怖しい顔」をした「強い、計算高い」父が、「浅黒い膚」の「温かい心と愛する力をもった」母を、幼い無力な自分から奪い取ったという恨みは、ハーンの人生と文学を最後まで呪縛していた。
憎むべき父なる西洋、愛おしい母なる東洋(ハーンはローザにオリエントの血が流れていると信じていた)、そして両者の悲劇的な争いを傍観するだけの無力な自分。この三つの基調と構図は、ハーンの残したさまざまな時と所の作品の中にたやすく見出せよう。ハーンの芸術の根底には、常に、失われた母への鎮魂の歌と父に対する断罪の叫びが、低く強く響いている。
シンシナティの波止場の生活や黒人社会を描くルポルタージュから、遺作となった『神国日本』に至るまで、ハーンの著作のすべては見事なほど一貫して、非西洋人への共感と異文化の理解を志向し――そして余人の追随を許さぬほどの成果をあげつづけたが、その原因としてまず指摘してよいのが、この無意識の衝動――一般の西洋人とはまったく逆の心情であろう。
遠田勝
日本IBM『無限大 No.88』より
返事を待ちかねていた。読んで大いに喜び、また大いに悲しんだ――本当のお前を肌身に感じられたのはうれしかったが、お前が好ましからぬ世界とも関係したと知って、とても悲しくなった。それでも、お前は奮起して、今は誰の世話にもなっていないようだ――もうどこから見ても立派な一人前の男だ!母方からか、父方からか、私たちは優れた素質を授かっている。お前の身を案じるたびに、「達者でさえいれば、どんなことがあってもお母さんの血が守り支えてくれるはずだ」と自分に言いきかせていた。いつもお前のことを、自分の分身、お母さんの生命(いのち)を受け継ぐ、もうひとつの高度な神経組織と思ってきたからだ。それどころか、今では私より強い人間に思える。私には到底真似のできぬことをしてきたのだから。

奥さんと赤ちゃんの写真、有難う。奥さんの顔には優しい心根と淑やかさがあふれていて、とても気に入った。それよりも赤ん坊だ!お前の子供だとは、とても信じられないぞ。誓ってもいいが、これは私の赤ちゃんだ! 眼もちゃんとある――いいかい、グレイシィの眼にはくれぐれも気をつけなけりゃいけないぞ。学校で勉強するようになったら、机にかがませないこと、いや、そもそも前かがみになって読み書きさせないことだ。私が父親になったら、子供は十七、八になって、大学か実業学校にゆけるようになるまでは、学校にやらないつもりだ。最良の教育は家庭でなされる。私たちの知る最も偉大な人物には、例えばハーバード・スペンサーのように、学校生活とは無縁の人が多い。でも、この問題について、あれこれ話し合う時間はたっぷりとある。

遠田勝
日本IBM『無限大 No.88』より
お前の手紙はただ個人的に嬉しかったばかりではない。私の知らなかったことが明らかになり、不意にお前が羨ましくなるほど関心をかき立てられた。私は親類について何も知らないのだ――名前も場所も職業も、その年さえ知らない。だからお前の手紙は、その愛らしい魅力とは別に奇妙な具合に私の興味を惹いた。話を続ける前に写真のことでお礼を言っておきたい。あれを見て私は柄にもなく自分が誇らしくなった。こんなに素晴らしい縁者と妖精のような姪まで一人いるとは夢にも思わなかった。私の妻は彼女の写真を盗み、返してくれない。小さい奇妙な日本の額縁に入れ、床と呼ばれる家の神聖な場所に飾ってしまったのだ。これは一種のアルコウヴで、きれいなものだけを飾っておく。大昔(何百年も前)は神様を祀る場所だったが、今では家の中に神棚があるので、床の間はたんに神聖で大切な場所とされている。

一八六九年の春、十九歳になろうとしていたハーンは、アメリカに渡った。ニューヨークを経由して、モリニュークスの義弟が住むオハイオ州シンシナティに落ち着く。そこでいろいろな仕事を転々とし、辛酸を嘗めつくした後、一八七四年、「シンシナティ・インクワィアラー」の事件記者として身を立てた。文学・美術・思想・科学さまざまな主題の記事を書いたが、最も得意としたのは、血なまぐさい犯罪事件やオハイオ河の波止場に群れ棲む貧しい黒人たちの克明なルポルタージュであった。その勤務の合間をぬって、フランスの作家テオフィール、ゴーチェの翻訳にも励んでいた。ハーンは、この後、ニューオーリンズでもマルチニークでも悲惨な生活を体験するが、おそらくその中で最も辛く苦しかったのが、このアメリカに来たばかりの頃、仕事とねぐらを求めてシンシナティの町をさまよった十九、二十歳の頃だと思われる。熊本時代の手紙に、異国妹ミニー・アトキンスンに宛ててアメリカでの生活のあらましを綴ったものがあるが、そこでもやはりシンシナティ時代初期の回想は、ひときわ痛切でなまなましい。
遠田勝
日本IBM『無限大 No.88』より
お前のかわいい心優しい手紙は、クリスマスに着いた。もっとも、この国にはクリスマスがないけれど。お前は、イギリスに暮らせてどのくらい幸せか分からないのか? どうやら分かっていないようだな。お前も外国に長く暮らせば分かるようになるだろう。お前の写真を見た。同じ眼だ。顎も眉も鼻もそっくりだ。私たちは不思議なほどよく似ている――もっともお前はとてもきれいで、私はその正反対だけれど――それは結局、お前のきれいな眼鼻立ちの特徴が、私の場合、極端に出すぎているのと、片眼が醜く失明しているためだ――学校でつぶされたのだ。
遠田勝
日本IBM『無限大 No.88』より
ワトキンさん――私はこの四十八時間、精神的にすっかり参(まい)っていて、とてもあなたと気持ちよく喋れるような具合ではありませんでした。それから、あなたも特にお忙しいようでしたから、自分の頼みを直接口に出しかねていたのです。わざわざ手紙にするのは、筆を執るのが自分の一番の得意ということもありますが、長々と話しこむよりは、手紙を読んでいただいたほうがあなたのお時間をあまり取らずにすみそうだと思ったからです。個人的な問題に赤の他人を巻きこむのがみっともないことは重々承知しております。ただ、機会があれば、あなたのお役に立ちたいという気持ちは私にもあります。この志に免じてお許しください。こんなわがままを言えるのは、ほかに誰もいないのです。もう二度と、こんなお願いで面倒をおかけすることはいたしません。お約束いたします。
遠田勝
日本IBM『無限大 No.88』より
親愛なる御老父。心細いほど広い屋敷の心細いほど広い部屋で、この手紙を認(したた)めています。ミシシッピ河が見渡せます。綿を積んだ小舟の苦しげに喘ぐ機関(エンジン)の音と水上を往来する人々の呼び交わす野太い声が聞こえます。しかしトンプソン・ディーン号は影も形も見えない。今週中の到着は期待できそうにありません。なにしろ今日、ニューオーリンズを出航したばかりというのですから。
遠田勝
日本IBM『無限大 No.88』より
親愛なる御老友。お便りを拝見して、どれほどうれしかったか、とても書き表せません。運悪くメンフィスではお手紙を受け取れませんでした。ずいぶん励みになったろうに、残念です。私のほうは、少しずつ、本当にゆっくりと具合が良くなっています。莫大な富がここには眠っています。鉱石のままの未精製の黄金とも言えましょう。この地こそ、見棄てられ朽ちかけた南の楽園です。これほど美しく悲しいものを、私はこれまでに見たことがありません。初めてルイジアナから上る太陽を見た時には、涙が溢れてとまりませんでした。まるで息絶えた乙女――オレンジの花輪で飾られた今は亡き花嫁――口づけしてくださいと囁(ささや)く少女の死顔のようでした。この朽ち果てた南部が、どれほど麗(うるわ)しく、豊饒(ほうじよう)で、美しいものか、とても言葉では言い表せません。
遠田勝
日本IBM『無限大 No.88』より
親愛なる御老人。あと何日かで二十八歳になります。残すところ、わずか数日、指折りかぞえては怯えております。誕生日が何曜なのか、暦を見るのさえ怖い――金曜日だったら――あの不吉な迷信が忘れられない――迷信のしぶとさには宗教も兜(かぶと)をぬぎます。この二十八年をふり返れば、遠ざかるに従い、暗くぼやけて見えるものの、少なくともここ二十年の歳月の容貌は一つ一つ鮮明に思い出せます。そのすべてに憂うべき特色――そう、不幸という共通の特徴が刻みこまれています。ぼんやりと霞(かす)んだ面影にさえ、不幸の輪郭(りんかく)は、はっきり見て取れる。
遠田勝
日本IBM『無限大 No.88』より
親愛なる御老人。大鴉は近頃、手紙を書くのが大儀(たいぎ)でなりません。厄介なことが少々あるうえに、勉強に身を入れ、旧に倍する著作をこなしています。暇など滅多(めつた)にないのです。なにしろ、この不細工(ぶさいく)でへんてこな眼がまだ治りきっていないのです。夜には書けません。この美しい南国の夜、星の燃え立つ闇につつまれては、文字などとても書けません。古代のギリシャの詩人が「聖夜」とうたった「学徒にとっては、一切が眼となり耳となる、芳(かぐわ)しい香りに満ちた」夜には大鴉は筆を取る気になれません。
遠田勝
日本IBM『無限大 No.88』より
今、大わらわになって東洋の伝説集に取り組んでいるところです――婆羅門(バラモン)、仏教、タルムード、アラビア、中国、ポリネシアなどの説話をまとめ、春までに仕上げたいと思っています。スクリブナーかオズグッドに出版してもらえそうです。おっしゃるような境遇なら、私だって人生も生きてみるに値すると思います。しかし、そんな結構な身分になかなかなれるものではない。私は余所に移ってみたいのです。新たな土地は、新たな暮らしと新たな青春を意味します。ここでは生活の問題という奴に鉄の眼(まなこ)でもって永遠に真正面から睨(にら)みつけられているのです。

ニューヨークで三十七歳の誕生日をひとりシャンペンを飲んで祝ったハーンは、七月初旬、トリニダッド行きの汽船に乗りこみ、西インド諸島を島から島へとめぐる旅を始めたが、その中でもっとも気に入ったのが、マルチニーク島だった。七月三日、親友であるニューオーリンズの医師ルドルフ・マタスに宛ててこう伝えている。
遠田勝
日本IBM『無限大 No.88』より
君からの返事は読みたいけれど、とても間に合わないだろう。この手紙がそちらに着くのには、おそろしく時間がかかる。私は、もうすっかりこの地の虜になり、西インド諸島のどこかに落ち着こうと決意した。マルチニーク島は、この世の楽園としか言いようがない。エロスを除きおよそ悪徳の存在しない島を想像してみたまえ。乱暴者も気取り屋もいない。すべてが原始的で、道徳的に汚れを知らない――ただ一つ、例外はあるけれど、この場合、むしろ純潔を守るほうが自然の秩序を乱すことになるのだ。気候について言えば、神々しいほど素晴らしい――今は最悪の季節、冬期なのだが。 私は、思考においても行動においても、一切の活発さ、機敏・性急さを憎むようになった。あらゆる対立、競争、成功を獲ようとあくせく努力すること自体が嫌になった。ここで暮らせるだけで幸せ、いや、幸せすぎるほどだ!――凡人には過ぎた悦びを味わえるのだから。あたりを眺めただけで嬉しさで泣きたくなるだろう。
遠田勝
日本IBM『無限大 No.88』より
親愛なる友――何日間か郵便船がないと分かったので、ちょっと腰を据(す)えてこの土地について説明してみることにする。君がもっと知りたくなるような、何か面白いことがあるかもしれない。――――マルチニークは山々が海のように浪(なみ)うつ島だ。どの方角を向いても巨大な山脈のうねりが目に入るくらい険(けわ)しい――そこここにピトンという乳房のような形の峰がそそり立ち、辺(あた)りの地勢と鋭い対照をなしている。
遠田勝
日本IBM『無限大 No.88』より
親愛なるミス・アニー――
愉快なことを見聞きし、体験するたびに、あなたがここにいて、一緒に見て楽しめたらと思います。あなたはとても性格の強い子だから、この地の美しい自然がそちらに行って、あなたをしっかり抱きしめれば、あなたの魂はこちらへ来てしまうのではないかと本気で信じています。あなたの小さな博物館のためにマルチニークのお人形を送ろうと思ってました。それからお父さんにはマントルピースに置くシガーホールダーを二つ、高木(こうぼく)状のシダの細工で、これは石炭紀の太古の森を生き延びてきた、抜け目のない木です。ただ防疫のための馬鹿げた交通遮断(しやだん)が続いていて、今のところ、船と連絡をとる手段が見つかりません。でも、もう貰ったものと考えて結構です――きっと送りますから。お猿さんも、もしその熱帯性の体が輸送に耐えられるのならお送りしましょう。
遠田勝
日本IBM『無限大 No.88』より
親愛なるオールデン様―― あなたから頂いた最後の手紙の日付は、二月十三日でした。今日は、七月一七日です。私の原稿をすべて受け取られたのか、私には分かりません――分かったのは、二ヵ月間、著作で得られたのは、わずか百ドルということです。 最初の失敗作による時間と金の損失は、とうとう取り戻せませんでした――それ以来、私はさまざまな悪条件と格闘しなければなりませんでした。病気、ありとあらゆる種類の屈辱、読み物の完全な欠如(図書館はないし、本もまったく手に入らない)、そして五マイル旅する金もなく、何もせずじっと我慢してなければならなかった。その成果にあなたが満足なさらぬのは、分かりきったことです。私とて同じです。精神的に破産したのだと認めざるを得ません――注目に値するものが何ひとつできないのですから……おまけにここには余所者が手を出せるようなものなど全くありません。
遠田勝
日本IBM『無限大 No.88』より
親愛なるオールデン様――
昨夜、写真家のレオン・ジュリーを連れての東北海岸への旅から戻りますと、驚いたことに途中わが友アルヌーが馬車を止め、あなたからの手紙を手渡してくれました。彼は、この小さな世界では貴族に属する人なのに、わざわざ山道をたっぷり一マイルも登って、届けにきてくれたのです。お手紙は、ご期待に違(たが)わず私を楽しませてくれました。
遠田勝
日本IBM『無限大 No.88』より
わが友マタス――
君の三月二十一日付の手紙が、ようやく今日、六月五日に着いたが、それでもやはり嬉しいものだ。西インド諸島から戻って、かれこれ三週間になるが、いつまでここにいるのか自分でも分からない。マルチニークを去る時は心が引き裂かれるような気持ちだった。私が今いるのは、世界で一番美しい町の一つで、親しい友人に囲まれている。眼の前にあるのは、人の最も偉大な努力の成果である素晴らしい光景、ニューヨークのように鉄と電気が荒れ狂っているのではない、優しく穏やかな都会だ。それでも熱帯の自然は、そのあらゆる思い出で四六時中、私につきまとい、私の思いをふたたび青い海の彼方、トルコ石色の大空の下、生い茂る巨大な椰子へ、火山地帯の丘陵へ、褐色(かつしよく)の肌をした女たちのもとへと駆り立てる。遅かれ早かれ熱帯に戻らねばならぬと覚悟している。

ニューヨークで三十七歳の誕生日をひとりシャンペンを飲んで祝ったハーンは、七月初旬、トリニダッド行きの汽船に乗りこみ、西インド諸島を島から島へとめぐる旅を始めたが、その中でもっとも気に入ったのが、マルチニーク島だった。七月三日、親友であるニューオーリンズの医師ルドルフ・マタスに宛ててこう伝えている。
遠田勝
日本IBM『無限大 No.88』より
親愛なる御老父。お案じくださっていたと知り、心からうれしく思いました。私とてあなたを夢みることがたびたびありました。西インド諸島で数年暮らしたあと、カナダを通り、ヴァンクーヴァー経由でこの地〔横浜〕に到着いたしました。何年間かこちらにとどまることになりましょう。金持ちになれませんでした――いやその正反対です。それでも、最終的には独(ひと)り立ちしようと、準備は着々と進めております。ただ、それも体がもてばの話です。今のところ健康は申し分ないのですが、ずいぶん白髪が増え、この六月には四十歳になります。
遠田勝
日本IBM『無限大 No.88』より
親愛なるペイジ――あなたのご希望どおり、すぐに返事を書くことにします。お手紙が着いたのが今日で、私はちょうど日本の聖地杵築から戻ったところです。杵築は、この国でもっとも古く神聖な神社で、そこに入るのを許されたヨーロッパ人は、私以前には一人もいないのですが、私はそこの宮司の方にとても気に入られています。今は旅の途中で家に立ち寄っただけで、またこれから珍しい未知の土地へ出かけるところです。日本でもこの地方は、ことに知られておらず、あのマリー社のガイドブックの編集者に初めて資料を送ったのも、この私なのです。……
遠田勝
日本IBM『無限大 No.88』より
親愛なるチェンバレン――ただ淋(さび)しくて仕方(しかた)がないので、手紙を書いています。ずいぶん勝手なものですね。でもあなたが少しでも面白がって下さるのなら、それもお許しいただけるでしょう。丸一年、日本を留守にしていらっしゃったから、その間に私の心に刻みこまれた出来事などはいかがでしょう。それでは―― 幻は永遠に消え去りましたが、多くの愉快なことの記憶が残っています。日本人について一年前よりずっと多くのことを知りました。それでも彼らがよく分かったとはとても言えません。自分の小さな妻でさえ多少は謎めいています。もっともそれはいつも愛らしい感じを与えてくれるのですが。もちろん夫婦ですから心は通じ合っています。しかし互いの気心とは別に、理解しがたい人種的相違はあります。一例を挙げましょう。私たちは隠岐(おき)で見つけた、没落した士族の可愛い男の子を熊本に連れて帰りました。今では養子のようなもので――学校を通ったり、いろいろしています。
遠田勝
日本IBM『無限大 No.88』より
親愛なるチェンバレン――そろそろ手紙を書く時分だと思いますが、何のニュースもありません。それで私の一日の暮らしぶりを一例としてお目にかけるというのは、いかがでしょうか。あなたになら別に構わないでしょう――もっともあなた以外にはどこの誰にも絶対、書きませんが。 午前六時――小さい目覚しが鳴る。妻が先に起きて私を起す――昔の侍(さむらい)時代のきちんとした挨拶で。私は起きて坐る。蒲団のわきへ火種の消えたことのない火鉢をひきよせて煙草を一服吸いはじめる。下男たちがはいって来、平伏して旦那さまにお早ようございますと言い、それから雨戸を開けはじめる。そのうちにほかの部屋では、小さいお燈明が御先祖様の御位牌と仏壇の前にともされて、お勤めが始まり、御先祖様へお供えをする。(御先祖様の霊はお供物は食べないで――精気をすこし吸うのだそうです。それでお供物はほんのちょっぴりです)。そのころ老人たちはもう庭へ出て、お日様を拝んで、柏手(かしわで)を打って出雲のお祈りの言葉を小声で唱える。私は煙草をやめて、縁側へ出て顔を洗う。
遠田勝
日本IBM『無限大 No.88』より
親愛なるヘンドリック――私はこの数週間、ずっとある出来事をあなたに伝えようと待ち続けていました。予想よりずいぶん遅れましたが、昨夜、私の子供が誕生しました――大きな黒い眼をした、元気な男の子です。外国人というより、日本人に見えます。鼻は私にそっくりですが、他のいくつかの点では母親の特徴が奇妙なぐあいに私のと混じり合っています。赤ん坊は五体満足で、どこにも異常はありません。
六月末から八月末まで家族を連れ、別れを告げるかのように懐かしい出雲を訪ねたハーンは、九月初めに上京、その月末には市ヶ谷富久(とみひさ)町に居(きよ)を構えた。翌一八九七(明治三十)年から一九〇二(明治三十五)年までハーンの生活には表向き書くべきことが、きわめて少ない。九七年に次男の巌(いわお)、九九年に三男清(きよし)が誕生した。夏休みに焼津(やいづ)へ避暑に出かけるほかは、ほとんど外出も旅行もしなかった。著作は毎年一冊ずつ『仏の畑の落穂』『異国情緒と回顧』『霊の日本』『影』『日本雑録』『骨董』と不気味なほど規則正しく出版された。これらが帝国大学での連日の授業(死後、アメリカで四冊の講義録として出版されるほど優れていた)と並行して書きつづられたのだから、その単調な生活の背後に鬼気迫るような努力が潜んでいたことは、容易に推察される。深夜、咳(せ)きこみながら執筆に励むハーンの姿を友人の雨森信成(あめのもりのぶしげ)は「さながらこの世ならぬ何者かと情を通じているかのようだった」(平川、前掲書)と書いている。こうした閉じ籠(こ)もりがちの生活だったから、著作にも当然、紀行文の類は影をひそめ、代わって回想や随想、それに古い物語の再話などが多くなった。なかでも晩年のハーンは好んで怪談を筆にした。なぜ幽霊が大切なのか、合理主義で凝(こ)り固まったチェンバレンに宛てて正面から怪談の価値を擁護した珍しい文章が残っている。一八九三年十二月十四日、熊本時代の後半に書かれた手紙の一節である。
遠田勝
日本IBM『無限大 No.88』より
親愛なるチェンバレン――あなたが子供の頃に感じた暗闇の恐怖という、お手紙の一節がずっと気にかかっていました。またいつか話をしようと思っていましたが、ちょうど今、百枚もの作文の添削(てんさく)を終えたところです。いい機会ですから、それについてお喋りいたしましょう。――中略――さて子供の頃、悪夢ははっきりと目に見える形をとって私の前に現れました。私は起きている時にそれを見たのです。連中は音もなく歩き回り、私に恐ろしい顔をして見せました。あいにくその頃、私には母がいませんでした――年老いた大叔母がいて、この人には自分の子供がなく、迷信を憎んでいました。暗闇の中で恐怖に悲鳴をあげても、鞭(むち)で叩かれるだけでした。しかし鞭よりも幽霊のほうが怖かった――なぜなら私には幽霊が見えたからです。大叔母は私の言うことを信じませんでしたが、召使いたちは信じてくれて、こっそりやって来ては私を慰めてくれました。少し大きくなるとすぐに私は学校に預けられましたが、その方がうれしかった――ずいぶんひどい扱いを受けたけれど、そこには夜、幽霊でない友達がいたから。だんだと幻影は消えていきました――十歳か十一歳の頃、私は怖がるのをやめました。昔の恐怖が蘇(よみがえ)るのは、今では夢の中だけです。今、私は幽霊を信じています。それは私がかつて見たからでしょうか?いいえ違います。私は幽霊を信じるが、魂という奴は信じない。私が幽霊を信じるのは、現代の世界に幽霊がいなくなってしまったからです。幽霊に満ち満ちた世界とそうでない世界の違いを考えれば、幽霊が、あるいは神々が何を意味しているのか私たちにも分かるはずです。 例のピアソンの本の耐えがたい憂鬱さは、次の文句に尽きるように思います――「希望を抱かせるものは永遠に人生から消え去ってしまった」これは恐ろしいほど真実です。何が人生に希望を抱かせてくれていたのでしょうか?幽霊です。その一部は神々と呼ばれ、また悪魔、天使とも呼ばれていました――彼らこそが人のためにこの世の有り様を変えてくれたのです。彼らこそが人に勇気と目的を与えていたのです。自然への畏敬を教え、それがやがては愛に変わった――彼らが万物を見えざる生命の感覚と活動とで満たしていた――彼らこそが恐怖と美を造りあげていたのです。 もはや幽霊も天使も悪魔も神々もいません。すべて死に絶えてしまいました。電気と蒸気と数学の世界は、虚(むな)しく冷たく空っぽです。これを文章にできる者など一人もいません。ここにロマンスのかけらなりとも見出せる者がいるでしょうか?われわれの小説家たちは何をしているでしょうか?クロフォードは、イタリアやインドや古代ペルシャについて書かなくてはなりません――キプリングはインドを――ブラックスはスコットランドの片田舎の生活を――ジェイムズは卓越した心理研究者として生きているに過ぎません、そして当人も小説の登場人物たちも大陸で暮らさざるを得ないのです――ハウエルズなどは、はかない民主主義国の最も醜悪な俗事を写生しています。いかなる偉大な人物が上流社会について読むに値する作品を書いているでしょうか、また書き得るでしょうか?今の中産階級についても、大都市の貧民についても同じことです。『ギンクスズ・ベイビー』のスタイルでも蒸(む)し返しますか?答えは否(ノー)です!いやしくも作家たる者は、その題材を今なお幽霊のとどまり棲む国に求めなくてはなりません。――後略――
遠田勝
日本IBM『無限大 No.88』より
小ママ。ゴメンゴメン。アナタヲ少シ喜バセルト思ヒマシタ。アノ地蔵ハ墓場ノ地蔵デハナイ。波ヲ馴(な)ラシテ静カニスル地蔵デス。悪イモノデハナイ。然(しか)シアナタハ好(す)カナイ。ソレナラ一雄ノ名モ私ノ名モドンナ名モ書キマセン。 唯(ただ)私ノ考ガ馬鹿デシタ。地蔵様ハアナタノ疑フノヲ聞イタ時大泣キシマシタ。私ハ唯(ただ)海ヲ大事ニスル地蔵ダト言ヒマシタ。『仕方ガナイ。アノ子供ノ母ガアナタヲ疑フ』ト私ハ地蔵ニ言ヒ聞カセマシタ。デスカラ今デモ泣イテ居マス。パパカラ、ゴメン――ゴメン。 石ノ涙ヲコボシテアノ地蔵ハ泣イテ居マス。
遠田勝
日本IBM『無限大 No.88』より
このささやかな書簡集には、ハーンの作品と生涯を理解する上で重要と思われる二十数通の手紙を各時代から選び、蛇足(だそく)になることを恐れながらも、一般読者の便宜のために、あえてその間に解説めいた文章を挟(はさ)みこんでみた。年譜の無味乾燥、書簡集のとっつきにくさを避けるための苦肉の策だが、さいわいハーンは英語文学史上、名にし負け優れたレター・ライターである。その書簡はどれをとっても気取りがなく誠意に溢(あふ)れ、型にとらわれず美しい一一そのおかげでどうにか、通読してもある程度は面白味のある読み物に仕上げられたのではないかと思う。そういう意図で編集したので、伝記や研究書には必ずといっていいほどよく引かれる有名な手紙もいくつか収めたが、ただ、それだけではつまらないと思い、三分の一ほどは、これまで邦訳のなかった手紙を紹介することにした。書簡三と四のアトキンスン夫人宛ての手紙は、近年、中田賢次氏が英国で発見され、八雲会の発行する雑誌「へるん」に発表された英文に拠(よ)っている。また第三章の「クレオールの島」に 収めた六通も、すべて初訳で、こちらは西崎一郎氏が翻刻されたマルチニーク時代の五十通近い書簡から選んだ。これはお茶の水女子大学の紀要に三十年以上も前に発表され、内容も非常に充実しているのに、どういうわけか、翻訳もされず、恒文社の『ラフカディオ・ハーン著作集』にも漏(も)れたまま今日に至っている。この埋もれた業績を広く伝える意味もあり、バランスをくずさぬ程度に、できるだけ多数を訳出しておいた。引用した書簡の英文は、以下の文献に収められている。書簡一、二 H.T. Kneeland, “Lafcadio Hearn’s Brother,” Atlantic Monthly, CXXXI (Jan., 1923).書簡三、四 中田賢次「小泉八雲の未刊行資料一一M・アトキンスン宛書簡」『へるん』二十六号、二十七号。書簡五 O.W. Frost, “Two Unpublished Hearn Letters,” Today’s Japan, V (No.1).書簡六~十、十七 M. Bronner, Letters from the Raven, (New York, Brentano’s, 1907).書簡十一、十二、十六 I. Nisizaki, “Newly Discovered Letters from Lafcadio Hearn to Dr. Rudolph Matas,” Studies in Arts and Cultures (Ochanomizu University), VIII.書簡十三~十五 I. Nisizaki, “New Hearn Letters from the French West Indies,” Studies in Arts and Cultures (Ochanomizu University), XII.なお書簡十八から二十二までの原文はすべてハーンの英文著作集にある。またワトキン及びジェイムズ宛ての書簡の訳文は、恒文社の『ラフカディオ・ハーン著作集第十五巻』に収められた拙訳に依拠している。ハーンの生涯を略述するにあたっては、主に同十五巻所収の銭本健二・小泉凡編の「ラフカディオ・ハーン年譜」、平川祐弘『破られた友情一一ハーンとチェンバレンの日本理解』(新潮社)、エリザベス・スティーブンスン『評伝ラフカディオ・ハーン』(恒文社)、森亮『小泉八雲の文学』(恒文社)を参照した。とくに森氏の簡潔で格調高い「小泉八雲 小伝」には、時代の区分や叙述の範囲を考えるうえで教えられることが多かった。ハーンの著作の邦訳題名も、おおむね氏の用いられたものをそのまま拝借している。以上、記して感謝申し上げる。
開港場の外人居留地は、その極東的な周囲に著しい対照を呈している。その街路の整然たる醜悪さの中に、人は世界の此方側(こっちがわ)には無いはずの場所を思い出させられる――あたかも西洋の断片が魔術的に海を越えて運び来られたかのごとく。――リバープールや、マルセーユや、ニューヨークや、ニューオーリンズや、さては一万二千ないし五千マイル彼方の熱帯植民地の市街の一部分が。商館の建物――日本の低く軽い商店に比較すれば巨大な――は財力の脅威を語るごとくに見える。種々雑多の様式の住宅――インド式の平屋建(バンガロー)から、小塔(ターレット)や張出窓(ボーウインドー)を備えた英仏式の山荘風に至るまでの建物――は平凡な刈り込んだ潅木の庭園に囲繞せられ、白い道路は固く卓子のように平らで、四角く刈られた樹木でかぎられている。ほとんど英米に於ける伝統的なすべての物が此処に移植されてある・・・
将来、日本では、英国でドイツ語が学ばれているように、英語を学ぶことになるであろう。しかし、この英語の学修は、ある方面には徒労であったとしても、他の方面に於いては、決して徒労でなかった。英語の影響は、固有の日本語の形態変化をきたした。その結果、日本語は、より豊かなものとなり、より柔軟性を持つものとなり、近代科学の発見が生み出した新形式の思想を表現するのにいっそう強靱なものになったのである。この影響は永続するに相違ない。多数の英語が日本語に吸収されていくであろう――フランス語やドイツ語の単語も同様であろう。実際には、この吸収は智識階級の言葉づかいの変化の中にすでに顕著であって、これは開港場のナマリ言葉でも同様で、このナマリ言葉には商業用外国語が珍妙な形式変化をして交じり合っているのである。
さらには、日本語の文法的構造も影響を受けつつある。私は、最近ある宣教師が「東京の街中で腕白小僧どもが、旅順口の陥落を伝えて『旅順口ガ占領セラレタ』とパッシヴ・ヴォイス(受動態)で叫んでいたが、これも『神意』の致すところを示すものだ」と述べていたのには賛成しないものの、日本語はこの民族の天稟と同じく同化的で、新しい境遇のすべての要求に適応し得る能力を示す証拠だとは考えている。
おそらく日本は、二十世紀になれば、こんにちの外人教師というものを、よけいに懐かしく思い出すだろう。しかし、思い出すにしても、この国が、明治以前のむかしに、中国に対して感じていたような、ああいう古来の風習どおりに恩師を尊敬する念は、感ずることはまずあるまい。これはなぜかというと、中国の知識は、日本はこれを自発的に求めたものであるが、西洋の学問は、強制的に押し付けられたものだからである。キリスト教にしても、いずれ日本は日本流の宗派をもつだろうが、それにしても、むかし日本の青年を教導した中国の高僧を、こんにちでも長く記憶しているようには、アメリカやイギリスの宣教師のことを、長く記憶はしないだろう。また、われわれが日本に滞在したという形見の品を、七重の絹にていねいに包み、美しい白木の箱に納めて、長く保存しておくようなことは、まずしないだろう。なぜかというのに、われわれは、新しい美の教訓は日本に教えなかったのだし、日本人の感情に訴えるような物は、なにひとつ与えることをしなかったからである。
外国人輸出入業者の自信は、一八九五年七月に手も無く破られた。それはこの時、英国の一商館が日本の一会社を相手取り、同社が注文した商品の引取りを拒絶したとして日本の法廷に訴え、裁判には勝って約三万ドルを勝ち得たものの、突然、今までその力など予想もしなかった強力な同業組合(ギルド)と対決させられ、脅かされるハメにおちいったからである。敗訴した日本の商社は判決に対し上訴はしなかった。のみならず、全額はすぐにも支払いますよ、お求めなら、と表明した。一方、その会社の属しているギルドは、勝訴の原告側に通告して、和解を勧め、それがつまりは身のためですよ、と告げた。この英国商館は、このとき、自社が全く破産させられるほどの不買同盟(ボイコット)で脅かされている状況にあるのに気付いた――日本全国のあらゆる商工業中心地を網羅した不買同盟だった。和解は直ちに成立したが、この外国商館はかなりの損失を被った、そして居留地は青くなった。このようなやり方の不徳義を非難する声もかなり聞こえた。しかし、それは法律では如何ともし難いやり方であった。というのも、不買同盟は法律では満足に処理し得ないものなのである・・・
五月十五日、兵庫にて。清国から帰還した松島艦が「和楽園」のまえに碇泊している。この軍艦は、大きな勲功をあらわした軍艦だが、それにしては大きな軍艦ではない。けれども、さすがに波ひとつない青畳のような海面に、にゅっと浮かんでるこの鉄(くろがね)の城は、澄みわたった日の下で見ると、たしかに犯しがたい偉容をそなえている。この軍艦を縦覧させるという許しが出たので、市民はみな大喜びで、まるでお祭りにでも出かけるように晴着を着かざっている。私もその連中と同行することになった。港内にある船という船は、一艘のこらず、みなその見物人を乗せるために出払ったかと思われるくらい、それほどわれわれ一行が着いたときには、装甲艦のまわりには見物客を乗せた船が蟻のように集まり群がっていた。とてもそんな人数が同時に軍艦へ乗りこむなどということは、できるものではない。そこで何百人かずつが、交代に乗りこんでは降りることになって、そのあいだ、われわれはしばらく待っていなければならなかった。
今日はどこかの連隊が帰るのを見に行った。神戸駅から「楠公さん」(楠木正成の英霊を祀った大きな社)まで、彼らの通る往来の上に緑門が出来ていた。市民たちは、兵士たちに凱旋後初めての食事を奉仕するのを名誉として、そのために六千円もの金を寄附していたが、これまでにすでに、幾大隊かの兵士が同様に親切な歓迎を受けていた。
兵士たちが食事をした神社境内の休憩所は旗や花綱で飾られていた。兵士全員に贈りものがあって、菓子や紙巻タバコや、勇気を讃えた和歌などを染め抜いた手拭などである。神社の門の前には本当に立派な凱旋門が立てられ、前後両面には歓迎の辞句が金文字で記され、頂上には地球の上に翼を広げた鷹が登っていた。
私は最初、萬右衛門を連れて神社に遠からぬ停車場の前に待っていた。列車が着いて、番兵が見物人に歩廊を立ち去らせた。外の街路では、巡査らは群集を制し、一般の通行を止めた。
三味線をかかえて、七、八つの小さな男の子をつれた女が、私の家の前へ唄を歌いにやってきた。女は百姓のような身なりをして、首に浅黄色の手拭をまきつけていた。女はぶきりょうだった。うまれつき、きりょうがわるいうえに、むごたらしい疱瘡にかかったために、なおさら、ふた目と見られぬ顔になっていた。子どもは、刷りものにした流行唄の束を持っていた。・・・
そのうちに、近所の人たちが、私の家の前庭にあつまってきた。近所の人たちといっても、たいていは、若い子持のおかみさんや、背中に赤ん坊をおぶった子守りなどであったが、なかには、やはりおなじように、子どもをつれたお爺さんや婆さん――近所の隠居連も混じっていた。隣り町の町角にある休息所から、辻待ちの車屋などもやってきた。そんなわけで、やがて私の家の門のなかは、もう人のはいる余地がなくなってしまった。
女は玄関の石段のところに腰をおろして、しばらく、三味線の糸の調子を合わせていたが、やがて合の手のような曲を一曲弾きだした。すると、たちまち一種の魅惑が、聴きてのうえに落ちてきた。聴きては、みな、ヘーエといったような顔をして、微笑をもらしながら驚きの目をみはって、たがいに顔を見あわせた。
私の家の二階からは、この町の通りが、ずっと下(しも)の方の港のあたりまで、ひと目に見渡される。通りの両側には、小さな商人家がずらりと軒を並べているのだが、ついこの間から、私はこの町すじの方々の家から、コレラ患者が病院に運ばれて行くのを、ちょいちょい目にする。今朝も、私はそれを見た。今朝のは、向こう側の瀬戸物屋の主人だった。瀬戸物屋の主人は、家人が涙を流して、おいおい言って泣くのもかまわず、むりむたいに連れて行かれた。衛生法によると、コレラ患者を自宅で療養させることは禁じられているのであるが、それでも町民は、たとえ罰金や体刑をくらっても、何とかして患者を隠蔽しようと苦労する。なぜそんなことをするかというと、避病院は患者で満員のうえに、あすこは病人の扱いが乱暴で、しかも入院すると、患者は身うちのものからぜんぜん隔離されてしまうからである。ところが、警官諸君は、なかなかどうして、そんな手はめったに食わない。直ぐに無届けの患者をさがしだして、担架と人夫をつれてやってくる。見ていると、ずいぶん残酷のようだが、しかし、衛生法なんてものは、これはよろしく残酷なものでなければいけない。瀬戸物屋のおかみさんは、泣き泣き、担架のあとを追って行ったが、けっきょく、警官がなだめて、とうとうしまいに、主人のいなくなった寂しい店へ追い返されてきた。店は、いま、大戸がおろしてあるが、おそらく、今のあるじの手で、二度とこの店をあけられることはあるまい。
One autumn evening Hamaguchi Gohei was looking down from the balcony of his house at some
preparations for a merry-making in the village below. There had been a very fine rice-crop, and
the peasants were going to celebrate their harvest by a dance in the court of the ujigami.
The old man could see the festival banners (nobori) fluttering above the roofs of the solitary
street, the strings of paper lanterns festooned between bamboo poles, the decorations of the
shrine, and the brightly colored gathering of the young people.
He had nobody with him that evening but his little grandson, a lad of ten; the rest of the
household having gone early to the village. He would have accompanied them had he not been
feeling less strong than usual.
宿に泊まり近辺の神社仏閣を訪ね歩き、ハーンは四月二十五日その感動をシンシナティの老友に宛ててこう伝えている。
One autumn evening Hamaguchi Gohei was looking down from the balcony of his house at some preparations for a merry-making in the village below. There had been a very fine rice-crop, and the peasants were going to celebrate their harvest by a dance in the court of the ujigami. The old man could see the festival banners (nobori) fluttering above the roofs of the solitary street, the strings of paper lanterns festooned between bamboo poles, the decorations of the shrine, and the brightly colored gathering of the young people. He had nobody with him that evening but his little grandson, a lad of ten; the rest of the household having gone early to the village. He would have accompanied them had he not been feeling less strong than usual.
The day had been oppressive; and in spite of a rising breeze there was still in the air that sort of heavy heat which, according to the experience of the Japanese peasant, at certain seasons precedes an earthquake. And presently an earthquake came. It was not strong enough to frighten anybody; but Hamaguchi, who had felt hundreds of shocks in his time, thought it was queer ? a long, slow, spongy motion. Probably it was but the after-tremor of some immense seismic action very far away. The house crackled and rocked gently several times; then all became still again.
明治 29(1896)年 6月15日 午後8 時半、宮城、岩手、青森三県を襲った「三陸大津波」。死者二万七千百二十二人(27,122)人、流失・破壊家屋 1万0390戸、観測史上最大の津波被害。当時の新聞は、連日のように津波被害の惨状を報じた。当時の新聞報道の解説の中に、42年前の1854年 (安政元年、嘉永七年)11月5 日( 陰暦) に紀州をはじめ太平洋岸一帯を襲った「安政の大津波」の際に、『稲むらの火』に語られているような手段で広川町ー当時の広村ーの村民を救った濱口儀兵衛(ハーンの『生神』では「濱口五兵衛」と名前を変えている)の史実が報じられた。
明治 29(1896)年 6.21 日曜日。大阪毎日新聞二面「海嘯の歴史」で浜口儀兵衛の逸話が掲載された。
平成 5(1993)年 8月末、和歌山市で、二百人を越す世界のツナミ学者が集まって「国際ツナミ学会」が開かれた。研究発表論文集の第一ページに、ラフカディオ・ハ-ンの作品として、『稲むらの火』(英文)を掲載。原文は『生神』。
『稲むらの火』
「これは、たゞ事でない。」
とつぶやきながら、五兵衛は家から出て來た。今の地震は、別に烈しいといふ程のものではなかつた。しかし、長いゆつたりとしたゆれ方と、うなるやうな地鳴りとは、老いた五兵衛に、今まで経験したことのない無氣味なものであつた。
五兵衛は、自分の家の庭から、心配げに下の村を見下した。村では、豐年を祝ふよひ祭の支度に心を取られて、さつきの地震には一向氣がつかないもののやうである。
村から海へ移した五兵衛の目は、忽ちそこに吸附けられてしまつた。風とは反對に波が沖へ沖へと動いて、見る見る海岸には、廣い砂原や黒い岩底が現れて來た。
「大變だ。津波がやつて来るに違ひない。」と、五兵衛は思つた。此のまゝにしておいたら、四百の命が、村もろ共一のみにやられてしまふ。もう一刻も猶豫は出來ない。
「よし。」
と叫んで、家にかけ込んだ五兵衛は、大きな松明を持つて飛び出して來た。そこには、取入れるばかりになつてゐるたくさんの稲束が積んである。
「もつたいないが、これで村中の命が救へるのだ。」
と、五兵衛は、いきなり其の稲むらの一つに火を移した。風にあふられて、火の手がぱつと上つた。一つ又一つ、五兵衛は夢中で走つた。かうして、自分の田のすべての稲むらに火を付けてしまふと、松明を捨てた。まるで失神したやうに、彼はそこに突立つたまゝ、沖の方を眺めてゐた。
日はすでに没して、あたりがだんだん薄暗くなつて來た。稲むらの火は天をこがした。山寺では、此の火を見て早鐘をつき出した。
「火事だ。莊屋さんの家だ。」
と、村の若い者は、急いで山手へかけ出した。續いて、老人も、女も、子供も、若者の後を追ふやうにかけ出した。
高臺から見下してゐる五兵衛の目には、それが蟻の歩みのやうに、もどかしく思はれた。やつと二十人程の若者がかけ上つて來た。彼等は、すぐ火を消しにかゝらうとする。五兵衛は大聲で言つた。
「うつちやつておけ。──大變だ。村中の人に來てもらふんだ。」
村中の人は、追々集まつて来た。五兵衛は、後から後から上つて來る老幼男女を一人々々數へた。集まつて來た人々は、もえてゐる稲むらと五兵衛の顔とを代る代る見くらべた。
其の時、五兵衛は力一ぱいの聲で叫んだ。
「見ろ。やつて來たぞ。」
たそがれの薄明かりをすかして、五兵衛の指さす方を一同は見た。遠く海の端に、細い、暗い、一筋の線が見えた。其の線は見る見る太くなつた。廣くなつた。非常な速さで押寄せて來た。
「津波だ。」
と、誰かが叫んだ。海水が、絶壁のやうに目の前に迫つたと思ふと、山がのしかゝつて來たやうな重さと、百雷の一時に落ちたやうなとゞろきとを以て、陸にぶつかつた。人々は、我を忘れて後へ飛びのいた。雲のやうに山手へ突進して來た水煙の外は、一時何物も見えなかつた。
人々は、自分等の村の上を荒狂つて通る白い恐しい海を見た。二度三度、村の上を海は進み又退いた。
高臺では、しばらく何の話し聲もなかつた。一同は、波にゑぐり取られてあとかたもなくなつた村を、たゞあきれて見下してゐた。
稲むらの火は、風にあふられて又もえ上り、夕やみに包まれたあたりを明かるくした。始めて我にかへつた村人は、此の火によつて救はれたのだと氣がつくと、無言のまゝ五兵衛の前にひざまづいてしまつた。
尋常科用 小學國語讀本 巻十の第十 文部省
ラフカディオ・ハーン(Lafcadio Hearn) の日本での主な著作一覧 (『神戸クロニクル』論説は除く。和訳名は、主として恒文社刊「全訳 小泉八雲作品集・全12巻。1964年~1967年出版」による。)
○明治27(1894)年 9.29.『日本瞥見記』(『知られぬ日本の面影』)
Glimpses of Unfamiliar Japan (ホウトン・ミフリン 社)
「極東第一日」(My First Day in the Orient)
「弘法大師の書」(The Writing of Kobodaishi)
「地蔵」(Jizo)「江ノ島行脚」(A Pilgrimage to Enoshima)
「盆市で」(At the Market of the Dead)
「盆おどり」(Bon-Odori)
「神々の国の首都」(The Chief City of the Province of the Gods)
「杵築―日本最古の神社」(Kitsuki: The Most Ancient Shrine of Japan)
「潜戸(くけど)―子供の亡霊岩屋」(In the Cave of the Children’s Ghosts)
「美保の関」(At Mionoseki)
「杵築雑記」(Notes on Kitsuki)
「日ノ御碕(みさき)」(At Hinomisaki)
「心中」(Shinju)
「八重垣神社」(Yaegaki-Jinja)
「キツネ」(Kitsune)
「日本の庭」(In a Japanese Garden)
「家庭の祭壇」(The Household Shrine)
「女の髪」(Of Women’s Hair)
「英語教師の日記から」(From the Diary of an English Teacher)
「二つの珍しい祭日」(Two Strange Festivals)
「日本海に沿うて」(By the Japanese Sea)
「舞妓」(Of a Dancing-Girl)
「伯耆から隠岐へ」(From Hoki to Oki)
「魂について」(Of Souls)
「幽霊と化けもの」(Of Ghosts and Goblins)
「日本人の微笑」(The Japanese Smile)
「さようなら」(Sayonara!)
○明治28(1895)年 3.9 『東の国から』
Out of the East (ホウトン・ミフリン社)
「夏の日の夢」(The Dream of a Summer Day)
「九州の学生とともに」(With Kyushu Students)
「博多で」(At Hakata)
「永遠の女性」(Of the Eternal Feminine)
「生と死の断片」(Bits of Life and Death)
「石仏」(The Stone Buddha)
「柔術」(Jiujutsu)
「赤い婚礼」(The Red Bridal)
「願望成就」(A Wish Fulfilled)
「横浜で」(In Yokohama)
「勇子―ひとつの追憶」(Yuko: A Reminiscence)
○明治29(1896)年 3.14. 『心』(Kokoro) (ホウトン・ミフリン 社)
「停車場で」(At a Railway Station)
「日本文化の真髄」(The Genius of Japanese Civilization)
「門つけ」(A Street Singer)
「旅日記から」(From a Traveling Diary)
「あみだ寺の比丘尼(びくに)」(The Nun of the Temple of Amida)
「戦後」(After the War)
「ハル」(Haru)
「趨勢一瞥」(A Glimpse of Tendencies)
「因果応報の力」(By Force of Karma)
「ある保守主義者」(A Conservative)
「神々の終焉」 (In the Twilight of the Gods)
「前世の観念」(The Idea of Preexistence)
「コレラ流行期に」(In Cholera-Time)
「祖先崇拝の思想」(Some Thoughts about Ancestor-Worship)
「きみ子」(Kimiko)
「三つの俗謡」俊徳丸、小栗判官、八百屋お七、の英訳(Three Popular Ballads)
○明治30(1897)年 9.25. 『仏の畑の落穂』(『仏陀の国の落穂』)
Gleanings in Buddha-Fields (ホウトン・ミフリン社)
「生神」(A Living God)
「街上から」(Out of the Street)
「京都紀行」(Notes of a Trip to Kyoto)
「塵」(Dust)
「日本美術の顔について」(About Faces in Japanese Art)
「人形の墓」(Ningyo-no-Haka)
「大阪」(In Osaka)
「日本の俗謡における仏教引喩」(Buddhist Allusions in Japanese Folk-Song)
「涅槃」(Nirvana)
「勝五郎再生記」(The Rebirth of Katsugoro)
「環中記」(Within the Circle)
○明治31(1898)年12. 8.『異国風物と回想』
Exotics and Retrospectives(リトル・ブラウン 社)
《異国風物》(Exotics)
「富士の山」(Fuji-no-Yama)
「虫の音楽家」(Insect-Musicians)
「禅の公案」(A Question in the Zen Texts)
「死者の文学」(The Literature of the Dead)
「カエル」(Frogs)
「月がほしい」(Of Moon-Desire)
《回想》(Retrospectives)
「第一印象」(First Impressions)
「美は記憶なり」(Beauty is Memory)
「美のなかの悲哀」(Sadness in Beauty)
「青春のかおり」(Parfum de Jeunesse)
「青の心理学」(Azure Psychology)
「小夜曲」(A Serenade)
「赤い夕日」(A Red Sunset)
「身震い」(Frisson)
「薄明の認識」(Vespertina Cognitio)
「永遠の憑きもの」(The Eternal Haunter)
○明治32(1899)年 9.26.『霊の日本』
In Ghostly Japan(リトル・ブラウン社)
「断片」(Fragment)
「振袖」(Furisode)
「香」(Incense)
「占いの話」(A Story of Divination)
「蚕」(Silkworms)
「恋の因果」(A Passional Karma)
「仏陀の足跡」(Footprints of the Buddha)
「犬の遠ぼえ」(Ululation)
「小さな詩」(Bits of Poetry)
「日本の仏教俚諺」(Japanese Buddhist Proverbs)
「暗示」(Suggestion)
「因果ばなし」(Ingwa-banashi)
「天狗譚」(Story of a Tengu)
「焼津」(At Yaidzu)
○明治33(1900)年 7.24. 『明暗』(『影』)
Shadowings (リトル・ブラウン 社)
《珍籍叢話》(Stories from Strange Books)
「和解」(The Reconciliation)
「普賢菩薩のはなし」(A Legend of Fugen-Bosatsu)
「衝立の乙女」(The Screen-Maiden)
「死骸に乗る」(The Corpse-Rider)
「弁天の感応」(The Sympathy of Benten)
「鮫人の恩返し」(The Gratitude of the Samebito)
《日本研究》(Japanese Studies:)
「蝉」(Semi)
「日本女性の名」(Japanese Female Names)
「日本の古い歌謡」(Old Japanese Songs)
《夢想》(Fantasies:)
「夜光虫」(Noctiluca)
「人ごみの神秘」(A Mystery of Crowds)
「ゴシックの恐怖」(Gothic Horror)
「飛行」(Levitation)
「夢魔の感触」(Nightmare-Touch)
「夢の本から」(Readings from a Dream-Book)
「一対の目のなかに」(In a Pair of Eyes)
○明治34(1901)年10. 2. 『日本雑記』
A Japanese Miscellany (リトル・ブラウン社)
《奇談》(Strange Stories)
「守られた約束」(Of a Promise Kept)
「破られた約束」(Of a Promise Broken)
「閻魔の庁で」(Before the Supreme Court)
「果心居士」(The Story of Kwashin Koji)
「梅津忠兵衛」(The Story of Umetsu Chubei)
「興義和尚のはなし」(The Story of Kogi the Priest)
《民間伝承 落穂集》(Folk-Lore Gleanings:)
「トンボ」(Dragon-flies)
「動・植物の仏教的名称」(Buddhist Names of Plants and Animals)
「日本のわらべ歌」(Songs of Japanese Children)
《あちこち艸》(Studies Here and There:)
「橋の上」(On a Bridge) 「お大の場合」(The Case of O-Dai)
「海のほとり」(Beside the Sea)
「漂流」(Drifting)
「乙吉のだるま」(Otokichi’s Daruma)
「日本の病院で」(In a Japanese Hospital)
○明治35(1902)年10.22.『骨董』
Kotto (Being Japanese Curios, with Sundry Cobwebs) (マクミラン 社)
《古い物語》(Old Stories)
「幽霊滝の伝説」(The Legend of Yurei-Daki)
「茶わんの中」(In a Cup of Tea)
「常識」(Common Sense)
「生霊」(Ikiryo)
「死霊」(Shiryo)
「おかめのはなし」(The Story of O-Kame)
「蠅のはなし」(Story of a Fly)
「雉子のはなし」(Story of a Pheasant)
「忠五郎のはなし」(The Story of Chugoro)
「ある女の日記」(A Woman’s Diary)
「平家蟹」(Heike-Gani)
「蛍」(Fireflies)
「露のひとしずく」(A Drop of Dew)
「餓鬼」(Gaki)
「いつもあること」(A Matter of Custom)
「夢想」(Revery)
「病のもと」(Pathological)
「真夜中に」(In the Dead of the Night)
「草ひばり」(Kusa-Hibari)
「夢を食うもの」(The Eater of Dreams)
○明治37(1904)年 4. 2. 『怪談』
Kwaidan (Stories and Studies of Strange Things) (ホウトン・ミフリン 社)
「耳なし芳一のはなし」(The Story of Mimi-Nashi-Hoichi)
「おしどり」(Oshidori)
「お貞のはなし」(The Story of O-Tei)
「うばざくら」(Ubazakura)
「かけひき」(Diplomacy)
「鏡と鐘」(Of a Mirror and a Bell)
「食人鬼」(Jikininki)
「むじな」(Mujina)
「ろくろ首」(Rokuro-Kubi)
「葬られた秘密」(A Dead Secret)
「雪おんな」(Yuki-Onna)
「青柳ものがたり」(The Story of Aoyagi)
「十六ざくら」(Jiu-Roku-Zakura)
「安芸之介の夢」(The Dream of Akinosuke)
「力ばか」(Riki-Baka)
「日まわり」(Hi-Mawari)
「蓬莱」(Horai)
《虫の研究》(Insect-Studies)
「蝶」(Butterflies)
「蚊」(Mosquitoes)
「蟻」(Ants)
○ 明治37(1904)年9.『日本―一つの試論』
Japan; An Attempt at Interpretation(マクミラン社)
「わかりにくさ」(Difficulties)
「珍しさと魅力」(Strangeness and Charm)
「上代の祭」(The Ancient Cult)
「家庭の宗教」(The Religion of the Home)
「日本の家族」(The Japanese Family)
「地域社会の祭」(The Communal Cult)
「神道の発達」(Developments of Shinto)
「礼拝と清め」(Worship and Purification)
「死者の支配」(The Rule of the Dead)
「仏教の渡来」(The Introduction of Buddhism)
「大乗仏教」(The Higher Buddhism)
「社会組織」(The Social Organization)
「武力の興隆」(The Rise of the Military Power)
「忠義の宗教」(The Religion of Loyalty)
「キリシタン禍」(The Jesuit Peril)
「封建制の完成」(Feudal Integration)
「神道の復活」(The Shinto Revival)
「前代の遺物」(Survivals)
「現代の抑圧」(Modern Restraints)
「官制教育」(Official Education)
「産業の危機」(Industrial Danger)
「反省」(Reflections)
○明治38(1905)年10.18.『天の川綺譚』
The Romance of the Milky Way, and Other Studies and Stories (ホウトン・ミフリン社)
「天の川綺譚」(The Romance of the Milky Way)
「化けものの歌」(Goblin Poetry)
「『究極の問題』」(“Ultimate Questions”)
「鏡の乙女」(The Mirror Maiden)
「伊藤則資のはなし」(The Story of Ito Norisuke)
「小説よりも奇なり」(Stranger than Fiction)
「日本だより」(A Letter from Japan)
「神戸のハーン」作品から
「お断り」 作品の題名と本文の和訳は主として恒文社刊「ラフカディオ・ハーン著作集・全15巻。生誕130年記念出版」「全訳 小泉八雲作品集・全12巻。1964年~1967年出版」(平井呈一訳)と、第一書房刊「小泉八雲全集・全18巻。大正15年~昭和3年出版」(戸澤正保、石川林四郎訳)に拠っているが、監修者の責任に於いて、いずれからも、事実の誤認は訂正し、人権上の配慮などにより語句を改め、新仮名遣いにするほか、表現に変更を加えている。また「注」とあるのは監修者による補足・説明である。
なお、英文は、
「The Writings of Lafcadio Hearn in Sixteen Volumes, Houghton Mifflin Company. 1922」から写している。
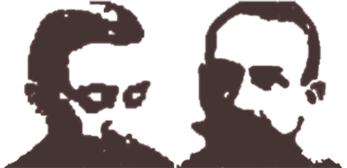
二人は同時代に生き、ともに神戸で暮らしたが面識はない。
しかしモラエスは、生前のハーンにあこがれを持ち、死後は追慕という形で心の片隅にハーンがいた。
モラエスは、1854年にポルトガルに生まれた。一方のハーン(小泉八雲)は、1850年のギリシャ生まれ。モラエスは1889年の八月に初来日し、ハーンが日本にその最初の一歩を印したのは1890年四月四日で、ほぼ同時期である。日本で生活した数年は、ハーンの十四年に対して、モラエスは三十年以上と長い。ただし、ハーンが日本を愛し、日本人を妻にし、家庭を築き、旧制松江中学や東京帝国大学で教鞭をとるなど、多くの知識階級との交流があったのに対して、モラエスは、領事という立場にはあったが、市井にひっそりと暮らしたという感が深い。また、同時代を生きたが、二人に面識はない。あくまでもモラエスにとって、ハーンは文明批評と異国情緒にあふれた作品を書く、範とすべき人物だったのである。
モラエスの著作を読むと、あちらこちらにハーンの名を見ることができる。
たとえば、神戸時代の著作「日本通信」Ⅱの第十九章、1904年十月二十六日の日付があるが、その記事の中でモラエスは、「ラフカディオ・ハーンの死」と題して、<<小泉八雲は、明らかに青年時代の難渋生活の無理がたたったのだろう、弱い肉体組織はかなり以前から病気にかかっていたので、雅趣がある庭に囲まれた東京にひきこもっていた。
(モラエス会 会誌「モラエス 第七号」より)
執筆者:「モラエス」編集委員会 モラエス会常任幹事 福原 健生 他
モラエスは、1854年にポルトガルに生まれた。一方のハーン(小泉八雲)は、1850年のギリシャ生まれ。モラエスは1889年の八月に初来日し、ハーンが日本にその最初の一歩を印したのは1890年四月四日で、ほぼ同時期である。日本で生活した数年は、ハーンの十四年に対して、モラエスは三十年以上と長い。ただし、ハーンが日本を愛し、日本人を妻にし、家庭を築き、旧制松江中学や東京帝国大学で教鞭をとるなど、多くの知識階級との交流があったのに対して、モラエスは、領事という立場にはあったが、市井にひっそりと暮らしたという感が深い。また、同時代を生きたが、二人に面識はない。あくまでもモラエスにとって、ハーンは文明批評と異国情緒にあふれた作品を書く、範とすべき人物だったのである。
モラエスの著作を読むと、あちらこちらにハーンの名を見ることができる。
たとえば、神戸時代の著作「日本通信」Ⅱの第十九章、1904年十月二十六日の日付があるが、その記事の中でモラエスは、「ラフカディオ・ハーンの死」と題して、小泉八雲は、明らかに青年時代の難渋生活の無理がたたったのだろう、弱い肉体組織はかなり以前から病気にかかっていたので、雅趣がある庭に囲まれた東京にひきこもっていた。交際嫌いで神経質で偏屈な気質で、最新では、東京に住む多くの外国人とのどんな交際も絶対に拒んでいた。九月二十六日の朝、少し庭園を散歩した後、突然、死んだ。埋葬は仏式で行われた。と、ハーンの晩年とその最期について述べた後、ハーンの業績についても言及し、小泉八雲は、入籍した新しい祖国を崇拝していたし、その著述でも日本を崇拝し続けている物が多い。すばらしい叡智、随想的で微細な芸術家気質、美しい形式で日本に関する著書を書き、ひどく日本的な随想を出版したが、そのすべてがすばらしい文学の宝玉であった(「定本モラエス全集」)・花野富蔵訳)と賛辞を贈っている。
また、晩年の「おヨネとコハル」の中でも、ハーンの著作について、それらはすべて、形式、優婉な言葉づかい、精妙な観察、鋭い感覚という点ですばらしいものであり、彼だけがもつある種のえもいわれぬ情緒性によって英国の、そして間違いなく世界文学の中で第一級の現代散文家のひとりと今日、考えられる権利―長いあいだ認められず、やっと得たのではあるが――を彼に与えている。(「おヨネとコハル」)・岡村多希子訳)と述べている。モラエスは生前のハーンに憧れを持ち、また死後は、追慕という形で常に常識の片隅にあったように思われる。
モラエスはハーンの模写であり、模倣であるという意見もある。たしかにその作品の中には、ハーンの影響も少なくない。対象への接近の仕方やものの見方、捉え方にハーンに通じるものが多いの確かである。日本の近代をどう見るかといった時に、モラエスはハーンと同様に、より肯定的に見ようとしている。
たとえば、彼が最後の著作としてまとめた「日本精神」などは、パーシヴァル・ローエルの「極東の魂」に構成や取り上げる項目が酷似しているが、日本人の国民性や日本文化についての評価は、否定的なローエルとはまったく正反対の結論に至る。
モラエスはけっして独創的な日本研究をしたとは言えないし、優秀なジャパノロジストではなかったかもしれない。しかし、彼は、彼自身の生き方を通して、異文化理解というものを体現した。それはハーンとはまた違った意味で、深く、重いものであった。その体験は、私小説的な随筆として異国に生きるエトランゼの孤独感と哀しみが的確な筆致で描かれる「徳島の盆踊り」や「おヨネとコハル」となって結実する。
ヴェンセスラウ・ジョゼ・デ・ソーザ・モラエスと小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)。この二つの名前にはそれぞれの生涯が象徴されているように思う。ギリシャに生まれ、自らのアイデンティティーを探し求め、遠く東洋の島国でその生涯を終わったハーンは、日本に帰化し、小泉八雲を名乗った。それに対して、大航海時代の覇者ポルトガルのリスボンに生まれ育ったモラエスは、終生モラエスのまま、誇り高きルシタニアの民としてその後半生を日本に送ったのである。(モラエス会)※ルシタニア・・・ポルトガルの古名、雅称。

マカオで海軍高官として、さまざまな重責を誠実にこなしたモラエスは、在任中公務で度々日本を訪れ、長期滞在を繰り返していた。そして日本の自然、人情、風習、めざましい発展ぶりなどに深く魅了されるようになっていた。
そうした考察や観察を「極東遊記」「大日本」などの著作に発表し、ポルトガル本国でも文筆家、日本通として知られるようになっていた。
1889年、ポルトガルの砲艦「リオ・リマ」の副官として長崎に上陸して以来、モラエスにとって日本は憧れの国となっていた。これまで漂泊の旅を続けてきたアフリカ、マカオなどの原色に彩られた熱帯性の野生美とは違って、そこには優しい光りと色をたたえた自然があり、心和ませる風習と生活にあふれ、愛くるしい女性たちがいた。しかし、彼に日本移住を決意させたのは、1897年のマカオの不当な人事であった。
(徳島県立文学館 特別展「モラエスとハーン展」図録より)
執筆者:林 啓介
マカオで海軍高官として、さまざまな重責を誠実にこなしたモラエスは、在任中公務で度々日本を訪れ、長期滞在を繰り返していた。そして日本の自然、人情、風習、めざましい発展ぶりなどに深く魅了されるようになっていた。
そうした考察や観察を「極東遊記」「大日本」などの著作に 発表し、ポルトガル本国でも文筆家、日本通として知られるようになっていた。
1889年、ポルトガルの砲艦「リオ・リマ」の副官として長崎に上陸して以来、モラエスにとって日本は憧れの国となっていた。これまで漂泊の旅を続けてきたアフリカ、マカオなどの原色に彩られた熱帯性の野生美とは違って、そこには優しい光りと色をたたえた自然があり、心和ませる風習と生活にあふれ、愛くるしい女性たちがいた。しかし、彼に日本移住を決意させたのは、1897年のマカオの不当な人事であった。
モラエスが希望した神戸領事館の開設は、難航を重ねた末、ついに1899年に実現した。やがて彼は公式にポルトガル国神戸領事に任命され、ポルトガルと日本の通商の拡大や日本在住のポルトガル人の保護など各方面にすぐれた外交手腕を発揮するようになった。
そして翌1900年(明治三十三年)年十一月、彼は徳島出身の福本ヨネと結ばれた。モラエス四十六才、おヨネは二十五才であった。
おヨネはどこか愁いを宿したかげりのようなものが美しい目鼻立ちに漂う女性だった。
控え目だが優しく細やかな心遣いでモラエスに尽くした。モラエスは彼女との結婚で初めて満ち足りた心の安らぎを得たといわれる。そしてますます職務や文筆活動に精力的な情熱を注ぐようになっていく。
1902年四月からは、ポルトガルの商都ポルトで発行されていた「ポルト商報」の第一面に、モラエスは「日本通信」を連載し始めた。内容は日本の政治、経済、軍事、社会芸術文化などあらゆる分野に及び、天皇を中心に発展を遂げる日本の姿を通して、混乱し衰退してゆく祖国ポルトガルの覚醒(かくせい)を促そうとした趣きがある。「日本通信」は1913年まで続き、全六巻を数える膨大な著作となるのである。
また彼は公的あるいは私的な会合にも熱心に参加し、巡洋艦「サン・ガブリエル」など母国の船が神戸を訪れると喜び勇んで最大限の歓待をした。
また関西各地への旅行の見聞や日本の文献などをもとに「日本夜話」、「茶の湯」など日本の自然、風俗、芸術などを賛える日本紹介の著作も次々に発表した。
ところが、1912(明治45年)年に、モラエスにとって耐え難いできごとが相次いで起きた。尊敬する明治天皇の崩御、最愛の女性おヨネの死、そしてポルトガル本国の革命。モラエスを取り巻く風景が一変してしまったのである。彼の憂愁は極度につのった。
心機一転をはかるため住居を山本通から神納町に移したり、新しくやとった出雲出身の永原デンを半年ほど同棲もした。
しかし、結局モラエスは無常感を払拭することができなかったのであろうか、翌1913年、ポルトガル共和国大統領あてに公職返上を願い出たのである。
—————–ポルトガル国海軍中佐ヴェンセスラウ・デ・モラエスは、きわめて極力な私的な理由から、一切の公的な理由から、一切の公的な地位とも、はたまたポルトガル人として国籍とも両立しない立場に身を置く所存であります。領事職の辞任を直ちにお認めいただきますよう、閣下にお願い申し上げる次第であります——————-
本国政府は突然の申し入れに驚いたものの、辞表を受理した。
鴨長明の「方丈記」や吉田兼好の「徒然草」を愛読していたモラエスは、神戸を離れて隠棲しようと考えるようになった。五十九才日本流にいえば還暦を迎えていたのである。
加納町にあったモラエスの自宅
右側の和服姿がモラエス
当初モラエスは、隠棲地として先にデンを帰してあった出雲を考えていたようであるが、彼が金を出して造ったおヨネの墓ができて徳島を訪れてからは徳島移住に心が傾いていった。「愛する人の墓のある徳島へ行こう」と決心したのである。徳島にはおヨネの姉ユキやその娘のコハルもいる。それに気候も温和で暮らしやすい。何よりも昔ながらの日本的な風習や人情が残っていて、緑濃い自然も豊かである。文筆活動に専念できる土地に思えたのであろう。彼は徳島行きの片道切符を買った。

ヴァスコダ・ガマのインド航路発見400年際の記念事業のひとつとして、リスボンの地理学協会が、東洋に関する図書を出版するにつき極東遊記の著者で、日本通のモラエスに日本についての著述の依頼があって執筆した。
この作品はポルトガルで好評を博した。
「日本通信Ⅰ」(日露開戦前)、1904年、ポルトで出版する。
ポルトガル北部の都市ポルトの経済新聞「ポルト商報」の編集長ベント・カルケジャが、通商官報にのったモラエスの領事館年報の記事に感銘し、懇願して無報酬の通信員になってもらい、書いてもらった記事を1902年四月八日から1904年二月十八日までの間に同紙に掲載したもの。
(モラエス会 会誌「モラエス 第七号」より)
執筆者:「モラエス」編集委員会 モラエス会常任幹事 福原 健生 他
ヴァスコダ・ガマのインド航路発見400年際の記念事業のひとつとして、リスボンの地理学協会が、東洋に関する図書を出版するにつき極東遊記の著者で、日本通のモラエスに日本についての著述の依頼があって執筆した。
この作品はポルトガルで好評を博した。
「日本通信Ⅰ」(日露開戦前)、1904年、ポルトで出版する。
ポルトガル北部の都市ポルトの経済新聞「ポルト商報」の編集長ベント・カルケジャが、通商官報にのったモラエスの領事館年報の記事に感銘し、懇願して無報酬の通信員になってもらい、書いてもらった記事を1902年四月八日から1904年二月十八日までの間に同紙に掲載したもの。
「茶の湯」1905年(明治三十八年)、モラエスが神戸で自費出版する。
「日本通信Ⅱ」(日露開戦中)、1905年、ポルトで出版する。
1904年三月二日から翌年の三月二十三日までのポルト商報に連載した記事三十編百十二項目を掲げる。
「中国・日本風物誌」1906年にリスボンで初版を、1938年に再版を刊行。
ブラジルやポルトガルの雑誌などで発表した随想を集めたもの。
「日本通信Ⅲ」(日本生活)1907年、ポルトで出版する。
前巻同様に1905年四月十四日から翌六年十二月二十五日までの間、ポルト商報に連載した記事をまとめ、モラエス自身が序文を認めたもの。
「徳島の盆踊」1916年にポルトで初版・1929年に再版を発行する。
モラエスが徳島に来住して執筆した「日本随想記」
「日本通信Ⅳ」1928年、リスボンで出版する。
前巻同様に1907年一月十六日から1908年十二月十五日までの間、ポルト商報に連載した記事をまとめる。ラフカディオ・ハーンとその著書についても触れている。
「日本夜話」1926年、リスボンで出版する。
これは前作の「おヨネとコハル」が好評を得たことで再版権を懇願していたリスボンのポルトガル・ブラジル社に対して、神戸時代に雑誌「セロンイス」に発表した短篇をまとめることで出版権を与えて、1926年に刊行したもの。
「日本精神」1926年、リスボンで出版する。
この作品は七十歳を過ぎたモラエスが、病魔にさいなまれ、ままならぬ体にむち打って大正十四年(1925年)9月に書きあげた最後の著作。親友モレイラ・デ・サを介して、リスボンのポルトガル・ブラジル社から刊行されたのは翌1926年の十一月であった。作品目次の初章を、最初の考え、そして、言語、宗教、歴史、家族、部族、国家、愛、死、芸術と文学、これまでのまとめ、と続き、日本精神はどこまで行くのか?を終章とし、日本教育、を補遺とする。
※クリックすると詳細が見れます










『バレット文庫』版四十一編は、その所在がわかりながら、入手できずにいて、ハーン研究者の間では、ずっと〃幻の論説集〃とされてきた。神戸松蔭女子学院大学が松江の「八雲会」の希望を受け、米国の提携大学を経て、ヴァージニア大学保存の『バレット文庫』がマイクロフィルム化されるを待って、七巻の提供を受け、英文、和訳合わせて研究叢書として平成四(1992)年出版。
Lafcadio Hearn Collection (#6101), Clifton Waller Barrett Library, Manuscripts Division, Special Collections Department, University of Virginia Library.
監修者の言葉
ラフカディオ・ハーンは、日本で暮らした十四年間に「怪談」「骨董」「心」はじめ伝承、民話からの再話文学など多くの作品を著し、日本と日本人の心を世界に紹介したのち、東京で没した。
米国での青年時代、敏腕の新聞記者として名を上げたハーンは、四十歳で来日して、松江、熊本では英語教師のかたわら、民俗学的著作も出版、そののち神戸を経て東京大学に移り、英文学を講じて日本英語学の草分けともなった。
ハーンが一家で神戸へ移住して来たのは日清戦争最中の明治二十七年暮れ。ジャーナリストに戻ったハーンは、英字紙「神戸クロニクル」新聞(注・1)を舞台に戦争評論などに健筆を振るい、神戸では日本の他都市では見られない特別な活動を続けた。市民生活の面でも、在住二年間の神戸は、ハーンが帰化して日本人の「小泉八雲」に生まれ変わる(注・2)という特別の地であった。
ハーンが「神戸クロニクル」紙で執筆した論説記事のうち、紙面掲載後、ほぼ百年を経てようやく日の目を見た『バレット文庫』版収録の「神戸クロニクル論説集」(注・3)を中心に、神戸でのジャーナリスト・ハーンの全容を描き出そうとしたのがこの番組である。
明治 28(1895)年 7月 神戸市山手通六丁目二六番地に転居。
明治 28(1895)年 7月 日本国籍を取る決心をする
明治 28(1895)年 8月25日「妻セツの婿養子となって日本人となろうとする手続き」で戸籍上の相談をする。松江の知人、親戚へ。
明治 28(1895)年 8月27日 小泉セツが分家をする
明治 28(1895)年 8月31日 ヘンドリック宛て、帰化の許可を待つと。
明治 28(1895)年 9月17日 一雄を小泉家へ先に入籍するようにとの助言あり。
明治 28(1895)年 9月 入籍による姓名変更の大臣許可を待つ。と手紙
明治 28(1895)年 11月 上旬 帰化願書は兵庫県知事・周布公平あて。三回提出
明治 28(1895)年 12月15日 西田千太郎へ「私は小泉八雲になる積もりです」
明治 29(1896)年 1月15日 46歳、小泉八雲の入夫許可
明治 29(1896)年 2月10日 入籍
明治 29(1896)年 4月15日 外山教授から「小泉八雲様」と宛名を書かれて私は奇妙な感じがしました。
明治 29(1896)年 6月15日 午後8 時半、宮城、岩手、青森三県を襲った「三陸大津波」。死者二万七千百二十二人(27,122)人、流失・破壊家屋 1万0390戸、観測史上最大の津波被害。当時の新聞は、連日のように津波被害の惨状を報じた。当時の新聞報道の解説の中に、42年前の1854年 (安政元年、嘉永七年)11月5 日( 陰暦) に紀州をはじめ太平洋岸一帯を襲った「安政の大津波」の際に、『稲むらの火』に語られているような手段で広川町ー当時の広村ーの村民を救った濱口儀兵衛(ハーンの『生神』では「濱口五兵衛」と名前を変えている)の史実が報じられた。
明治 29(1896)年 6.21 日曜日。大阪毎日新聞二面「海嘯の歴史」で浜口儀兵衛の逸話が掲載された。
平成 5(1993)年 8月末、和歌山市で、二百人を越す世界のツナミ学者が集まって「国際ツナミ学会」が開かれた。研究発表論文集の第一ページに、ラフカディオ・ハ-ンの作品として、『稲むらの火』(英文)を掲載。原文は『生神』。
眞貝義五郎(しんかい・よしごろう)
1926年新潟県生まれ
東京大学文学部仏文学科卒業
元・毎日新聞社編集委員。元・神戸松蔭女子学院大学教授
訳書《ラフカディオ・ハーンの「神戸クロニクル論説集」-『バレット文庫』版》
(1994年 恒文社)
眞貝義五郎
黒澤 一晃(ハーンの論説、ハーンの本コーナー)
藤森きぬえ(ハーンの神戸マップコーナーの説明文)
遠田 勝(ハーンの手紙コーナー)
小泉 凡
小泉八雲記念館
神戸松蔭女子学院大学
神戸市立博物館
神戸市立中央図書館
早稲田大学図書館
兵庫県中央労働センター
株式会社ジャパンタイムズ
日本IBM株式会社
(社)中華会館
神戸市
広川町教育委員会
大阪歴史博物館
神戸市立須磨海浜水族園
播磨町郷土資料館
嘉納毅人
産経新聞社
湊川神社
旧居留地地区連絡協議会
岡部仁一 ほか
徳島県立文学書道館
秦 敬一「ハーンとモラエス」
徳島モラエス学会理事長 林 啓介「神戸とモラエス」
モラエス会常任幹事 福原 健生「モラエスの作品」
岡村多希子「モラエスの年譜」
神戸市立博物館
徳島市観光協会(モラエス館)
神戸市 ほか