企画展示
戦争も平和も、災害も繁栄も、私はいつも神戸とともに経験した。
神戸のなかに私があり、私のなかに神戸がある。ー『神戸ものがたり』より
開港を機として、神戸は伝説の重圧を受けない、まったく新しい町として出発した。
このさわやかこそ、神戸の身上であろう。ー『神戸を讃える』より

地図をみればすぐにわかるが、神戸は長い海岸線をもち、帯状の町ぜんたいが、海にへばりついている。
これは町をあげて、南にむいていることで、南には海と太陽がいっぱいだ。
したがって、神戸は翳(かげ)のすくない町である。
山から神戸をみると、なんとなく白っぽい。太陽の光線を思う存分吸いこんで生きている町なのだ。
町のまえにひろがっている海は、神戸の呼吸をたすけている。海がなくなれば、この町は息をとめてしまうだろう。
お国自慢式にいえば、神戸は大むかしの大和田の泊り以来の港町だった。
平清盛がここに福原京をつくり、一ノ谷で源平が戦い、湊川で楠木正成が討死した。
--この楠木正成は「ナンコーさん」と呼ばれ、かつては神戸市民の偶像であった。
しかしよく考えてみると、楠木正成は河内(かわち)の人間であって、
神戸にとって郷土の英雄とはいいがたい。
たまたま神戸で死んだという浅いえにしで結ばれているだけではないか。裏がえしていえば、よそ者の楠木正成を市民が憬慕したことは、神戸がいかに歴史や伝統と縁がうすかったかを物語るものであろう。
たしかに兵庫は、ずっと港町として歴史を生きてきた。が、われわれはそれを京都や大阪の歴史とくらべようなどとは思わない。ケタがちがうのである。
枝葉を切り払って、はっきり言ってしまえば、神戸の歴史は幕末の開港からはじまったのである。平清盛や楠木正成も、神戸にとってみれば、一と揺りでふりおとされるような、そんなはかない泡のような存在だった。とても町の伝統を形成するものとはいえない。
*
開港を機として、神戸は伝統の重圧を受けない、まったく新しい町として出発した。このさわやかさこそ、神戸の身上であろう。
海というものが、そもそもなにものにも拘束されない自由奔放なものである。そして神戸の山を代表する六甲山も、めずらしくさっぱりした山だ。畿内のちょっとした高さの山々は、比叡、高野、大峯、生駒など、いずれも宗教臭がつよい。ところが、六甲山だけはそれがない。言うに足る祠(ほこら)一つなかったのである。
裳裾(もすそ)をひいたこの六甲のスカートのうえにのって、町ぜんたいが南の海に面している。こうした地理的な開放性に加えて、伝統のないというさわやかさがあり、神戸をいよいよ翳のない町にしている。
自由の海にむかい、自由の山を背にした神戸には、自由の市民があつまった。
ふるい伝統のある町へ行くと・・・・・・とかくうるさいものだ。何代もおなじ場所に住み、何代も前のことをあげつらう。
ところが神戸の住民は、百年まえに港がひらかれ、そこに仕事があったので全国の各地からあつまってきたのである。そのとき「ヨーイドン!」で、一斉にスタートをきった。よそ者ばかりである。家柄出身などにこだわる風気はなかった。要するに実力本位である。


*
こうした精神風土は、じつは開港場むきであった。ことに明治初期の開港場は、外来文化の関門という、特殊な使命をもっていた。そこの住民は、外国からはいってくる新しい事物の鑑定人である。
「これはとりいれるべきであろうか?」
という問題に取り組む。
もし伝統の重荷を背負った保守的な住民であれば、外来の文物にたいしてきわめて臆病で、思いきった摂取をためらったであろう。だが、われら神戸の市民は、その点、きわめて身軽であった。
「これ、おもろいやないか」
と、大ていのものにとびつき、大胆な取捨ができたのである。日本の伝統に抵触(ていしょく)するようなものまで、おおらかに取り入れた。
「こいつもためしに入れてやれ。あかんかったらそれまでや……」いささか無責任なようだが、これぐらいの調子でなければ、外来文化の紹介者はつとまらない。卑近な例では、映画、マッチ、パーマネント、ゴルフなど、みな神戸ではじまった。結核療養所、水族館などもそうだが、ペストの流行まで神戸が第一号である。
わるくいえば、一種のお先走りだが、その気風はいまだ根づよく残っていて、戦後では、日本ではじめてスーパーマーケットなどをおっぱじめた。また新しい町づくりでは、神戸は全国の先端をきっている。須磨の高倉山や六甲の鶴甲山を削り、それで海を埋める。土砂は、須磨ではベルトコンベヤーではこび、六甲では河床にダンプ専用道路をつけた。この合理主義の精神も神戸の一つの特徴といえよう。よけいな伝統の重みがないから、
「これはいける!」
と思ったものは、躊躇せずに採用できた。よしあしを判定することにかけては、
外来文化の鑑定人としての経験がものを言う。
国内各地からよそ者があつまっただけではない。外国からもいろんな人たちがやってきた。
彼らは神戸という新しい土地にきて、新しい人生をはじめた。それ以前の経歴を、
あっさり切り捨てた人が多い。神戸はそんな人たちにも、大きく胸をひろげて、うけいれたのである。
いまも舞子に残っている六角堂(移情閣)を建てた中国人実業家呉錦堂(ごきんどう)は、鐘紡の重役にもなったが、三十一歳で日本にやってくるまで、彼が本国でなにをしていたか、知る人はいない。神戸は人生のスタートを切るにふさわしい場所だった。
以前のことは不問に付すような空気ができている。よそ者の集団だからである。したがって、よそ者には暮しやすいところなのだ。
*
神戸とはこんな町である。旅行者はそのことを念頭において、
まず宗教臭のない六甲山へ登ることをすすめたい。そこで神戸的なものに触れ、じっくりと神戸の町を俯瞰していただこう。
六甲を降りると灘、-酒どころである。
銘酒の産地は、水のきれいな場所ときまっている。六甲の花崗岩のすきまで磨かれた水はまことに清澄であり、飲料水を補給する商船は、むかしから日本では神戸の水をほしがった。ただこのあいだ新聞で、神戸が船舶に提供する水は、分析の結果、かならずしも優良でないとわかった、という記事を読んだ。
気がかりなことだ。
灘から三宮へ出る。繁華街であり、神戸のヘソである。
センター街や元町をぶらついてほしい。それもゆっりと。このあいだ東京から来た友人をセンター街に案内すると、「神戸の人間、歩くのがおそいなァ」
と、いらいらしていた。神戸は東京や大阪のような、あわただしい町ではない。
もっとおおらかなのだ。ゆっくり歩いてもらおう。
港見学もわるくない。とにかく、神戸へ来たというかんじが一ばん強いのは港であろう。
山手の異人館群のあいだを、これもゆるりと散策すれば、ますます神戸的なものの味がわかってくるだろう。いろんな国の人びとが、そこに住みついている。しかも、いかにも住み心地よさそうに。
湊川神社を西へ行くと、庶民の盛り場新開地に出る。神戸の浅草という人もいるが、神戸人はそんな表現は好まない。あくまで神戸の新開地なのだ。
西新開地はいまや副都心づくりに懸命である。その一角に立って、神戸の未来を卜(ぼく)してみるのもよかろう。
さらに西へ行けば須磨である。白砂青松といったむかしの面影は失われつつあるようだが、そこにはまぎれもない海がある。コンクリートの枠にはめこまれた港だけではなく、神戸には磯の香のする海もあることを知ってほしい。
*
さきにものべた、伝統がないとか、翳がないとかいったことは、その町を薄っぺらなものにしかねない。神戸はどことなく軽い、といった人がいる。
たしかにそうである。人によっては、映画に出てくるアメリカの西部の町を連想するかもしれない。海にへばりついた帯のような町は、街道に沿って一列だけならんだ安普請(ふしん)の西部の街に似ているところもあろう。
奥行きのことである。街道から一軒の家をつき抜けると、その裏はもう荒野であったというのでは困るのだ。
六甲の裏にある有馬を合併したことは、その意味で神戸に大きなプラスだったと思う。歴史のない神戸の町にくらべて、有馬は温泉郷としてふるくから有名な土地である。
有馬をえて、神戸もようやく翳をもつようになった。だが、どんな陰翳をもつにせよ、神戸の核は、自由の海と自由の山、そして自由の市民によって構成されたメトロポリスである。それだけは忘れてはならない。
太陽にきらめく海。--その光の余韻(よいん)が山を越えて有馬に及び、そこからまた返ってくる。
こんなゆたかな、たのしい町がほかにあるだろうか?
幸福をもとめてなぜさまようのか
ここに住もう
ここに私の未来のホームをつくろう
これは、百年まえ、神戸にきた一外人のつくった神戸讃歌の一節である。
『ワンダフル・コウベ』
(1961年 神戸新聞マーケティング・センター:現・神戸新聞総合出版センター)より

神戸に新しい土地が誕生した。
これまで神戸というまちは、隣接する町村を合併して、東に西に、そして六甲連山をこえて北に広がってきたのである。土地ははじめからあり、それを神戸にとりいれたにすぎない。ところが、こんどは土地のなかったところに土地をつくったのだ。神戸の南の港に、人口島をつくるという画期的な試みが成功したのである。
………
じつは機能的な問題よりも、港南に新しくひろい土地が生まれ、それによってまちに意外な深みを与えたことのほうが重要である。いつも北から南を見ていた神戸が、南から北を見る位置を得た。自分をちがった角度から見ることができる人は、それだけ人間としての奥行きをもつ。まちもおなじではあるまいか。
-『神戸ものがたり』より

ポートアイランド完成の直前、筆者はしばしばシルクロードを訪れた。タクラマカンの砂漠にも、天山(てんざん)や崑崙(こんろん)やパミールの銀嶺(ぎんれい)にも感銘を受けたけれども、それはいわば予想された感動というべきものだった。予想外の感動は、その地方の住民が自然にたちむかうように、人工的な生活をしている事実を、目のあたりに見たことであった。
……シルクロードの生活には、水にかんして、きわめて人工的な施設がほどこされている。カレーズ(坎児井 カンアルチン)といって、天山や崑崙の雪どけの水を、地下水路で何十キロもみちびきいれ、それを飲料にも灌漑(かんがい)にも用いているのだ。
……シルクロードで思わぬ人工の生活を見て、筆者はそのすがたを、ポートアイランドにかさねてみたことだった。
……ポートアイランドは、つねに未来に目をむけるように運命づけられているのだ。これは神戸のまちの性格を凝縮したものともいえる。
金星台に立とう。---
真下が、神戸の中心部である。十二階の県庁の新庁舎が、まるで視野を遮(さえぎ)るように建ち、その西がわにポートタワーが、脇仏のようにつっ立っている。それを中心に、あかるい町が海にむかって、ひろがっているのだ。
………
町ぜんたいが、海にむかっている。これは町の雰囲気を、いかにもあかるく、そして開放的なものにしている。神戸の町の性格をひと口でいえば、その海洋性のあかるさにある、といってよいだろう。裏がえしていえば、陰翳の(いんえい)の欠如であろうか。六甲の山なみは、裳裾(もすそ)をひいて、海にくずれこんでいる。神戸の町はそのなだらかなスカートのうえにのっかかっているようで、地形的にも、なんとなくなまめいたところがある。だが、そのなまめかしさにしても、いたって開放的なのだ。
-『ふりむけば港の灯り』より

神戸の町は、いつ生まれたのであろう?
制度のうえではなく、実質的な誕生を考えるなら、筆者はそれを、「海軍操練所」が設置されたとき、としたい。
海軍営之碑には、将軍家茂がその地形を相して、海軍営の基をつくらせたとある。もちろん事実は、勝海舟の進言によるものだ。地形を相したのは、ほかならぬ勝海舟だった。
神戸が都市として発展したのは、その地形によってである。
咸臨(かんりん)丸艦長として外国を見てきた海舟は、新しい時代の海港の条件を知っていた。そして、神戸の地形がその条件に合うと判断した。
………
その意味で、金星台の海軍営之碑は、神戸の町の誕生を記念するモニュメントでもある。
神戸の町のたましいをさぐろうとするなら、その源流を「海軍操練所」にもとむべきである。

実力本位である。身分の高下は、問題にならない。-この近代的な合理性が、海軍操練所を貫いていた。それが、神戸という町の血管のなかにも、流れこんだのである。
坂本竜馬といえばかならずといってよいほど、引き合いに出されるつぎのような、有名なエピソードがある。--
あるとき、彼は友人のもっている長い刀を嘲笑(ちょうしょう)して、「そんなのは無用の長物というものだ。実戦には短い刀のほうが使いやすい」と言った。
しばらくしてその友人が竜馬に会うと、こんどはピストルをみせられた。
「これが西洋の新しい武器だ。よく見ておけ」
竜馬はピストルをぶっ放して、このまえ推薦した短い刀も、無用の長物視した。
ところが、そのつぎに会うと、一冊の本をみせて、
「これからは武力ばかりじゃだめで、学問が大切だ、おれはいまこの本を読んでいるが、じつにおもしろい」と威張った。本は『万国公法』だった。
この伝説的なエピソードは、幕末のはげしい時代のテムポと、竜馬がそのなかでいかに時代より一歩進んだ思想をもっていたかを物語る。
進歩的思想。-このかがやかしいことばを、意地わるく裏から表現すれば「お先走り」ともいえよう。伝統ある標準的な長刀を勝手に縮めてみたり、あまつさえピストルにかえてしまう。
この合理主義とのりかえの速さは、「軽佻浮薄(けいちょうふはく)」と隣り合わせなのだ。
………
しかも伝統の重圧がないから、新しいものを取り入れることが容易だった。刀よりピストルのほうが便利だとわかれば、誰憚(はばか)るところなく、刀をすてることができたのである。ときには、かわりにすてる刀さえ、はじめからなかったのだから、よけい都合がよかった。
近代神戸人はこうした環境で、このように育った。
坂本竜馬を神戸人の祖と仰ぐのは、こうした類似点があるためにほかならない。

孫文(そんぶん 一八六六-一九二五)は明治末から大正期にかけて、なんども日本にきたが、同国人の多い神戸によく立ち寄った。
………
孫文は神戸という町が好きだったが、とりわけ、北野町、山本通りなど、緑の多い山手の道を愛した。
亡命の革命家は、なにを考えながら、歩いたのであろうか?
彼は脳裡(のうり)に、祖国の未来図を、この異国の港町のうえに重ねていたにちがいない。
……
---北方大港を直隷(ちょくれい)湾青河湾河の間に築く。
---東方大港として上海を発展させる。
---広州を世界港にする。
孫文はこうした祖国の港湾の青写真を、神戸のうえにのせて、透かしてみたことであろう。

西欧文化の浸透には段階があった。しかし神戸の町には、居留地のなかに「西欧」が忽然(こつぜん)と出現した。一般の民衆から隔離された居留地のなかに、それがとじこめられているうちはまだよかったが、雑居地域に指定されたところ、とくに山本通りから北野町にかけて、またしても「西欧の町」が、すっぽりとはめこまれたのである。
………
そうした背景をもつモダニズムは、必然的に一種の薄さをもたざるをえなかった。が、同時に、あやしいまでに幻想的でもあった。薄さそのものが、ロマンだったともいえよう。
異人館地帯の雰囲気は、日本的風土、極端にいえば、シャーマニズムの世界とぶつかって、スパークをおこす。その火花のひらめきのなかに生まれたのが、神戸的モダニズムではないだろうか?

その地形から、神戸は南北の道は坂が多い。
山麓(さんろく)から中山手通りを越え、高架のガードをすぎて大丸前にいたるトーア・ロードも、坂道である。
むかしは、元居留地のオフィスから、山手の住宅に帰る外人たちのコースになっていて、外人相手の店が多かった。しかし、商店街としては、道はばがすこしひろすぎるようだ。むかしからここは、揃いの街灯柱をたてたり、アーケードをつくったりするような、「商店街意識」はすくなかった。教会があったりオフィスがあったり、ふつうの住宅らしい家もはさまっていた。
………
このあたりをあるいていると、ふいに爆竹の音に驚かされることがある。
「ああ、そうか、今日は旧暦の三月二十三日だから、媽祖(マーツオ)さまの誕生日だな」と、思いあたる。
そんな節日の思いあたらないときは、まず近所に結婚式があったと考えてまちがいない。
………
トーア・ロード近辺は、華僑たちが自分たちの故郷の風習を、誰憚(はばか)るところなく、そのとおりにやれた特殊な場所だったのだ。
布引のモラエスにたいする六甲のグルーム。これほど対蹠(たいしょ)的な人間もめずらしいだろう。二人は両極にいる人間だった。モラエスは精神家で、グルームは実務家だった。ロマンチストとリアリスト、文学者と商人。翳(かげ)をもった男と、太陽がいっぱいの男。--そして、グルームはさきにのべた意味で、日本人になりうる外人の一人であった。
………
いったい滝というものは、なにか厳粛なかんじがする。滝にうたれて修行するということもある。瀑布(ばくふ)のとどろきは、なにやら人間精神へのきびしい警告のような響きがこもっている。滝をもつ布引には、そんな空気があった。いかにもモラエスむきである。
しかし、ドライブ・ウェーにとりまかれ、スケート場やゴルフ場をもつ六甲は、ひとえにレジャーの山というかんじしかない。グルームのひらいたこの山は、開祖の性格に似て現世的であり、快適な浅さがある。雪が降らなければ人工スキー場をつくるという、まっしぐらな神経は、あるいは浅いかもしれないが、逞(たくま)しいではないか。これを神戸市民的といいかえてもよかろう。刀がダメならピストルという、坂本龍馬仕込みの、さわやかな合理主義の考え方である。
神戸の海は、港湾とそうでない海にわかれる。
神戸は天然の良港という。むかしから、大陸との貿易交通の門戸であった。北には六甲山系の屏風(びょうぶ)があり、和田岬は西からの波浪を防ぐ。水深、海底地質、干満、潮流、あらゆる点からみても、理想的な港湾である。
神戸から港をとってしまえば、なにも残らないといってよいだろう。港あっての神戸である。
………
港が神戸の核を象徴するとすれば、港でない海は、神戸の余剰を象徴するだろう。いくら拝金主義でも、仕事だけが生活とはいえない。須磨(すま)、舞子(まいこ)という美しい憩(いこ)いの場が神戸にある。おなじ海でも、まったく正反対なのだ。
山を削って海を埋める。山と海の町では、これはかんたんな方程式である。ただし、削った山の土砂を海にはこぶとき、交通の妨げとなってはならない。須磨(すま)では、高架式のベルトコンベアで、山から道路をまたいで、海へ送りとどけている。東部では、六甲山を削った土砂を積んだダンプが、住吉川の河床を走って海にむかう。水のないときの河道は空いている。
「じゃ、それを使おうやないか」と、そこにダンプ専用道路を設けた。
市内の交通を混乱させるおそれはなく、また河床を散歩する人などはいるまいから、交通事故もおこらない。
開港以来、神戸市が身につけた「合理的」な考え方が、こんなところにもあらわれている。
神戸はふりむかない町である。その眼はつねに未来にむけられてきた。いささか軽率でお先走りのところはあるが、まっしぐらに進んできたのである。これからもそうするであろう。
六甲山麓(さんろく)の高台に、筆者は十年以上住んでいる。書斎の窓から、ポートアイランドができあがる過程を、ずっと眺め暮してきた。いま六甲アイランドができあがりつつある。ふりむかない神戸の未来に、どのようなすがたがあるのだろうか。海を眺めているうちに、ふと不安をおぼえることもある。
開港百年をとっくにすぎたのだから、このあたりで、ふりむいてみる必要もあるのではなかろうか。

〈戦争勃発、帰省、スパイ事件と、多事多端であった昭和十二年はすぎた。翌十三年の七月、連日のように雨が降り、五日に六甲諸川は鉄砲水となって、市街全域に溢(あふ)れ出し、未曾有(みぞう)の大水害となった。
「山津波」という時代がかったことばが、まさにぴったりの表現であった。
死傷・行方不明者が四千人に近く、流失または全壊家屋七千、浸水家屋二十二万戸という大悲劇である。
………
このときから、私にかぎらず、たいていの人が水害の前とか水害の後とかいう言い方をするようになった〉
-『道半ば』(水害の前)より
水害の記憶
そごう神戸店前の三宮交差点を洗う激流。昭和13年7月5日
神戸新聞社 提供
あの数日間の豪雨で、1年分の雨が降った。それが昭和13年の神戸大水害だ。その日、学校が臨時休校になった。しかし家へ帰るにも、水が引かないので大回りをして市電山手線に出たが、腰までの濁流である。それで太いロープを真ん中に通し、それを伝っていった。濃い粘土色をした水だった。学期試験の日であった。試験の途中、体操所へ集まるよう緊急指示があった。試験が中止になりそうではしゃいでいた私たちに、先生が真っ青な顔で「何を騒いでいる。街がどうなっているか知っているか」と言う。そのとき、山津波のことを知ったのだ。家は浸かってしまっただろうと思いながら、ようやく家へたどりつくと、ガタガタ震えて仕方がなかった。1階の倉庫は1メートルほど浸水していた。水が引いてからあけてみると、倉庫の中は濡れていなかった。泥水であっため、泥がセメントのような働きをして、隙間を防いでいたからだ。あの時の神戸の町を襲ったのは、このような泥水だったのだ。かつて生田川は加納町を流れていたが、それを付け替えた。ところがその川が流れなくなっていたため、加納町あたりの被害は最もひどかった。父たちが登っていた再度山(ふたたびさん)の姿も、洪水のために変わってしまった。その年の夏は、神戸市内の中学生が総出で復旧作業の奉仕にあたった。死体と出会わないことを祈りながら土を掘った。

〈三月十七日未明、B29の大群が神戸を襲った。
………
焼夷弾(しょういだん)はひとかたまりがザァーと夜空を切って投下される。するとある区画が焔(ほのお)をふきあげる。つぎは別の区画が火の海となる。どうやら重複しないのである。三宮(さんのみや)駅の東がわは青白い焔を立てて燃えあがる。
落下する音までちがっているような気がした。
………
焼けて失われたのは建物だけではない。この「まち」にこれまで住んでいた人が、再びここに集まって住むこともないであろう。
亡(ほろ)びた、というかんじが強かった〉
-『道半ば』〈炎上前後〉より
海岸通りの家へ行ってみると、1階の煉瓦の壁だけが残り、あとは燃えてしまっていた。剣道の面の 金具だけが残っていたが、私は人の骨かと思ってギョッとしたものだった。そのとき形のうえで、私 の思い出につながるものが失われてしまったのだ。
〈六月五日の神戸空襲は、この前が夜であったのに対して、こんどは午前からであった。小学校は疎開で、ほとんどの生徒は農村へ行っているし、中学以上は工場へ動員されている。中学生たちは、工場へむかう途中で、空襲警報の発令を知り、安全と思われる知人の家などに避難したようである〉
あのときは辛かった、人がたくさん死んで…。とくにひどかったのは生田神社あたりで、そこへ逃げ込んだ人たちはあわれであった。私は2回目の空襲があったその後、神戸の親戚知人の安否を確かめるために弟と二人で垂水から歩いていった。再度山の下あたり、中山手通りに差しかかると、人があおむけに寝ている。私は近づこうとしたが、弟が引っ張って連れ戻そうとする。寝ているのではなく死体だったのだ。それからその日、私はおびただしい死体を見たのだ。

〈我が愛する神戸のまちが、潰滅(かいめつ)に瀕するのを、私は不幸にして三たび、この目で見た。水害、戦災、そしてこのたびの地震である。大地が揺らぐという、激しい地震が、三つの災厄のなかで最も衝撃的であった。私たちは、ほとんど茫然(ぼうぜん)自失のなかにいる。
それでも、人びとは動いている。このまちを生き返らせるために、けんめいに動いている。亡(ほろ)びかけたまちは、生き返れという呼びかけに、けんめいに答えようとしている。地の底から、声をふりしぼって、答えようとしている。水害でも戦災でも、私たちはその声をきいた。五十年以上も前の声だ。いまきこえるのは、いまの轟音(ごうおん)である。耳を掩(おお)うばかりの声だ。
それに耳を傾けよう。そしてその声に和して、再建の誓いを胸から胸に伝えよう。
地震の四日前に、私は五カ月の入院生活を終えたばかりであった。だから、地底からの声が、はっきりきこえたのであろう。神戸市民の皆様、神戸は亡(ほろ)びない。新しい神戸は、一部の人が夢みた神戸ではないかもしれない。しかし、もっとかがやかしいまちであるはずだ。人間らしい、あたたかみのあるまち。自然が溢(あふ)れ、ゆっくり流れおりる美(うる)わしの神戸よ。そんな神戸を、私たちは胸に抱きしめる〉
-「神戸よ」:1995年1月25日「神戸新聞」(『神戸わがふるさと』講談社 収録)
1994年、宝塚の講演中に倒れたときは、意識は少しあり、病院に連れていかれたことを覚えている。しかし身体は全く動かなかった。それから5カ月、神鋼病院に入院した。震災が起こった日は、退院して4日目だった。2日後、友人たちが神戸から脱出することを勧めてくれ、大阪への道は潰滅状態で通れないので、六甲を越えて8時間かけて、まず京都へ避難した。だから、あの震災では私は神戸の惨状をあまり見ていない。しかし六甲トンネルまでいくと、災害のありさまを少し見ることができた。「これは大変なことになった」と思った。体が弱っていたし、気も弱っていたから、なおさら悲観的であった。震災に関する原稿依頼があったとき、私は書けないと断った。しかし神戸市民へのメッセージとして、何かを伝えてほしいという重ねての要望があり、「神戸よ」を書いて送信した。不自由な右手を動かしながら、私はあの時、泣きながら原稿を書いた。病気で涙腺がゆるんでいたのかもしれないが、あのような経験は初めてだった。新しい神戸をつくるとするならば、人が安心して住める街をという気持ちを込めて書いた。みんなが望んでいるような街ではないかもしれないが、私が望むのは、本当に人間が住める街だという願いからだった。
《自分は何者かという問いかけが、いつも私の心からはなれなかったということではないだろうか。この幼児の呟(つぶや)きが、じつは私の作家としての出発点であり、ふりかえってみればいつでも私は自分の出発点を見ることができる。そして、自分がいまどこにいるかということも、およその見当がつくことでもあろう》
-『道半ば』〈幼い日々〉
かろうじて立てるようになった頃、台湾に帰っていた時のエピソードとして、聞かされてきた話がある。客間に先祖の位牌とともに、神々が祀られ、その中にひげを生やした神様もいた。その神とは関帝爺(クワンテエヤア)として祀られていた関羽であったと思うのだが、私はそのひげを引っ張り「台湾人というのはこういうものか」と子供言葉で言ったらしい。
日本に暮らして日本人に囲まれて育ちながらも、自分はどうも台湾人らしいということがいつも気になり、子供心に混乱が起こっていたのだろう。
幼い日のことで記憶に残らないはずだが、親戚や近所の人に知られた逸話で、帰省するたびに聞かされたことだけに、私の中にも鮮明な情景として残ったのだろう。
《読書は私の幼少のころからの娯(たのし)みであったが、傾向としては歴史ものと、フィクションの両刀使いであった。小学校のときは、少年倶楽部の愛読者であって、当然、江戸川乱歩の『怪人二十面相』に熱中した。推理小説との出会いが、こんなところにあった》
-『道半ば』〈乱歩賞まで〉
昭和初期の神戸の鉄道は、高架ではなく路面の上を走っていた。鉄道のそばにあった広場で、踏切の上がり下がりを見ながら遊んだということをよく兄から聞かされた。鉄道が高架になったのは、私が小学2年生くらいの頃だった。
元町7丁目、旧三越百貨店の並びの家に住んでいたころから私の記憶も紡ぎだされる。家の向かいにあった建物は、後年になって知ったことだが白鶴酒造の倉庫だった。それらの場所も空襲で燃え、今は道路になっている。
《中突堤とメリケン波止場のあいだの海は、ハシケ溜(だま)りで、ハシケを家とする家族も多かった。彼らの水上生活が、幼い私たちにはロマンチックにみえた。……… ハシケ溜りはにぎやかであった。港の仕事は、遠くから連絡し合うことが多く、ハシケと岸壁とで、喧嘩(けんか)のようにどなり合っていた。ときにはほんものの喧嘩もあったが、彼らはたいてい手鉤(てかぎ)を持っているので、喧嘩は物騒千万であった。みなとことばが荒らっぽいのはいうまでもない。汗のにおい、酒のにおい、屋台のおでんのにおい。猥雑(わいざつ)だが活気に満ちていた》
-『神戸わがふるさと』〈神戸港〉
小学生の頃は、押入れにこもって出てこないこともあった。夢想していたというような格好のよいものではなく、人と会うのが嫌いだったからだ。今でもその傾向は少しあるだろう。真っ暗闇の押入れの中で、幼いながらも私は物語を考えていた。
もともとは華僑の豪商「仁記(じんき)公司」の建物で、典型的な3階建ての華僑商館だった。元の会社名が3階に彫り付けてあったが、それを隠すために父は緑色のペンキを塗ったトタン板を張って囲った。だから外から眺めると、1階の倉庫は煉瓦の赤、2階の事務所はモルタルの白、3階の住居は緑という色になり、私はこの家を舞台に『三色の家』という作品を書いた。
10歳から20歳まで住んだ海岸通5丁目のことはよく覚えている。家は5丁目の中ほどにあり、海岸通りに面していた。通りと平行して港へ貨物を運ぶ貨車が通る臨港線が走り、その向こうはもう海である。 この海岸通りと栄町通りの間に道路があって「内海岸」と呼ばれていた。道の両側には海産物問屋が百軒近く並んでいた。客はほとんどが華僑だったが、独特の雰囲気があった一帯だ。
《---もっと私の心をとらえるものがあった。それは映画である。
兄弟が多く、監督の目が届かないのをよいことに、私は当時、学校では禁制であった映画館によく入った。
言訳めくが、はじめて映画に惹(ひ)かれたのは、英語の勉強がそれでできるのではないかと思ったことだ。すぐそれ以外に自分の心をとらえるものがあることを知った。ことばだけではなかったのだのである。
…………
私は映画と小説で、このころ自分の世界をひろげたように思う》
-『道半ば』〈舞い落ちる旗〉
《平和な時代にみえた。だが、私たちには聞こえなかったが戦乱の足音は確実に近づいていたのである。その予兆が私の小学校卒業直前の二・二六事件であった。
そんなことはまだ子供であった私たちにはわからない。第一神港に入って、カーキ色の制服を着て、ゲートルを巻くのがうれしかった。はじめて革靴を穿(は)くのもうれしかった……》
-『道半ば』〈進学〉
《学生時代と研究所助手の時期を含めて、私は上本町(うえほんまち)八丁目時代と名づけている。最後の一年は空襲によって校舎が焼失して、しかも日本が戦いに敗れるという、劇的な出来事があった。私は自分の履歴を書くとき、このくだりでしばらく迷うのである。》
-『道半ば』〈上八時代〉
《大阪外語の印度(インド)語部を受けることは、はじめからきめていた。英語や国漢などは勉強しないでも大丈夫だという自信はあった。当時、国立の学校で入試に理数の科目がないのは、大阪外語と上野の美術学校と音楽学校(のちの芸大)だけであった。
印度語をえらんだのは、そのころ、タゴールの小説『ゴーラ』を英訳で読み、その影響もあったのだ。
印度の知識人が民族主義をのりこえて普遍主義に至るというストーリーで、私の疑問にたいする一つの回答がそこにあるような気がしたのである》
-『道半ば』〈舞い落ちる旗〉
私はインド文学が好きであった。何となくだが、西洋より東洋が好きであり、中国語が話せた。しかしインドの言葉になると、たくさんの方言があることを知らず、興味をもったのだ。
またインドの詩人タゴールの作品を読んだことも一因かもしれない。日本に彼の文学が紹介され始めたころだった。
もし作家にならなかったら、インド文学を研究する仕事に進んでいたかもしれない。
-『道半ば』〈舞い落ちる旗〉
《昭和十五、六年は大陸の戦線は膠着(こうちゃく)し、物資はしだいに欠乏するようになった。そんななかを私たちは青春時代の門を潜(くぐ)ったことになる。満州事変以来、軍国化の傾向はますます強まって、息苦しい時代になって来た。私たちは青春のにおいを嗅(か)ごうとすれば、そこに硝煙(しょうえん)のにおいを共に胸に吸いこむことになる》
-『道半ば』〈太平洋戦争まで〉
大阪外語は天王寺区上本町8丁目にあり、私は神戸から通学した。5年制の旧制中学校から上級の学校に進む率は25人に一人ほどで、大学で「諸君のうしろには、25人の勤労成年がいることを忘れるな」と言われたことを思い出す。印度語部の新入生は12人ほどで3年制であったが、私たちは繰り上げ卒業になり、2年半の在籍だった。
昭和16年12月8日、日本がアメリカに宣戦布告した日のことはよく覚えている。私は登校途中のラジオでそれを知ったが、学校では全校の学生が集められた。「これは負け戦だ。諸君、からだを大切にせよ」とある教授が言ったと噂になったが、学生は一人もこのことを口外しなかった。
《玉音放送があるとその日の午前に予告されたときも、
--最後の力をふりしぼれと、かしこくも陛下が激励なされるのだ。
という予想のほうが多かった。
だが、私の目には日本が力尽きたのだとしか見えなかった。
………
放送をきいたときは、一般の人たちはまだ半信半疑だったが、放送終了後、人びとは情報を交換し、すぐに状況を把握したのである。
正直なところ、人びとはほっとしたはずである。ほっとしたあとに湧(わ)きあがるものは、人によって大きく異なっているだろう》
-『道半ば』〈戦い終わる〉
《日清戦争によって、我々台湾人は自分の意思にかかわらず、
国籍を清国から日本に変更させられた。
そして五十年後、太平洋戦争の終結によって、再び国籍を中国にさし戻されることになった。
これまた本人の意思に関係なくそうなったのである。
これが私立の学校なら、あまり問題ではなかったが、大阪外語は国立なので、複雑な問題がおこった。
日本人でない限り「任官」できないのである》
-『道半ば』〈上八時代〉
私は1年か2年、台湾へ帰り様子を見るといった気楽なつもりだった。
しかし帰るとすぐに新設の中学校の教員に迎えられ、
教壇に立つうちに情勢が変わって戻れない状態になってしまったのだ。
中国本土で内戦があり、負けた蒋介石の軍隊が台湾に入って来て、二・二八という台湾の大事件が起こった。
私は田舎にいたけれども、銃声が聞こえてきた。
その銃声で、どれほどの台湾人が命を落としたことだろうか。
結局、それで3年半もいることになった。
〈生徒たちにしても、日本語の「あいうえお」をはじめから六年間勉強したかと思えば、
それをご破算にして、こんどは国語(北京語)である。
これは悲壮ではないか。
しかもはじめに六年ほど学んだ日本語は、彼らのマザータングとは大いに異なる外国語であった。
(若いときでよかったじゃないか。……)
そう思うしかなかった〉
-『道半ば』〈学校事始〉
《目の前にあるのが神戸であるらしい。
こんな角度で神戸を見るのは、はじめてではないだろうか。
………
晴れた日であった。十月の終わりで、秋晴れの絶好の日で、まるで私の帰還を祝福してくれているようだった。
神戸が空襲で焼け野原になってから四年がたっている。
復興しているとはいえ、敗戦のあとだから、それほど目ざましいものではないはずだ。》
-『道半ば』〈さらば台湾〉
私が帰ったときの印象は、「神戸は平たくなってしまった」ということだ。
すぐにわかったことだが、米軍キャンプがあり、焼け跡に急造の建物が平たく並んでいたからだ。
一つだけ大きな建物が見えた。甲子園球場だった。
野球の応援によく行き、少年時代の思い出が詰まった甲子園が健在であったことに、私は目頭があつくなった。
〈学究の道を行くことをふさがれて、私は生活のためになにかをしなければならなくなったが、できれば学問の周辺にいたいと願った。そんな職業がすぐにみつかるわけはなく、とりあえず父の貿易を手伝うというイージーな選択をしたのである。私は七男三女の二番目なので、なにもあとを継がなくてもよかった〉
-『道半ば』〈乱歩賞まで〉
〈それでも焼跡らしい場所が、まだところどころに残っていた。その焼跡もしだいに焼跡色を消し、ただの空地になった。それは空襲から十年ほどたったころではあるまいか。人びとはけんめいに働いて、まちの変貌にあまり気づいていなかった。もはや復興というかけ声も、時代おくれになったかんじがしたころ、私は方向を変換して、ペン一本で生活する決意をかためたのである。
サラリーマンというべきか、ビジネスマンというべきか、台湾から戻ったあとの十年は、本来自分がめざした道ではなかった〉
〈どんな小説を読んでも、そのなかに推理の要素があるのに気づいた。ということはどんな小説を書いても、それは推理小説になりうるということにほかならない。学問の周辺に生きようとした私は、はじめ物語作家たろうと目指した。純文学と呼ばれる作品に私は失望することが多かったが、それは物語性に乏しいことが最大の理由であった。乏しいというのは、物語に合理性が無いことも含めてのことであった〉
やはり会社員の生活というのは、自分がめざした道ではなかった。これはだめだな、将来やっても成功しないと思った。
小説が書けるのではないかと思ったのは、娘を徹夜で看病していたときに読んだ小説のおかげだった。それがものすごい小説であったなら、自分には書けないとあきらめただろうが、これなら書けるのではないかと思えたのだ。
それまでも習作のようなものは書いたことがあったが、後年、引っ越しのときに出てきたその原稿は処分してしまった。
小説は勤めを終えて家に帰ってから書くのだが、妻は作家をめざすことにはあまり賛成ではなく、賞をとれなければあきらめるように言われたこともあった。
〈……山本通から北野町の我が家にむかった。その途中でカバンのとっ手がはずれた。仕方がないので、右の脇でカバンを抱えるようにして歩いた。--カバンのとっ手がはずれたというのは、もうサラリーマン生活はやめよということかな。………ふとそんなことを考えた。乱歩賞の選考が行なわれているころだろうから、そんなとりとめもないことが、頭にうかんだのかもしれない。
三本松の坂にさしかかったところで、妻が娘を抱いて、香港上海銀行社宅前の通りに出て、手を振っているのが見えた。そのころ、私はそこの路地から歩いて二分ほどのところに住んでいた。それまで誰もそこまで迎えに出てくることはなかった。なにか特別なことがあったにちがいない。妻もうれしそうに笑っている。
なにがあったのか、私はすぐにわかった〉
自分の生きている時代を書きたいと思っていた。現代につながるものを考えてみると、阿片戦争が浮かんできた。「西」と「東」による戦争が起こり、それが現代まで影響を与えているのだから。阿片戦争に関する資料は、乱歩賞前から集め始めていた。
乱歩賞を受賞してから、出版社からの注文は推理小説ばかりだった。私が阿片戦争について書きたいと話したら、講談社の編集の人が「書いて下さい」と言ってくれて書き始めた。
物語を見る目をどこにおくか。私が最も苦心する点であるが、コスモポリタンとしての視線を持っていたいという姿勢は、基本的には変わっていない。
それは神戸で海をながめながら育ったことや、もうひとつの故郷が台湾であることとも関係あると思う。
私のことを「二つの目をもっている」と評する人もいる。二重のものが自分のなかにあって、一つを取り出したり、もう一つを取り出したりといったことだろうか。
私の作品には最初から、戦争で傷ついた人たちの物語がある。だから推理小説というジャンルでくくられようとも、私からすれば歴史小説である。
私が小説を書こうと思い始めたのは昭和30年代でも前半のほうだった。そのころは日清戦争といえども、まだ関係者が生存していたから、近現代史は正面からは書きにくかったということもある。歴史を物語として、フィクションとして書くことが無難であった。
だから『阿片戦争』を書いた時、ジャンルを変えたという感じは全然なかった。これでようやく現代の門を開いたという感じであった。それが太平天国や日清戦争というようなところまで、ずっと続いていく。
『青山一髪』はちょうど中日戦争のはじめまで書いた。あとは残している。私が生まれたのが1924年で、その翌年に孫文が死んでいる。私が生きた時代、自分もそこにいた時代はまた書けていない。命のある限り、命との競争だ。


世界の港がそうであるように、神戸の港も機械的になってしまい、あまり人間の においがしなくなった。私は 10歳から20歳まで海岸通り五丁目の中突堤近く に住み、毎日、海を眺めて暮らしていた。喧嘩があり、荒っぽい言葉が聞こえてきた。
港の雰囲気は男性的だった。そこは仕事場であり、感傷的な気分など入る余地が ない場所だった。そうした人間のにおいが希薄になってしまった港の光景は、私 には残念なことだ。

神戸の言葉は、大阪や京都とはまた違うものがある。神戸は港町だから、昔から荒っぽい気風があった。遠くにいる船に伝えるためには、簡単に、大きな言葉で伝えなければ届かない。神戸の言葉は荒っぽいのでなく、わかりやすく伝えるために工夫された言葉なのだ。
「なんどいや」という言葉は「なんですか」という意味だが、神戸でしか通用しない言葉の一つだろう。

明治維新の時、神戸の人口は約2万5000人。それが明治10年の「西南の役」の頃には、10万人あまりにもなった。全部よその土地から来た人たちだ。そのため神戸には「よそ者の精神」というようなものがあった。ここで失敗しても恥ずかしくはない。失敗すれば帰ればいい……。新しい神戸人は、実にあっさりしていた。
誰も知らないということを裏返せば、ハッタリが通用する。少々のウソなら言ってもかまわない、というような気分があったし、新しいものを積極的に取り込むことにも関心があった。
竜馬の有名なエピソードだが、みんなが刀をもっている時に「これからの時代はこれだ」とピストルを見せ、みんながピストルを持つようになると『万国公法』という本を示し、「これからは世界の法律が重要だ」と話したということも、神戸人気質の一端を示すものだろう。

有馬は古い時代からの温泉地だ。太閤秀吉も有馬ファンで、大名を集めて大茶会もやったらしい。山に囲まれ、しっとりとした情緒がある有馬を持つことは、神戸にとってしあわせなことである。
私もときどき訪れるが、有馬へ至るまでの景観が楽しみで、四季の景観が変化に富み、心を慰めてくれた。しかし高速道路が開通し、そうした風情を楽しむ余裕もなくなってしまったのだ昨今だ。

楠木正成を祀った湊川神社。その公園には、飛び上がらんとする馬に甲冑姿でまたがった大楠公こと楠木正成の銅像が建っている。
湊川の合戦で亡くなった楠木正成にとって、神戸は終焉の地であるに過ぎないが、郷土の偉人のように思う神戸人は多い。
神戸には歴史や伝統へのしがらみがない反面、歴史に対するあこがれも抱いていたのではないだろうか。

平安時代、神戸が少しの間だけ首都になった時期があった。平清盛が遷都した福原京だ。日本の鋳造技術は未発達で、中国の宗銭を使っていた。しかも宋との貿易は博多に限られていたから、清盛は日宋貿易の拠点をつくろうと遷都したのだろう。
ところが源氏の挙兵などもあり、わずかの期間で都は京都に戻された。福原京の遺跡発掘は、現在も行われている。

神戸市の小学生は、源平合戦や湊川の合戦などをくわしく教えられたものだ。須磨一の谷は平家と源氏が闘った場所だ。地形がせばまった一帯であるため、天下の要衝とされたのだろう。神戸を屏風のように取り囲む摩耶山や再度山などとゆかりのある寺は、みな真言宗である。六甲連山を要衝と見立てて伽藍が建ったものだと思う。須磨寺は「平敦盛の菩提寺」と知られるが、私は空海が唐に学んだ時代のことを書いた『曼陀羅の人』を通して縁が重なった。
昭和62年、平敦盛に関する七言絶句二首を詠んだが、それが古稀を迎えた平成5年、須磨寺境内に碑として建立された。

六甲山は昔から雑木林しかない山だった。近畿の大きな山ならたいてい神社やお寺があるはずだが、六甲山には何にもなかった。だからグルームも安心して開墾して、ゴルフ場をつくれたのだ。グルームは六男三女をもうけた。最後の子が柳(りゅう)さんで、私はこの方からいろんな話を聞いたことがある。彼は子供に英語を習わせず、洋服もよほどの事情がなければ着せなかったという。グルームも日本が好きな外人だった。長崎のグラーバー商会の出張員として神戸に来たグルームは、後に独立して商売を始め、外人たちが組織した神戸の商工会議所のような組織の会頭も務め、その明るい性格から人気者だった。
彼は明治28年に六甲山に山荘を建てた。次第にほかの外人の山荘も六甲山にできた。明治36年にできたゴルフ場には、開設者のグルームや外人だけでなく、神戸人も楽しんだ。

私の作品にハンターズ・ギャップという道が登場する。これは実際にあった道で、北野町の山の麓にあったハンター邸の横からはじまる登山道である。戦前は毎朝、外人がそこから再度山(ふたたびさん)へ登っていったものだ。
ハンター邸は王子公園に移築されたが、明治末期の代表的な異人館である。ハンターは神戸の開港とともに来日し、日立造船所のもととなる鉄工事業を興したイギリス人だ。日本に帰化し、日本人と結婚し、「範多」と名乗った。74歳で亡くなり、外人墓地に埋葬されたと記憶している。

布引の茶店の娘に惹かれた一人がモラエスだ。布引の恋は実らなかったものの、後に徳島の女性と結婚して神戸に住んだ。
モラエスは日本の風土に同化し、森羅万象のなかに神を見ようとした。着物を着て、朝は東方に向かってカシワ手を打ち、誰よりも日本人になろうとした彼だが、日本人からは仲間扱いされなかったという。晩年は愛妻にも先立たれ、娘がいた徳島に移り昭和4年に亡くなった。吉井勇が彼の句を残している。
モラエスは阿波の辺土に死ぬるまで
日本を恋いぬ かなしきまでに

孫文は明治末から大正期に日本へよく来たが、同胞が多い神戸もよく訪ねた。彼はとりわけ緑の多い山手の道を好んだ。そして祖国の未来図を神戸に重ねて考えていたに違いないと思う。北京と天津を結ぶ構想や、上海を中心にして大港湾都市をつくるといった彼の夢は、この21世紀になって実現しつつある。

神戸は百万ドルの夜景と言われるほど、すばらしい夜景がある。ところが残念なことに、海から眺めるしかなかった。これが香港だったら、香港と九龍の両方から景観が楽しめる。私はそれを残念に思っていたが、ポートアイランドができ、南から見る地を得た。神戸に奥行きができたのだ。

中国人実業家、呉錦堂が舞子に建てた別荘が移情閣だ。孫文も立ち寄ったことがあり、彼が書いた「天下為公」の碑もある。
大正6年に建てられたときの場所は現在地より東だが、当時は前には広い砂浜があり、呉錦堂は馬に乗って明石まで遊びに行ったという。
呉錦堂は浙江省の出身で、包み一つを持って日本へやってきた人だが、後に鐘紡の重役を務めた。株に関する話が有名だが、それだけでなく大きな開墾事業を手がけ、彼にちなんだ「呉錦堂池」も残っている。


甲子園は私が生まれた年にできた球場である。十支の「甲(きのえ)」と十二支の「子(ね)」の年であったので、そう名づけられた。プロ野球が盛んになったのは戦後のことで、阪神タイガースも藤村選手などが出てから人気が出てきた。私も一ファンとして、これからも応援したい。

「神戸の浅草が新開地だ」とは、よく言われた言葉である。神戸の盛り場は東の三宮と西の新開地が双璧だった。私が過ごした海岸通り5丁目の家はこの中間にあたり、映画が盛んだった時代には、新開地の映画館によく足を運んだものだ。三宮と比べようもなく映画館が多く、新開地の本通りに軒を連ねていた。その壮観な様子はいまも思い浮かべることができる。


2004年1月、神戸製鋼ラグビー部の試合を見に訪れた。いいスタジアムだ。試合は神戸製鋼が勝ったが、ラグビーが強いことは神戸の伝統である。これからも強くあってほしい。


神戸には汗くさい、人の働く海と、憩いの海という二つの海がある。港でない海は、仕事だけではない神戸の余剰を象徴するものだ。風景を楽しみ、レクリエーションを楽しむ須磨や舞子は、そうした趣がある場だ。
須磨には明治時代に日本で最初のサナトリューム「須磨浦病院」がつくられてもいる。従軍記者として大陸へ渡った正岡子規は、帰国する船の中で吐血し、須磨で療養した。
嬉しさに涼しさに須磨の恋しさに 正岡子規


神戸が発達したのは、兵庫の港と灘の酒造地帯という二つの有力なスポンサーがあったからだとも言える。
灘の酒が有名であるのは、良質な水と米を育む豊かな土地だったからだ。経済的な余裕は、文化的な水準も向上させる。突出した芸術家を生まなかったものの、灘には平均的に高い文化が継承された。灘があるおかげで、神戸に歴史と味わいが醸し出されたと思う。


布引の滝は外人の散歩道だった。観音堂を越えてしばらくすると雌滝があり、さらに行くと雄(おん)滝がある。明治時代の布引は観光客でにぎわう名所であり、茶店も多数あった。
明治30年ごろ、美人の三人姉妹がいる茶店があり、外人たちは彼女たちを目当てに登ってきたようだ。姉妹と結婚した外人もいたが、そうしたロマンスが芽生えるところが布引だった。

有馬は古い時代からの温泉地だ。太閤秀吉も有馬ファンで、大名を集めて大茶会もやったらしい。
山に囲まれ、しっとりとした情緒がある有馬を待つことは、神戸にとってしあわせなことである。
私もときどき訪れるが、有馬へ至るまでの景観が楽しみで、四季の景観が変化に富み、心を慰めてくれた。
しかし高速道路が開通し、そうした風情を楽しむ余裕もなくなってしまったのが昨今だ。

六甲山を開いたグルームを記念して、山上に「六甲開祖の碑」が立てられたが、太平洋戦争末期に壊された。敵性国人のものだからと、こなごなに壊されたのだ。戦後、碑は再建されたが、「六甲山の碑」とされた。再び愛国者によって壊されることを恐れ、娘さんが希望したそうだ。
六甲山はレジャーの山という感じがする。グルームがひらいたこの山は、開祖の性格に似て、現世的で、快適な浅さがある。雪が降らなければ人口スキー場をつくるという発想には、たくましさがあり、さわやかな合理主義の考え方がある。


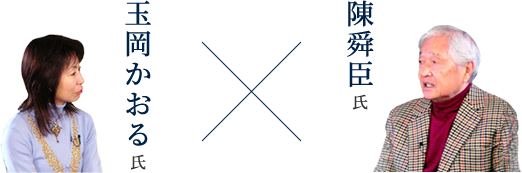
作家。1956年(昭和31年)、兵庫県三木市生まれ。神戸女学院大学卒業。1987年、『夢食い魚のブ ルー・グッドバイ』で神戸文学賞を受賞し作家デビュー。関西を舞台とした『サイレント・ラブ』 『ラスト・ラブ』、山本周五郎賞候補作『をんな紋』など著書多数。近著に松方幸次郎に焦点を当て た『天涯の船』(全2巻)がある。TVコメンテーターや各種行政審議委員としても活躍。加古川市 在住。


港じゃないかと思います.海岸通りの五丁目に長く住んでいましたから…..。 今の中央突堤の西あたりです。 現在はずいぶん光景が変わっていますけど、原風景と言えばやはりあの港の光景ですね。 港といっても大きな船が来るところではなく、ハシケに荷物を捨んで運ぶところです。 港湾労働者がたくさん働いていて,1日に1回や2回は喧嘩がありました。 そうした光景を含めた原風景です。 私が子供の頃ですから昭和のはじめ頃です。不景気な時代でしたけど、 満州事変によって景気が良くなってきた時でした。あの頃は、人間の心の上がり下がり というものが、ひどい時代だったと思います。

変わったなと思ったのは、昭和13年、中学生のときに体験した水害後の再度山の光景です。しかしいま歩いてみたら、昔の面影が残っているんです。いちばん変わったと思ったところが、いちばん変わっていない。あとが変わり過ぎましたからね。
今日も須磨へ来る車の中で「ここはどの辺だろう」と思ったけど、全然わからない。山を見て、「あ、あのあたりか」と思い出せるくらいで、ずいぶんと変わりました。
そうしたことを思えば、私にとっての神戸の原風景は、やはり海と山ですね。

その点は今も変わってないでしょう。だいたい神戸人に自分たちの街・神戸という気持ちが起こってきたのは、そう昔の話ではないと思います。
神戸港が開港した当時の人口はだいたい2万人くらいです。仕事を求める人が集まってきて、明治10年の西南の役--西郷隆盛と政府が戦争した頃には10万人ほどになりました。ほかのところから来た人たちが集まってできた街が神戸です。何か失敗しても、帰れるところがある人たちが集まってきた。そうしたことから、独特の合理的な精神が育まれ、過去というしがらみがない「明るさ」が培われてきたのではないでしょうか。

作家として仕事を始めたのは江戸川乱歩賞を受賞した昭和37年からですが、その頃はやはり東京へ行ったほうが何かと便利だったことは確かです。しかし私は別に東京へ行くこともないと思いました。その時期に神戸から、というより関西から東京へ行った作家は多くいました。関西で作家が仕事をするようになったのは、それ以後です。私たちの世代から後で、司馬遼太郎さんとかもそうでした。
神戸に住み続けるのは、もともとここにいたからで、外へ出ていかなかっただけです(笑)。それに、どこにいても仕事ができる状態になって、ファックスでも原稿を送れます。昔は航空便で原稿を送っていましたが、それでも東京には1日ぐらいかかったものです。

故郷と言っても、「ここしかない」という感じです。神戸だけしか知らないということでしょうか。大学は大阪でしたけど、家から通っていましたから、とにかくずっと神戸が中心でした。戦後3年半ほど台湾に帰っていた時期がありましたけれども、よそへ行こうという気持ちはあまり起こったことはないですね。よそへ行くのが面倒だったからじゃないでしょうか。
この頃は「がんばれ、がんばれ、神戸!」という気持ちです。神戸が元気になってほしいものです。

小説であれエッセイであれ、神戸のことを書くとき、私はめったに取材に出かけない。
熟知している土地だという自信があり、たいていのことは、自家薬籠中の物だと思っている。ただ将来もし地震のことを書こうとすれば、かなりの調査と取材が必要であろうという気はする。
歴史小説であっても、現在の地形を見ておいたほうがよい。作品を書くためでなく、たとえばNHKの特別番組シルクロードの委員として、同行することがあり、それがあとの作品の取材になることもあった。読売に連載した『紙の道』の取材に、紙が西方に伝わるルート、すなわちタラスの古戦場(唐とイスラム軍が戦った所)、タシケント、サマルカンドの紙工房跡などを訪れた。これはなんども訪ねた中国側のシルクロードとあわせて、『チンギス・ハーンの一族』の取材にもなった。結局、チンギス・ハーンを朝日に書くときは、イル・ハーン国の歴史に出てくるシリアやイスラエルをまわるだけでよかった。『桃源郷』を書くときは、残っていた舞台のスペインだけをまわった。
『琉球の風』のときは、かぞえ切れないほど沖縄に足をはこんだ。最初に沖縄の土を踏んだのは一九七二年、すなわち沖縄が日本に復帰した年である。サンデー毎日に連載していたエッセーのための取材であった。毎日の記者であった俳人の赤尾兜子が同行した。おなじ年に文藝春秋の講演に、再び沖縄を訪れたが、この時は開高健、山岡荘八たちと一緒だった。私は講演が苦手だったが、場所が沖縄であれ万難を排して行ったものである。
はじめて来たときは、本島だけでなく石垣島まで足をのばした。 ここは一八五二年にアメリカのバウン号という船から、中国人クーリー三八〇人が虐待にたえかねて、 逃亡し一年七ヶ月のあいだに、 英米の追手に逮捕されたり、砲撃で死んだり病死したりで、生存者一七二人が、島民のあたたかい保護で福州に送り帰された。
この島で不幸にして死亡した一二八人は、島民がていねいに埋葬していて、いまは 改葬されて、 唐人墓と呼ばれている。
この琉球のやさしさが、私はなにより大好きだ。
ニライカナイといって、海の彼方に他界があり、そこからしあわせと豊穣がやってくるという琉球特有の考え方がある。このニライカナイの考え方は、琉球人の客好きと関係がある。 隣人をできるだけ自分たちに福をもたらす存在と考えるのだ。 世界にひろげたい考え方である。
念を押すように謝汝烈は言った。--
「状況も条件も異なりますが、私たちは明のなかに、まず別の国をつくるのです。はじめから大きなことは望みません。明にたいする怨恨(えんこん)を深く抱いた沿海の同志を結合して、そう、南海王国をつくるのです」
「南海王国。……」
啓泰はその名を口にしてみた。
「そうです。その南海王国は、琉球王国を手本にしなければなりません。私があなた方にお願いしたいと申し上げたのは、そのことです。……」
謝汝烈はそう言って、啓泰と震天風の顔を、かわるがわるに見た。
「南海王国。……」
今度は、震天風が噛(か)みしめるように言った。そのあと、彼はかすかにからだを揺すった。こみあげてくる感情の浪(なみ)を、それでおしとどめているかんじであった。
「おわかりでしょうか?」
念を押すように謝汝烈は言った。
「わかります」震天風は身をのり出すようにして言った。・・「われらはその日を再びよみがえらせるのが望みです。明国に支援を要請するのも、そのためです。……誰からも支配されずに、自由に四方の海に乗り出しました。……それは、そう、人間の生きて行く手本になるでしょう。人間、そのように生きねばなりません。……お礼を申し上げます。われらの先祖の生き方を評価して下さったことを……」
震天風は感きわまったか、そこで絶句した。
啓泰はぼんやりとそれがわかる気がした

17世紀初頭の琉球…。27年ぶりに中国・明から冊封使を迎えるところから物語は始まる。かつては対朝貢貿易によって大きな利益を得ていた琉球も、西方諸国の進出、倭寇やそれと結ぶ明の海商の出現によって商圏は徐々に狭められていた。一方、日本では薩摩が、日明貿易の道を開くべく琉球を掌握する必要に迫られていた。200年以上も戦いを経験せず、武器を持たない琉球の人々は、薩摩の侵攻を前にして、徹底交戦論から無条件降伏論まで意見は多様に分かれたが、最終的には名誉ある敗戦の道を選び、その後の琉球をにらんで準備を進めていった。そして1609年(慶長 14年)琉球は薩摩の侵攻に屈する。薩摩の支配下に入った琉球は、日本における対明貿易の唯一の窓口という立場をうまく利用し、表向きは独立国家としての体面を保ちつつ、明や清の冊封を受け続けた。そうした琉球の苦悩に満ちた現実に直面してもなお、琉球人としての誇りを失うことなく、琉球王国の再興を願う人たちや、
新しい王国の建設を夢見る人たちがいた。17世紀初頭から半ばに至る東アジア史を下敷きに、南海王国の建設を夢見で活躍する主人公の青年、琉球の音曲や踊りの素晴らしさを世界に広めたいと願うその弟、琉球人の魂を守り抜こうとする反骨の人たち、経験と実力を頼りに海上交通の覇権を争う海の男たち……琉球、日本、中国の各地を駆けめぐり、新しい時代への対応を模索し続けた人々の人間愛に満ちた物語。
『琉球の風』は、1606 年に中国・明から冊封使一行が訪れ、1663年に清朝最初の冊封使 がやって来た頃までの琉球の人々の物語である。中国は明王朝の末期であり、日本は徳 川時代の初期であった。琉球は第二尚氏王朝七代・尚寧の時代で、明や南蛮貿易で栄え、豊かな琉球文化を育ててきた経済力にも陰りが見え始めていた。ポルトガルやスペインの進出、東アジア会社による活動、委寇の出没、中国沿海の海商の進出などがあり、琉球の貿易は大きな打撃を受けていた。薩摩藩は関ヶ原の戦(1600年)で西方につき廃絶こそまぬがれたものの財政危機に見舞われ、その打開策として琉球の掌握をねらっていた。秀吉の朝鮮出兵以来、明国は日本との貿易を禁止していたが、対朝貢貿易を継続している琉球を掌握することで利益を確保しようとしたのである。その背後には国との直接貿易を再開したいという徳川幕府の思惑もあった。1609年、薩摩軍は琉球に侵攻し、ほとんど無抵抗のうちに全土を占領した。中国は270年以上続いた明朝の末期。独裁体制のもと国勢は衰退の一途を辿っていた。中国東北部ではヌルハチが後金国を建国し、その子、ホンタイジが朝鮮と内蒙古を併合して清国とし(1636年),1644年,明王朝が滅んだのに乗じて北京に遷都。中国最後の王朝となった。徳川幕府は二度にわたる大坂の陣で豊臣軍を破り、キリスト教禁止と鎖国へと傾いていった。外国船の寄港地を長崎・平戸に限定、日本人の海外渡航・帰国を禁止し、さらに1639年、ポルトガル船の来航禁止により鎖国政策を完成させた。
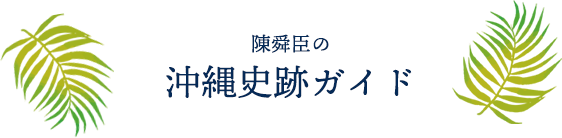

グスクは琉球語で「城」「砦」を意味する。12~13世紀の三山対立時代、各地に城砦 が築かれ、その数は 250 を超えるとされる。各地に有力な勢力が生まれ、それが中 山、北山、南山という三つの勢力(三山)となり、統一されるまでの過渡的な時代にグ スクが築かれたのだ。三山を統一したのは中山であり、琉球中山王と名乗った。

沖縄には台風がよく来る。だからあまり高い建物は建てられず、石造りでひたすら台風の風を避けるのが沖縄の民家の基本である。そして通りの角に刻んであるのが石敢当(イシガントウもしくはセキガントウ)の三文字だ。これは中国の風習を受け継ぐ魔除けであり、T字路や交差点は悪霊が横行するため、道教にもとづき防ごうとするものだ。

沖縄の民家でよく見かけるのが、屋根にある獅子の置物シーサーである。台風による風水害から逃れることはできないが、少しでも被害が軽くなるようにとの願いから、あるいは祈りから置かれるようになったのではないかと思う。

泡盛とはずいぶん付き合ってきた。泡盛は江戸時代には幕府への献上品だった。あのような蒸留酒は日本では飲めなかったからだ。泡盛でも非常にいいものはなかなか手に入らない。瓶(かめ)に入ったものもあり、20年もの、30年ものという古酒もある。泡盛の瓶は呼吸している。泡盛を入れたままにしておくと減っていくので、ときどき継ぎ足しておく必要がある。飲んで足しておくと、いつでもうまい古酒が飲める。

沖縄の楽しみのひとつは、市場を見ることにある。私は沖縄に行くたびに那覇の牧志公設市場へ行くが、そこには豚のあらゆる部位が店頭に並び、台湾の市場を思い起こす。
市場にはあらゆる沖縄の食べ物があって、「ちょっと食べていきなさい」と店の人が声をかけてくれ、すぐに親しくなれる。店の2階には食堂のようなところがあり、食べ物を注文すると、1階にあるよその店の店員さんが運んできてくれたりする。家庭的で、家族ぐるみの付き合いがあって、助け合っている。市場では年長者も大切にされ、それぞれの役割を果たしながらいろいろと差配している。沖縄が長寿社会であることも一因だろうが、もともと長寿の人を祝福する風土が沖縄にはある。
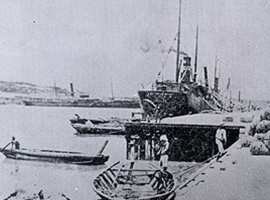
明治以降、沖縄から多くの人がハワイや中南米へ移民として渡った。その歴史はハワイから始まっている。サトウキビの栽培がハワイでも盛んになり、栽培技術にたけた沖縄の人々がハワイへ渡っていったのだ。
沖縄ではハワイや中南米にいる親戚の話が当たり前のように出るが、そのたびに、沖縄はつくづく移民の島だと思う。
何年か前、沖縄からのハワイ移民が100年を迎えて記念行事が行われた。不思議なことは、あれだけ沖縄出身者が多いのに、ハワイには沖縄料理の店がないことだ。故郷の料理にこだわらなかったのは、現地にとけ込もうとする知恵だったのだろうか。

戦前、最後の沖縄県知事が島田叡(あきら)さんだ。兵庫県出身で、神戸二中を卒業し、東大から内務官僚になり、大阪府の内務部長も務めた。
島田さんに沖縄県知事の辞令が下ったのは、1945年1月。誰もが断る中で死を覚悟した赴任だった。すでに太平洋戦争は最終段階で、那覇は空襲で大きな被害を受け、前知事は出張を理由に沖縄に戻らなかったほどだ。
島田さんは沖縄へ行き、最後まで県民とともに苦難をともにした。食糧を調達するために台湾まで出かけてもいる。
沖縄戦は太平洋戦争で最大の人命を奪った地上戦であった。島田さんは県庁組織の解散を告げた後、軍司令部へ向かったが、その後の消息は途絶えたまま戦死した。享年45歳。島田さんを慰霊する「島守の塔」は、戦後いち早く摩文仁の丘に建てられた。

「むらさき村」(元琉球の風テーマパーク)内にある沖縄古来の住まい。ここで私は謝名親方(じゃなうえーかた)のことを思う。唐名を鄭迥(ていけい)とも言った彼は、薩摩の侵攻を受けたとき、降伏する意見が多数であった中で、ただ一人だけ抵抗した宰相職の人だった。そして島津から誓約書に連判を求められた時、これを拒んで処刑された。
これまで頑迷な抵抗をした人としてあまり評価されていなかったが、最近では沖縄の意気を示した硬骨の人であると再評価されるようになってきた。『琉球の風』では、彼のような人物も主人公の一人とするつもりで書いた。

首里城は琉球王家の城であるが、何度も焼けている。板葺き屋根であったので、火災には弱かったのだ。瓦の技術は入っていたが、台風に対処することができず江戸時代末までは板屋根の時代が続いた。
大正時代、荒廃が進む首里城を壊して新しく造ろうとする政府の動きがあった。これに反対し、修復を強く進言したのが著名な建築家、伊東忠太博士である。東アジア文化の合流地点にある歴史的な建物を保存するよう政府へ電報を打ち、これが契機となって数多くの文化財が保存・修復された。
伊東博士は建築と風土を結び付けて考えていた。風土から生まれた建築物は、その中で磨かれ、かけがえのない造形を持つということを熟知した博士の努力で、沖縄の建築物は生き返った。
首里城は沖縄戦でほとんどが破壊されたが、設計図は残っていた。
もし設計図が保存されていなかったら、修復の手立てはなかっただろう。

琉球は武装をしていない国であった。武器を持たず、貿易によって世界をつなぐ架け橋になろうとした国であった。
「万国津梁の鐘」は1458年に鋳造された。当初は首里城正殿にかけられていたが、現在は沖縄県立博物館に所蔵されている。
その銘には、自らを「蓬莱(ほうらい)の島」と称し、「琉球国は朝鮮と中国と日本の間にあって、その橋渡しをする」と宣言している。日本が平和憲法をつくるずっと以前から、貿易によって世界と友好関係をはかろうとしていたことが、ここに示されている。

沖縄の墓地は地形が良い斜面につくられている。墓も仏教とほとんど関わりがない。中国と日本の影響を受けてきた沖縄にあって、仏教の影響力が伝統的に小さいことは不思議なほどである。
沖縄には固有の先祖崇拝が、広く、深く浸透している。亡くなった人の骨を何年か後に洗い清める「洗骨」という儀式もある。先祖の霊が子孫を護ってくれ、それに報いるために先祖を崇拝するという信仰が非常に強い。
玉陵は王家の墓地だが、こうした先祖崇拝にもとづくものだ。

沖縄の遺跡は沖縄戦で破壊されたものが多いが、崇元寺の石門は戦火に耐え残っている。崇元寺は琉球王朝の王の菩提寺だった。臨済宗の寺であるが、仏教はあとから習合したもので、もともとは琉球古来のシャーマニズムがあった。
琉球国は中国を宗主国とし、国王が替わるときは中国皇帝の承認を得た。中国から皇帝の名代として冊封使を迎える儀式が数十年に一度行われたが、この王朝最大の儀式にあたって、最初の主会場となったのも崇元寺であった。

琉球王家の別邸が識名園である。1800年、中国(当時は清)からの冊封使を迎えるために造営されたと言われる。王が替わるとき、中国から派遣される使節団である冊封使は、4カ月から8カ月滞在し、数百人の規模になる。長短はあるが、20年から30年に一度やってくる。冊封使が詔勅(しょうちょく)を読み上げて琉球王と名乗ることができた。
冊封使をもてなすために琉球の芸能も発達したとも言われるが、識名園も、彼らをもてなすために造られたものである。
別名を北山城と言い、三山時代の北山の根拠地であった。石灰岩石でつくられ、西から東へ向かって次第に高くなっている。私もなんどか石段を登り、奥の本丸跡まで行った。


沖縄には聖なる場所がほうぼうにある。その中でも最も大切にされている聖地が斎場御嶽だ。鳥居も神殿も、人工的な造形物はない。進むにつれて樹木がうっそうとし、深い木陰が続く。御嶽そのものが神なのだ。そこへ行ってお参りをする。そういう祈りの場だ。
切り立った岩の間から、天気がいい日は久高島が見える。久高島も琉球の建国神話が展開される聖地であり、斎場御嶽でも久高島でも、木の葉一枚、石ひとつ持って帰ってはいけない。沖縄の人々の心が込もったよりどころであり、神々しいところだ。


座喜味城は平らな丘に築かれ、登らずにすむ城だ。やさしも表現され、私にとっては親しみがもてる城である。
中が劇場のようになっており、数年前、シェークスピア劇が公演されたこともあった。



ペリーがアメリカ艦隊を率いて来航したとき、測量した城が中城だ。ペリーは「要塞の資材は、石灰岩であり、その石造建築は、賞賛すべき構造のものであった」と記している。
万座毛とは不思議な名前だ。「毛」とは野原の意味で、かつて琉球王がこの地に立ち寄り、「万人が座するに足りる」すばらしい風景だと話したことから付けられた名称だと伝えられている。
私は1995年、この万座のビーチに60日余り滞在し、リハビリに専念した。毎日、砂浜を1時間ほど歩くリハビリで右手が使えるようになり、なんとか文字が書けるようになった。
私自身の再生の地とも言える思い出の場所だ。

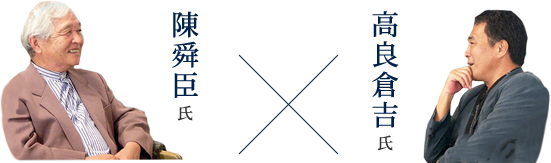

陳:『琉球の風』の取材で初めてお会いしたのは1992年のことでした。それから2年後に私は脳内出血で倒れたのですが、作品を書き上げた時にお礼にこなかったからだと思って、斎場御嶽(せーふあうたき)へお参りしました。それで少しは良くなったようです。
高良遅まきながら、ご挨拶なさったわけですね。
私の一番の思い出は、連載されていた作品の最初の読者だったということです。編集者から歴史的な事実関係をチェックしてほしいと、ものすごい量の原稿が送られてくるのですが、陳先生が憑かれたように書き続けておられる姿が想像できました。『琉球の風』が紡ぎ出されていく過程の、すごい瞬間に立ち会ったなという印象でした。
しかし小説家というのは、あんなに短時間に、集中的に書かれるものなのですね。
それともう一つは、執筆に入られる前に取材に来られた時に、あちこちお酒をご一緒したことです。
陳:飲みましたね。あの頃は、まだ飲めた時でした。
高良先生が取材の場や酒席でいろいろ話された言葉を思い出しますと、今からすれば、小説の構想を見すえながら話されていたという気がします。
構想にはどれぐらいの期間をかけられたのですか。
陳:あの作品を書きたいという思いは、ずっと前からありました。実際に構想に入り、資料を集め始めたのは、1年ほど前からだったと思います。

陳『琉球の風』以降のことも書き加えなければと思っています。できれば短編でも、という望みはいまもあります。
高良親しく話を聞かせていただいたからだと思うのですが、琉球という小国の厳しい時代を生きた人たちの心根と言い ますか、気概、誇り、あるいは屈折した思い、そういったことに先生はすっと入っていかれた。 すごい方だと思いました。
陳それは私が植民地時代に生きた人間だからです。台湾植民地時代の日本国民 として20年過ごし、それから中華民国に変わり、そのあと日本で生きてきたわ けでしょ。そのことが、琉球の歴史と重なっているからではないでしょうか。
高良琉球だ、日本だという国家の壁みたいなものがありますが、主人公たちは そうした壁を比較的低くして、むしろ東アジアという世界を舞台に生きている。 そういう人間を描くことは、琉球の歴史を研究している者にとっては、 かつてからの願いでした。琉球の歴史はがんじがらめになっている部分がたくさ んあるけれども、実際はそれを超えて活動する勇気のようなものがあったはずな のです。ところが、いかんせん歴史研究者というのは、 そういったことは泡盛を飲んだときにしか…(笑)。
陳あの時は飲みましたね。
高良ちょうど今日のように風の強い日でした。浜で飲んでいる先生はじめ私たちみんなが、あの闇の中で宙に浮かんだような感じで、非常に浮遊感のある飲み会だったように記憶しています。

高良首里城の復元工事がとりあえず終わり、1992年11月2日に完成パーティーがありました。私はその日の天候が気になっていたのですが、見事に晴れ渡り、夜はお月様がものすごくきれいで、首里城の真ん前に丸い月が浮かびました。
これで首里城も『琉球の風』も大丈夫だと感じました。
『琉球の風』の時代の日本は、信長や秀吉、家康といった大きな人物が生きた時代で、普通の人々はそういうスーパースターから捉えていると思います。その時代に対して、「ちょっと南のほうを見てごらん」という陳先生の小説のコンセプトが、何かお月様に祝福されているように思えて、私はパーティが終わってから、首里城にある物見台で15分ぐらいずっと月を眺めていました。
陳作品は1992年秋に発刊されましたから、首里城の復元パーティーには間に合いましたね。テレビでは、大河ドラマとして1993年に放映され、NHKエンタープライズが制作を手がけました。
高良1992年は沖縄にとっては復帰20周年という節目であり、首里城が復元され、そして『琉球の風』というひとつの深い世界を先生がお書きになった。後々の時代にも、1992年という年は語り継がれていくと思います。
ただ、この作品を執筆されるにあたって私が少し心配したことは、沖縄にとってはいちばんデリケートな時代、薩摩の侵攻前後をどういうふうにお書きになるのかという点です。書き方によっては、琉球の人間からすれば自分たちの心根を反映していないと言われかねないデリケートなテーマです。
陳見方によってずいぶん違いますからね。
高良ところが先生の小説は、厳しい国難の後に人々はどう生きていったかというところを書いておられます。

陳書きたいことがたくさんあって、『琉球の風』で描いた前の時代、大貿易時代のことも書きたかったんです。構想はいろいろありました。
高良アジアとの交易時代ですね。私たちにすればぜひ書いていただきたいところですけど……。あれくらいのスケールで時代をお書きになれるのは、陳先生以外にはいらっしゃらないと思います。
陳アジアと交流した中で、福建の人たちが琉球に来て一緒に仕事をしています。その中で琉球の人たちはみな褒められているんです。
人を騙さないとか、人買いは絶対にしないとか……。
あの頃は奴隷貿易をしていましたから。
高良一人の歴史研究者として、琉球がアジアに羽ばたいた時代はもちろん好きな時代です。ところが薩摩軍の侵攻以降の時代については、これまでの多くの歴史家たちは非常にネガティブで暗いイメージで描いてきたわけですが、私は全然そう思っていません。この20年ぐらい歴史研究をしてきた者はみなそうです。「沖縄の近世はもっとダイナミックで、面白い時代だ」と私たちが言い始めたちょうどその時期に『琉球の風』が出ました。歴史研究者としても、ちょうどいいタイミングでお手伝いできたと思っています。
陳薩摩侵攻以降も、たとえば牧志朝忠が活躍した頃は面白い時代ですね。彼は語学が堪能で、外交官として異例の出世を果たします。
彼について書きたいと思ったのは、『阿片戦争』の取材の中で、林則徐(りんそくじょ)の日記を読んだからです。林は故郷・福州から北京へ行き、南下して広州へ着いた時、手紙をいちばん早く家に届けるにはどうすればいいかと尋ねます。すると琉球館から船が出るから、それが早いという情報を得るのですが、それを読んだとき、こんな時代に広州で琉球の人が活躍していたのかと驚いたからです。
高良大河ドラマ「琉球の風」は、ニューヨークでも日本系放送局が放映していました。翌年に招聘されてタイのアユタヤで講演した時も、現地の研究者はあのドラマを見ていて、「うらやましい」と言われました。タイでは王朝を正面に据えた歴史ドラマは、絶対に作れないそうです。
そのあと間もなく私は大学の教師になりました。学生の3割から4割弱は他府県から来ていますが、高校生の時にあのドラマを見て、沖縄の歴史を勉強したいと思ったという学生も結構います。
彼らは沖縄を観光リゾートのように思っていますから、過去にこんなドラマがあったのかということを初めて知ったみたいです。
琉球大学法文学部教授。愛知教育大学卒業。琉球史の内部構造および琉球・アジア交流史に関する研究を展開。沖縄学の父として著名な伊波普猷(いはふゆう)氏にちなむ賞を「琉球王国史の課題」で受賞。
ほかの著書に『沖縄歴史論序説』『琉球の時代』『琉球王国の構造』『琉球王国』などがある。
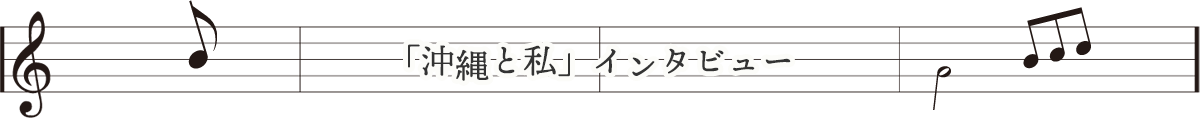

いつ頃からとは、はっきり言えないですね。ちょうど物心がついた頃からでしょうか。神戸の海岸通り五丁目に住んでいたことがあって、あのあたりは沖縄出身の人が多かった。家の前には中突堤があり、戦前は日本と沖縄を結ぶ航路の発着地でしたから、沖縄の人が多かったのでしょう。家の2、3軒隣には、「泡盛」という名の店もありました。
その後、歴史に関心を持つようになり、琉球が特殊な地位を築いていたことや中国との関係について考えるようになり、いつか沖縄のことを書こうと思っていました。日本に復帰した年に初めて沖縄を訪れ、以来30年以上、毎年来ています。

たとえば阿片戦争の取材でいろんな文献を見た時、林則徐の日記を読みました。この人は阿片戦争の英雄で福建の人ですが、彼が北京から広東へ行ったとき、無事に着いたことを故郷に知らせようとして、どのようにすればいいかと聞くわけです。すると、ちょうど琉球の船が出るから、それに頼むのがいちばん早いと言われたと書いている。「ああそうか、あの頃にも琉球と広東の間で交易が行われていて、琉球の人も頑張っていたんだなあ」と思いました。
阿片戦争は1840年に起こり、当時の日本は鎖国をしていましたが、琉球の人たちは、それよりずっと前から中国と貿易をしていたのです。

沖縄は故郷の台湾と気候も近いし、風物や食べ物を見ても故郷のことが偲ばれます。それに日本の植民地時代の台湾には沖縄の人が多く、特に学校の先生にたくさんおられました。日本は台湾を侵略してから悪いこともしたけど、いいこともしています。そのひとつが教育の問題で、沖縄の人がたくさん関わっているのです。

琉球のことを書こうとした時、最初に思いついたのは講演でお世話してくださった沖縄タイムスの玉城さんという方でした。それで玉城さんに連絡したことを思い出します。もう長い付き合いですが、彼がほとんどセットしてくれました。
琉球はもともと書きたいテーマで、NHKから依頼があったときは、ちょうど潮時だと思いました。知識が少ないと困るけど、かなり知識が増えた頃に依頼されたので、ちょうどいい時期だったと思います。
NHKの紹介で歴史学者の高良倉吉さんにもお会いしました。一杯飲みながらいろいろ話をしたのですが、そのあとで高良さんは、伊波普猷さんの顕彰碑がある場所へ私を連れていきました。顕彰碑に向かってお祈りされてから、「お引き受けします」ということで始まったんです。伊波普猷さんは沖縄学の父と言われる方で、高良さんたちは大先輩として尊敬されています。

だいたい史実だと思いますが、実際の状態はあまりよくはわかりません。薩摩のほうでも隠していることがあり、琉球のほうでも隠そうとしたところがたくさんあります。ですから、わからない部分は、小説家が想像してつないでいけばいいのではないかと思います。
『琉球の風』にはいろいろな登場人物が出てきますが、史実には出てこない人物もたくさんいます。主人公の啓泰や啓山といった名の人は実在しません。
しかし、そうした立場の人はいたはずだと思います。琉球に起こった一つの悲劇の中で、歴史の中ではなかなか出てこない人たちの心を、彼らを通じて探ってみたかったのです。

琉球は薩摩に侵略されて、その支配下にありましたが、良かったことは国際的であったことです。日本と中国、朝鮮との関係もいろいろありますが、東アジアとの交わりというのようなものが、その頃からできてきます。組踊は沖縄の大きな文化遺産ですが、これは薩摩が来てからできたものです。中国からサツマイモが伝わってきたことも、そうです。
だから琉球は薩摩に侵略されたのではなく、結びついたのだと考え、その始まりを書きたいと思いました。ただ単にやられたのではなく、抵抗しながらも新しい文化的基盤ができていったことを書きたかった。そのためには民族的なことは取り除いて考えるべきだと思いました。
19世紀の初めは世界各国との船での交易がはじまり、視野が広がっていく時代でもあり、世界の文化を取り入れるという一種の高揚した気持ちがあったと思います。そうした時代の空気もうまく取り入れたいと思いました。

神戸で大震災があった前の年に倒れて5カ月入院しました。ちょっと動けるようになったので、沖縄でリハビリしようと思って退院した4日目にあの大震災が起こりました。それで神戸を出て、京都に1週間ほどいて、それから沖縄へ来たわけです。沖縄では50数日リハビリをしました。
だから沖縄という地は、私にとっては『琉球の風』の舞台だけではなく、再生の地であると同時に、癒しの地でもあります。リハビリは辛いことでした。ビーチを歩くと足跡がつきますが、右足は軽くしかつかないけれども、左足の跡は強くつく。自分が歩いたあとを振り返るとわかるんです、右足にもっと力を入れなければということが……。リハビリでは言葉で表せないほど妻に励まされました。夫婦二人の合作みたいなものです。神戸の復興に合わせるように私もリハビリをしたわけですが、神戸もだんだんと元気になるように祈っていました。
私の台湾での幼い頃の思い出は、客間のテーブルにあがり、まつられていた関羽の像のヒゲをひっぱり「タイワンラン シ チョン エ クワン」(これが台湾人かいな)と言ったことだ。思い出というより、周りの大人から聞かされた。ーインタビューより



台北では本屋や市場の屋台で食べたりしていた。市場は好きな休憩場所。屋台の焼豚円(ショーバーワン)が好きだった。


教師時代、1ヵ月程避暑がてら訪れていた。
祖師廟は、北宋の英雄「陳昭応」を祀り、陳姓の人々が参りにくるところ。
-インタビューより-


台北県立新荘初級中学教師時代に過ごした街。
当時は田園地帯だった。そのころは橋はなく板橋とは渡し舟で結ばれていた。
-インタビューより-


約260年前からつづく台湾で有名な寺院。
神仏泉交で観音菩薩のほか媽祖や関帝などの道教の神々も祀られている。
-インタビューより-
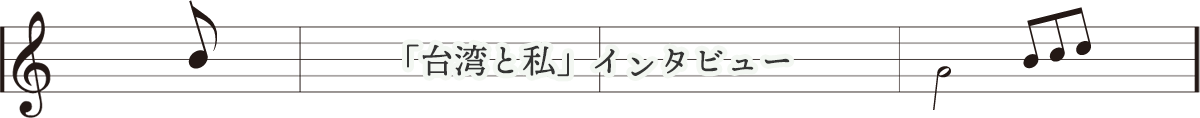

まだ物心つかない時なのですけどね。最初の思い出というのは、 僕が椅子からそのテーブルに這い上がってね。そこに関羽さんの像 があるんですよ。その髭を引っぱって、『これが台湾人かいな』と 言ってね。台湾語でね・・・。
その言ってたというのは、僕は覚えてないけどもみんなが覚えて いるんです。周りの大人がね・・・。いつも、それでからかわれる んですよ。
その時は、日本にたくさんの留学生が来てたんですよ、台湾の留学生がね、千人ぐらい来ていたんですよ。それから戦争中に日本に連れられて来た工員・・・。その人達が帰る時、何千人、何万人という人たちを運ぶ船があるんです。だからその船に乗って帰ったわけなんです。それも送還が済んだらもうないんですよ。帰れないんです。ちょっと長居になりましたね。
その台湾へ帰る時に、李登輝さんとかね、何既明さんらも一緒に帰ったんですよ。それで、何既明さんと李登輝さんはその船で親友になったわけです。
その間のことねえ、辛いことがありましてね。2・28事件っていいましてね。
そのきっかけはね。煙草はね、中国では誰が売っても構わないんですよ。日本の組織そのまま専売にしたんですよ。他の土地では自由に売れるのに台湾だけは専売。政府が儲かるからね。それで煙草を売ると、時々取り締まるんです。
あのときはね、まだ台湾は、前の年の八月まで日本の領土だったんですから日本人は随分いましたからね。日本的な雰囲気は随分あった時代です。だんだんそれがなくなっていく時代で、さきほど、言ったような2・28事件のようなひどい目に遭ってるって言う時代になってきたんです。
そうです。身辺のあれから始まりましたね。処女作のね、『枯草の根』とかね、『三色の家』とかみんな自分の身辺を題材にした。だから取材しなくてもいいんですよ。知ってる社会のことを書きましてね。まあ何とかそれで江戸川乱歩賞いただきましてね、主にミステリーの世界でね。で、中国の歴史の『アヘン戦争』というのを書きました。
そのあとです。そのあと結局僕達の生きておった時ですけどね。これは、まだわからないことがたくさんあります。だんだん今、真相がわかってきてるんですね。だからそれを資料にして書こうと思ってたんですけど、どうも歳をとり過ぎましてね。間に合うかなという気持ちです。構想はいっぱいあるんですが、選ばなきゃいけない、その中から・・・。その中で僕がやりたいのは、この中国人の心、そして世界の心とね。中国人といってももう中国だけじゃ駄目なんです。世界中を目において考えるということ。中国古代の考え方でね。
そうですよ。他民族に征服されたこともありますね。それはモンゴルとか、それから清朝の時代ですね、満州族が支配した・・・。支配を受けたことも何べんもある。そして、そんな中で、中国人と言ってるけど本当の中国人かどうかはわからない、中国人が何かわからない。漢族だと言っても漢族が何かわからない。
あんまり変わらないですね、関羽さんのひげをなでた時代からね、台湾人とはこんなものかと、自分は違うのか、世界はみんな同じじゃないかという、そこは言ったか知らないけれどね、なんかおかしいなと言う気持ちがあったんですよ。
地中深く張り、まわりの土壌とすっかりなじんだ強靭な根が、にわかに草を失ってしまった。これまで人びとは、土のうえの草しかみていない。根はなおも、いやこれからもっと強く、生きつづけようとするのに。
彼は海岸通に出てから、古風な水上警察署の塔を仰ぎながら、東へむかってゆっくり歩いた。威圧するように聳えている塔は八角である。そして、ご丁寧にも、四面に時計をはめこんでいる。もっとも、海に面した南側の時計は、陸地から見えない。西側と正面の時計は、三時五分まえをさしていた。陶展文は自分の時計を見た。時刻はちゃんと合っている。塔の時計は飾り物ではないのだ。チャータード銀行をすぎると、東側の時計が見えてきた。それは四時四十分をさしていた。彼はそこで、しばらく立ちどまった。腕時計の針は進んで、ちょうど三時になった。塔の正面の時計も三時である。東側のは、相変らず四時四十分のままだ。つまり、故障でうごいていないのである。
-『枯草の根』(1961年 講談社)より
神戸、海岸通。六階建ての「東南ビル」地階で中華料理店「桃源亭」を営む陶展文。ある日、彼の漢方薬の患者で象棋(しょうぎ)仲間徐銘義が首を絞められ殺される。彼は、アパート経営と金貸しを営んでいた中国人で、かねてから新聞記者の小島より政治家の汚職事件に絡んで目を付けられていた。事件発生当夜、友人朱漢生と徐銘義宅へ象棋を打ちに行っていた陶展文はこの身寄りのない友人の事件の真相解明に乗り出す。
市会議員吉田庄造とその甥、同じ「東南ビル」五階で中国人商社を営む李源良とその客人である南洋の著名な実業家席友仁、そして一枚の脅迫状。複雑に絡み合った糸がほどかれた末には、繊細な伏線によって導き出される衝撃の事実が……。
1961年、第七回江戸川乱歩賞受賞作品。探偵陶展文が活躍するシリーズとしては、『枯草の根』に続いて、作者の実家である華僑商館をモデルに青年期の陶展文を登場させた続編『三色の家』(1962年)や『割れる』(1962年)、『虹の舞台』(1973年)などの長編と数点の短編小説がある。
私が最初に考えたのは、誰もがミステリーを背負っているということです。人間だれもが、過去に一つはミステリーがあるはずです。近現代史を書く上で、ミステリー仕立てにできないかと考えて著したのが、この『枯草の根』でした。
この作品は戦争中の愛憎を巡る問題から殺人が起こるという設定であり、日本と中国の近現代史を描きたいという思いから外れた作品ではありません。
これを書いたのは40年前です。この主人公をもとに新しい作品を書こうと思っていましたが、まだできていません。主人公の前身は不明にしています。何かの政治的な問題で日本に来て、それで日本にとどまっているという記述にとどめ、あとは大きな小説を書くときにふくらませようと思っていたのですが…。
ミステリーは若くないと書けませんね、エネルギーがいりますから。私自身、もう一度書いてみようと思うし、勧める人もいますが、体力が必要ですね。
--積弊を根絶する。
包囲の結果が、どうなるかわからない。しかし、もはやその場のがれはゆるされない。膿(うみ)を出しきるためには、どんな痛い目も覚悟すべきである。--これが、林則徐のゆるがぬ信念だった。
--破壊によって、突破口をつくる。
連維材は胸にひめた未来図を、ひろげてみる。
相対している二人の呼吸は、あるところではぴったりと合い、しばらくすると、なんとなく離れて行くような気もした。
林則徐は思いきった行動によって、衰世にピリオドをうつつもりでいた。しかしながら、連維材にとっては、それは終止符であるよりも、新しい世界の開始であった。
二人の呼吸は、この個所で、みだれる。
傾きつつあるもの。--李芳は病におかされた自分の肉体で、それを象徴しているかのようだった。
--没落はするが、それに他人の牙は借りぬ。われとわが牙で、潰れてみせよう。
李芳の眼が、そう語っているような気がしてならない。
この国が生まれかわるには、清新な山中の民、海浜の民が、力をえなければならない。連維材はそう信じていた。そのためには、破壊が必要なのだ。破壊の過程は、彼の頭のなかでは、直線的なものとしてとらえられていた。しかし、李芳に会って、彼はそれがもっと屈折した形をとる可能性を考えるようになった。
崩壊すべきものが、ある時期には時代の主人公となって、自らをうち砕く役をつとめるのではないか?
弱々しい李芳のからだを見たばかりなのに、連維材はかえって、相手のひめている力の大きさをかんじた。
-『阿片戦争』(1967年 講談社)より
1832年4月2日、清朝第8代道光帝の時代、外国貿易の窓口を広州一港としていた清国の禁令を破り、英商船アマースト号が厦門(アモイ)の港に近づいてきた。東インド会社による中国貿易独占権が廃止される直前のことであった。
独占権が廃止されると英国商人は競って中国に商品を持ち込んだが、中でも利益が得られる阿片の量が急激に増加。このため銀が大量に流出して国の財政を圧迫した。そのため清朝は阿片の販売・吸飲を禁止するが、賄賂の横行、行政機関の頽廃が広がり、阿片の害毒は確実に中国の社会を蝕んでいった。
この状況を打開するため、皇帝は、有能な官吏である林則徐(りんそくじょ)を広東へ送った。この清廉潔白な官吏に心酔し、母国の将来を託そうと、早くから経済的支援を続けてきた豪商・連維材。その心底には漠然とした破壊欲が見え隠れするが、周りには様々な役割を果たす人たちがいた。一方には彼らをおとしめようとする人たちの権謀術数、そして罠……。
欽差大臣に任命された林則徐は、広州に赴くと、英商人が所有する阿片の全面的引き渡しを要求し、これを廃棄するという強行措置を断行。しかし、英国も阿片を扱わないという誓約書へのサインを拒否。交渉が難航する中で、1840年2月、英国政府は出兵を決定。6月には全艦隊がマカオ沖に集結して、北上を開始した。
これで清朝はにわかに和戦論に傾き、林則徐を罷免する。しかし、香港島の領有などをねらう英国は停戦交渉に応じず、本格的な攻撃を加えて次々に要塞を陥落させた。ほとんど無抵抗のまま、上海、鎮江が占領されたところで清朝はついに屈伏。長く続いた封建社会の土台は大きく揺らぐことになった。
大英帝国が威信をかけて清朝に開国を迫った歴史上の事件に真正面から向き合い、膨大な史料を渉猟して骨組みを固めるとともに、そこに生き、死んでいった人たちの、ぎりぎりの姿をその行間に織り込んで、事件の核心に迫ろうとした力作である。なぜ、あの大清国がいとも簡単に蹂躙されたのか……。
中国という国が外国の国と実際的に接したのは、阿片戦争が初めのことでした。「イギリスなどは政府間で約束を交わしてきちんと取引したい。ところが清国政府は、民間でやるのだったら構わないという姿勢であり、そのためイギリスは清国政府に正式に貿易を認めさせるために戦争をした」。--これまでの教科書は、阿片戦争について、こうした記述をしていました。
ところが、それだけではなかった。それを書きたかった。イギリスがひどいことをしたことを書かなければいけないと思ったのです。
いろいろな資料を調べ、たとえば林則徐の日記も読みました。その中には、流通についての話も出てきます。広東から福建の家に向けて無事に着いたという手紙を書くのですが、いま福建に手紙を送るのは、どの便がいちばん早いかと探し、琉球の船がいちばん早いので、それに託してその手紙を出したのです。ところが琉球信託局というのは、歴史に出てこない。福建の福州に琉球館があって、そこでやっていた資料があるんですが、広東まで行っているということは歴史にはあまり出ていないことです。琉球の人たちはえらいなと、この時、思いました。
中国では第8代皇帝道光帝の治世(在位は1821~50)の前代あたりから国勢は衰退期に入り、絶対的な君主独裁制のもと内政は行き詰まっていた。
同じ頃、イギリスでは産業革命が進み、生産力が飛躍的に拡大して、その目は世界の市場に向けられた。東アジアではインドの植民地化を進め、運営資金を現地で調達する必要から、インド産の阿片を中国に売り込み、大きな利益を上げた。そして東インド会社の対中国貿易独占権が廃止されると、英国商人は大量に中国に阿片を持ち込み、銀の流出に困った清朝は、阿片の販売・吸飲を禁止する。
イギリス議会は武力によってこれに対抗することを決め、遠征軍を派遣して圧倒的な武力で清朝軍を圧倒し続け、ついに清朝は屈伏した。
ちなみに阿片戦争が起こったとき、日本では天保の大改革に着手し、幕府権力の強化を図ろうとしていたが、そうした時期にこの事件が起こり、西洋列強の圧倒的な軍事力を知って徳川幕府は大きな衝撃を受けた。
「遠い所へ行ってもらうつもりじゃ」
と、大石は言った。
「どこへなりとも悦(よろこ)んで参ります」
陶羽は覚悟してきたのである。
「延禧(えんき)のために苦労をかけるよ、まったく。もうすこしましなのが上にいたら、と悔まれてならん。いまここでいくら言っても仕方のないことじゃがな」
と、大石は言った。
陶羽はすこし肩をすぼめた。ふだんなら聞き捨てできないことである。延禧とは大遼国のいまの皇帝の名である。あろうことか、大石はそれを呼びすてにしたのだ。
陶羽はうなずくことも、首を横に振ることもできない。黙っているほかなかった。
「いいか、我が大遼国はもう亡びたのとおなじだ。もはや挽回(ばんかい)の望みはない。だが、将来に希望を託すことはできる。そのためには、この地をしばらく離れなければならん。おそらくこの一、二年のうちにな。……西へのがれ、捲土重来(けんどちょうらい)するのだ。幸い西方には我々の兄弟部族がいる。この地へ攻めこむのではなく、道を借りるだけじゃ。そう説けば戦いはおこらんじゃろ」
大石はそこまで言って、陶羽の顔をじっとみつめた。おれはここまで言ったから、あとはおまえがしゃべれと言っているようだった。
「私に説得の使者に立てとおしゃるのでございますか?」
陶羽はそうたずねた。
大石はその質問を待っていたようである。
「その使者はもう出してある。そなたにはもうすこし遠くへ行ってもらいたいのだ」
と、青年皇族は言った。
落目になったとはいえ、キタン王朝の有力者である。キタンはモンゴル系の部族であり、通過するだけなら、ことばも風俗もそのあたりの部族とほぼおなじで問題はない。大石は逃亡しながら、勢力をふやそうと思っている。無事に通るだけではなく、相手を吸収したい。その説得の使者はすでに出してあるという。
「大食(タージ)でございますか?」
陶羽がそう言うと、大石はうなずいた。
-『桃源郷』(2001年 集英社)より
12世紀始め、大国「金」と「宋」の勢いにおされ、末期的症状にあった「遼」の皇族耶律大石は、西に新天地を求めるため、18歳のうら若き青年、陶羽を大食(アラブ)に遣わせた。旅立ちが決まった時、陶羽は父親に一家に伝わる秘密を告げられる。それは一家が陶淵明の『桃花源記』に描かれた理想郷「桃源郷」から下界に遣わされた探界使の末裔であるという秘密であった。そして旅の案内役として耶律大石より送られてきた人物、白岳中もその「末裔」であることがわかる。探界使が派遣されたのはちょうど千年ほど前、その後桃源郷へ行った人の話もなく、面妖(めんよう)だといぶかしがりながらもはるか西方の国々の情勢を探るため二人は旅を続ける。陶羽はイスファハーンの街を散策中に、イスラム教シーア派の巣窟として知られるアラムート(鷲の巣城)へ誘拐され、長老ハサン・サッバーフに出会う。そして喫菜事魔(きっさいじま)と呼ばれたマニ教の姿が次第に明らかにされてゆく……。
ウマル・ハイヤームの四行詩(ルバイー)をちりばめながら耶律大石西遷などの史実を背景に展開する陶羽の旅は、燕京から開封、そして泉州、カリカットを経由しホルムズ、バクダート、アレクサンドリアそしてイベリア半島へと続きユーラシア大陸全土を巡る。陶羽はその〈西遷〉と〈東帰〉の旅の中で民族、国籍、宗教の入り乱れた多くの人々と出会い、「桃源郷」伝説に隠された秘密を悟ってゆく。大石が陶羽に命じた内偵の旅の意味、そして真の理想郷とは--。歴史に精通した作者が、史実と空想を織り交ぜ、争いのない理想郷の実現をテーマに描き出す稀有壮大な大冒険ロマン。
陶淵明が著した『桃花源記』という本があります。中国ではそれまでリアリズムな物語しか認められていなかったのですが、幻想的、空想的な内容が書かれたこの本以後、中国文学でもユートピア物語が生まれたように思います。私もそれにならって、一つの理想郷を著したいと思いました。ただし舞台はずっと西で、ペルシャからスペインあたりまで広がった世界です。
契丹族がつくった遼国がありましたが、それが滅ぼされて一族がヨーロッパの近くまで逃げていったという歴史的事実があります。『桃源郷』はこうした背景のもと、マニ教を登場させています。マニ教徒の主人公がイベリア半島まで逃げ、そこでも隠れたマニ教徒がいることを知ります。そして宗教の名前など何でもいいが、真実を伝えることが大事なことだ、と言わしています。
これは、こういう考え方をする人がいたのではと想像して書いたことです。いまの世界では実現できないことかもしれませんが、宗教や主義といったもの以外につながるものを求めなければ、人類は救われないのではないでしょうか。
混濁しかける意識のなかで、諸葛孔明はもう一人の自分と問答をはじめた。……
---お前が玄徳(劉備)についたのは、曹操に天下を取らせたくないためであったのだろう。天下三分の計というが、徐州の庶民を、草を刈るように殺した曹操が憎かったからではないか?
---そのとおりだが、それだけではない。人間の心には、幾筋もの糸がぶらさがっている。曹操憎しもその一本だ。
---曹操が死んだあと、おまえにはもう仮想の敵はいなくなったのではないか。なにをそんなに心を労したのか?
---そんなに強くなかった糸が、心のなかで太くなった。そのために死力を尽くした。
---それで報われたのか?
---効果のことか?それならあった。天下三分の計。……蜀漢を強盛ならしめ、魏や東呉を併せて、天下を統一するのは、私の素志ではない。天下統一は万民の不幸になるかもしれない。
---なぜだ?
---秦の始皇帝の下で、天下万民はしあわせであったか?
---始皇帝はとくべつだ。例外ではないか。
---そうではない。曹操が第二の始皇帝になったかもしれない。
---では、天下三分を長くつづかせるのか?
---私は浮屠の徒のように、永劫(えいごう)のことは考えない。まず百年ほどのことしか、念頭にない。百年、天下、三分されておればよい。そのためには、魏の力を弱めなければならないのだ。
---天下三分は、天下に戦乱が絶えないことではないか?
---三者は相争うだろうが、それは戦争だけではない。人びとをしあわせにする競争もおこなわれる。富強の競争、人心を得る競争、学問の競争。……それに負けまいと競い合う時代……それがつづくのが人びとのしあわせだとおもった。
---悔いはないか?
---それはない。……ま、いちど司馬仲達と話し合いたかった。彼も魏の強盛を望まないだろう。十万の蜀漢軍を、彼は無傷で蜀に返したいはずだ。蜀漢がほろびて、魏帝が強くなれば、大将軍司馬仲達が危うい。……追撃 滅の勅命を、彼は守らないだろう。守らない口実を彼に与えなければならぬ。……
「なにか……おっしゃいましたか?」
孔明の唇が、かすかにうごくのをみて、楊儀は耳をよせて、そう訊いた。
「簾(すだれ)を……」
孔明はわずかに顎をうごかした。
秋とはいえ、渭南(いなん)平原には、まだ残暑の気が消えていない。
簾をあげよ、ということであろう。---楊儀が小声でそう言うと、姜維が簾をしずかにひきあげた。部屋のなかがあかるくなった。諸葛孔明は、窓のほうに顔をむけるようなうごきをみせた。
「旗を、反(ひるがえ)せ。……鼓を、鳴らせ。……」
それが最期のことばであった。
赤い星が孔明の営に投じたというのは、その瞬間のことであろうか。臨終の場所は、五丈原の郭氏塢(かくしう)であった。
-『諸葛孔明』(1993年 中公文庫)より
日本の邪馬台国時代、中国では三国時代を迎え、魏、呉、蜀の三国が覇権を争っていた。諸葛孔明は蜀の劉備に三顧の礼をもって迎えられ軍師となり、魏の曹操、呉の孫権を相手に知恵と力を尽くして闘う中、病で亡くなる。その英雄・孔明の一生を描いた大作。孔明の少・青年期から詳細に描き出し、なぜ呉にも魏にもつかず、蜀についたかを再現する。「三国志演義」で広く知られる孔明について、文献に撤して調べ上げ、作家の想像力によって肉付けして、新しい孔明像が描き出された。吉川英治文学所受賞作。
『三国志』は中国の歴史として、日本でもよく知られている話です。それだけに誤解も多い。たとえば諸葛孔明は神様のように書かれていますが、実は神様ではない。一人の人間です。非常に優れた人ですが、三国志の正史には彼は戦争が下手だと記されています。負けてばかりいましたからね。一方、誠実な人であったと褒めています。私は彼が神様ではなかったということを書こうと思ったのです。
もう一つの理由は孔明の誠実さです。人民に対するあたたかい気持ちです。彼は法家といって法律を第一にする人です。何をしてもいいという戦乱の世の中で、命令に反して戦を起こした馬謖(ばしょく)を斬り捨てて責任をとらせました。「泣いて馬謖を斬る」という諺がありますが、本当に子供のようにかわいがっていた馬謖を法に基づき処分したのです。余談ですが馬謖の兄弟は五人いました。諸葛孔明は皆をかわいがっていました。優れた兄弟の中でも一番できたのが長兄で、眉毛が白かったのです。「白眉」という言葉も、この逸話から出ています。
中国の歴史では動乱の時代が長くありました。その中で平和になることを願った代表的な人物が孔明ではなかったかと思っています。
サラディンが十字軍に勝利をおさめつつあったころ、東方では群小氏族が統合しはじめていた。マリアがコンスタンティノープルに着いた翌年、一一八九年、二十一の氏族の代表は、二十八歳のテムジンを、可汗に推載したのである。
もうすでに、小集団では生きて行けない時代になっていた。
小集団連合の長は、あまり家柄が良すぎてはいけない。テムジンは、当時まだハーンの称号を持っていなかった。家格では彼よりも上位の者がすくなくない。それにもかかわらず、彼が代表者にえらばれたのは、不都合なことがあれば、すぐに罷免できるからであった。
しかし、テムジンは自己防衛に熱心であった。彼はハーン号を、このとき、「チンギス」としたのである。「チンギス」は、「強力」とか「海」「光」の意味がある。光の精霊として、人びとがその名を口にするのもおそれている。誰もがめったに口にしないその名を、ハーン号に採用したのはただごとではない。
ハーンの位は、もとはそれほど光りかがやくものではなかった。老人がやりたがらない、ただ働きの雑用役である。それを権威あるものにしたのは、彼であった。どの英雄豪傑もそうだが、彼も自分一人しか使えない称号を好んだ。チンギスという名は彼一人だけのものである。
人びとは相変わらずテムジンと呼んだが、テムジンはチンギス・ハーンと呼ばれることを好んだ。まだそれほど実力のなかった時代は、テムジンにも安じていたが、しだいにチンギス・ハーンが多くなった。
二十八歳まで、ただのテムジンであった彼は、敵には強く、味方にはやさしかった。誰もあまり就任したがらないとはいえ、ハーン位を彼が得たのは、人気があったからなのだ。その人気は彼の武器となった。
-陳舜臣中国ライブラリー『チンギス・ハーンの一族』(2000年 集英社)より 〈初刊本:『チンギス・ハーンの一族』1~4 朝日新聞社 1997年〉
1189年、モンゴルの21氏族の長(ハーン)に推挙されたテムジンは、自らをチンギス・ハーンと名乗る。彼は周辺の国々を武力によってまとめあげ、巨大なモンゴル帝国を築き上げた。
チンギスの死後、2代目ハーンとなったオゴディは、金国を滅ぼし、帝国をより強大なものにする。その一方、次第に激しさを増す後継者争い、チンギスの子孫同士の対立、モンゴル帝国内の民族の不和など、勢力拡大を続けるモンゴル帝国は、この巨大さゆえの悩みにも直面していく。
4代目ハーン、モンケの死後、実弟との激しいハーン位争奪戦を経て5代目ハーンとなったフビライは、南宋を滅ぼして南方の覇権を握り、元王朝を創始した。
しかし、二度の日本遠征失敗や、モンゴル王家の叛乱など、元王朝が抱える問題はフビライを悩ませ続ける。
フビライの死後、内紛で衰退した元王朝は1368年、明に北方へと追いやられ、歴史の表舞台から消えていった。
この作品では、遊牧民の社会や生活、考え方を描こうとしました。日本人は遊牧民の生活をあまり知りませんが、現代のような社会では、遊牧社会の精神はかなり重要になってきていると思います。知らない国へ行って生活する、そういう時代になってきていますから……。
私は遊牧民の生活様式や考え方について、ずいぶん以前から関心をもっていました。学生時代から西南アジア周辺に興味があり、インド学を学ぶ中でチンギス・ハーンのことが気になり、いつか作品に取り入れたいと思っていました。
当時、遊牧民の社会は、日本やそこで暮らす私たちにとって遠い世界のことでした。ところがだんだんと注目されてきて、日本の学界でも「遊牧の精神」ということが言われるようになりました。
チンギス・ハーンの事績は、考えられている以上に大きな意味をもっていると思います。彼らは野蛮な集団という見方をされていましたが、チンギス・ハーンの戦略は、降伏した者は生かし、抵抗した者、裏切った者を排除するのです。また彼らは、民族を超えて能力がある人を登用しました。総理大臣にあたる職にも、ペルシャ人などいわゆる西域の人を登用しています。
遊牧社会では国家や民族という意識が希薄です。そういう思考を私たちの社会も取り入れていけば、もっと世界は広がるのではないでしょうか。
二人は最も親しい同窓であり、こんなふうに紙筆を前にすると、昔を思い出すのであった。孫文は墨をすったあと、しばらく考えこんだ。
いま孫文は反清革命に全力を傾けているが、それが最終目標ではなかった。民族主義の革命の目標は、要するに民族のあいだの差別をとり除くことにあった。民族間の差別がなくなった先には、「大同」の世界が見えなければならないのである。
「大同」と書こうとしたが、これは説明がやや困難である。
実現は難しいが、めざさなければならないのは「大同」、すばわち「ユートピア」である。洪門に入るときの第一誓(せん)は、--尓(なんじ)の父母は即ち我が父母、尓の兄弟姉妹は即ち我が兄弟姉妹、尓の妻は即ち我が嫂(あによめ)、如(も)し誓に背(そむ)く有らば、五雷誅滅(ごらいちゅうめつ)せよ。
であり、鄭土良はとかくそれを口にせよ、と教えてくれ、孫文は実際にそれを唱えた。
(これは博愛ということだな)
孫文はそう思った。
いま彼は紙にむかって筆にたっぷり墨を含ませ、「博愛」の二字を書いた。
一気に書き上げた。一枚も書き潰(つぶ)しはしなかった。鐘工宇は数枚の予備の紙を用意していた。孫文はそれを見て、
「もう一枚書こう。……この墨はほんとうに書きやすい。それに紙もりっぱだな。宣紙(せんし)だろう。宣紙でも上等のほうだ」
新しくひろげられた宣紙に、孫文は言った。
安徽(あんき)省の宣州は造紙の中心地で、上質の紙を産し、宣紙といって世に珍重されている。墨もこのあたりでつくられたのは、徽墨(きぼく)といって上質なものが多い。
--天下為公
と書いた。天下は公(おおやけ)のものであって私(わたくし)すべきでないという意味である。めざす共和国ではとうぜんのことであった。それにつけても、共和革命がまだ成功していないことが残念であった。
-『青山一髪』(2003年 中央公論新社)より
副題に「孫文立つ(上巻)」「辛亥革命への道(下巻)」とあるとおり、清朝打倒を決意した孫文の一度目の蜂起失敗(1985年10月)から、武昌蜂起(1911年10月)の後、1912年1月1日、南京で中華民国臨時大統領に就任するまでの若き革命家の日々をつづった物語。
1895年10月なかば、台湾の南方の海面にうかぶ船(はやぶさ号)から物語は始まる。物語の主人公となる孫文(1866~1925年)は前年6月に北洋大臣李鴻章宛に法を改め、国を強くする八千字の進言書を出していたが、清国外交担当者である李鴻章は朝鮮をめぐり白熱化する外交戦の渦中にあり、進言書に対する反応はなかった。日本と清国の関係はますます悪化し、8月1日に日清戦争が開戦、1895年4月17日に下関で開かれた講和会議で、清国にとって屈辱的な条約が調印される。しかしかつて清国の富強策を進言していた孫文は、この時もはや清国の敗北を悲しむ気持ちはなく、清国の崩壊を望んでいた。はやぶさ号はこの下関条約により日本へ割譲された台湾から武器弾薬を仕入れる商売をしており、その品物(武器)の引き取り人は1985年10月26日(陰暦の9月9日)、広州での重陽蜂起を企てていた孫文であった。
この広州での最初の武装蜂起は失敗に終わり、孫文は盟友を失う。自らも反逆者として懸賞金をかけられ、故国を追われた孫文は日本、ハワイ、アメリカ、イギリスと亡命の旅を続ける。彼は亡命地香港や日本からも清国の要求で追放され、安住の地を失いながらも、革命運動の炎を燃やし続ける。
戊戌の政変(1988年)、義和団事件(1900年)など衰退する王朝の姿を露呈していく清朝政府と、光緒帝の忠臣をもって任ずる康有為に代表される変法派の保皇会との確執を背景しながら、孫文は多くの人々との出会いに支えられ、悲運にも不屈の精神で立ち向かい、「大同社会」の実現をめざした。日本でも政府は清国との繋がりを優先させたが、多くの民間人が孫文の支援者となった。1905年には東京赤坂に、各省留学生と華僑約70人が集い「中国同盟会」を設立する。ここには興中会、華興会、浙江系の光復会、湖北科学補修所の人たちが集まった。中国の若者たちからこの会の名を「対満同盟会」とする案が出されたが、孫文は革命は排満だけでなく、あらゆる専制を排斥しようとするのだという理由から反対した。彼は狭い民族主義はいずれ排斥されるものと考えていたのである。
こうして孫文は保皇会との拮抗をも問題とせず、掲げる理念にまっすぐに進み、各地の秘密結社を革命のもとに結集していく。革命派の蜂起は何度も失敗を重ねたが、幾度となく上がった烽火は次第に連なっていき、ついに革命の嵐は中国本土を覆うことになる……。
中国の歴史小説というと、三国志から前の時代が多いですね。しかし私たちにとっては、自分たちの血とつながっている、二、三代前の先祖の話のほうが近いはずです。
日清戦争は私の生まれただいぶ前の出来事ですけれど、私は孫文と一年だけ同じ世界の空気を吸っています。孫文は1925年に亡くなっていますが、私は1924年の2月に神戸で生まれました。その年に孫文が最後の旅行で神戸に来ています。そのとき、神戸の県立女学校を会場にして大アジア主義という講演を行っています。その最後の講演は、日本人に対する遺言です。日本は西洋列国の走狗となって、われわれと戦争するのか、それとも虐げられた人々の側にたって、彼らに対抗するのか、その二つの道がある。日本はどちらを選ぶのか、と……。
最晩年の孫文と私は同じ空気を吸っています。そういう時代を書きたかったのです。自分とは、そんなに遠い昔ではない話を。
これからも近代を書きたいと思います。しかし近代を描くとなると、関係者が生きている場合もあります。だからなるべく架空の人物に託して書くことになるでしょうね。
足を踏みいれると同時に、私は息をのみました。二年ぶりの石窟寺ですが、独特の雰囲気が、記憶によみがえってきました。二年前、はじめて石窟へはいって、胸をしめつけられるような、名状しがたい感動をおぼえたものです。そこには歴史が封じ込められています。そして、その歴史がにおうのです。
…………………
日本で弥勒といえば、たいていの人は中宮寺や広隆寺の半跏思惟(はんかしい)のスタイルを思いおこすでしょう。片脚を膝にあげて、片手を頬にあてて考えごとをしているすがたです。半跏思惟像は中国にも数多いのですが、それは弥勒さんではありません。弥勒さんなら兜率(とそつ)天で衆生を摂化し、将来、成仏して釈迦のあとをつぐことがきまっているのですから、なにも考えこむ必要はありません。「考える人」のスタイルで、あれこれと思い悩んでいるのは、悟りをひらく前のお釈迦さん、すなわち老病生死の苦に煩悩するシッダールタ太子です。したがって、中国の半跏思惟像は、たいてい太子思惟像であります。日本で弥勒さんを半跏思惟スタイルでつくったのは、おそらく朝鮮から伝わった作法ではないでしょうか。
この第二七五窟は、本尊のほか交脚像が四体ありました。
「古さのわりに保存が良好で、色彩もあざやかです。光背の絵は後代の補修です」
そんな説明をききながら、私はじっと交脚弥勒をみつめました。
衣裳(いしょう)はうすく、ぜんたいにしなやかなかんじですが、体格がどっしりしています。女性的ではありますが、健康でおちついた女性といった趣きがあります。手のひらが、グローブをつけたように大きく、そのため、包容力をかんじさせます。
これは人の好みによるでしょうが、未来仏として衆生を済度する弥勒は、このように、おおらかな、こだわりのないすがたがよいと、私には思えるのです。こちらが救ってもらおうと思っているのに、相手がなにか考えごとをしているようでは、あまり頼みがいがないではありませんか。
-『敦煌の旅』(1995年 読売新聞社)より
〈初刊本:『敦煌の旅』 1976年 平凡社〉
『敦煌の旅』は1975年に行った旅の記録ですが、敦煌はまだ外国人に開放されていない地域でした。今から思えば、観光地になるかどうかをテストする意味もあって、私に許可が出されたのでしょう。あまり自由に行動できませんでしたが、そこに行くこと自体が貴重な体験で感激しました。私が訪れる何年も前にも日本人が行っていますが、その間に中国では文革が起こり、敦煌はつぶれてしまったという噂もありました。それだけに現地には研究所があり、研究が続けられていることを写真を交えて紹介したのです。
敦煌は西域と中国の交流点で、時代によって西域の影響の強い時代があり、それから西域の文化を咀嚼した中国的なもの加わり変化してきています。敦煌には、少ないながらも初期の西域の文化が残っており、私はかつての文化交流の姿を想像しました。
ジープのうしろの座席では、進行方向にむかって左側に私が坐り、右側に息子が坐り、まんなかに妻をはさんでいました。左右の両端に坐れば、車が揺れるようなとき、そばに掴むものがありますが、中央にいる妻はそれがなく、自分のからだでバランスをとらねばならず、そのためずいぶん疲れたということでした。
「ああ、きれいだ。……」
と、息子が呟きました。進行方向にむかって右側というのは、窓がほぼ南に面しているのです。そこからカラコルムの山なみが見えました。しかも、夜明けです。銀白の嶺は、暁の色に染められていました。ピンクです。銀嶺は日本アルプスでよく見ましたし、写真でもなじみの景色です。しかし、ピンクの山には胸をうたれました。朝焼け富士の美しさをきいたことがありますが、こうした景色のすばらしさは、所詮、じっさいに見て、心をうたれた人でなければわからないでしょう。
「あれはムスタグアタかな、それともコングルかな。……」
私は若いころから、あこがれのあまり、なんども地図を眺めて、その名が頭に焼きついてしまった山の名を思い出しました。もしムスタグアタ山であるとすれば、七、五四六メートルですし、コングル山なら七、七一九メートルです。エンギシャハルのあたりから見える高山といえば、この二つの巨峰のいずれかにちがいありません。よく見ると、さらに西のほうにも白い嶺が見えるのです。---だんだんと自信がなくなってきました。
銀嶺に映っていたピンクが、しだいに薄れて行きます。このシルクロードの本通りにも、ようやく人影がふえて来ました。ただ人影というのは正確ではありません。人間がひとりトボトボと歩いているシーンは、きわめてすくないのです。ロバにのっているか、駱駝をひいているか、馬車を走らせているか--とにかく人間はたいてい動物といっしょにいるのでした。
-『シルクロードの旅』(1995年 読売新聞社)より 〈初刊本:『シルクロードの旅』 1977年 平凡社〉
1977年、カシュガルやホータン地方を訪れた紀行です。ウルムチからカシュガルまで小型機で行き、ジープでホータンへ向かいました。実は景徳鎮(けいとくちん)を訪れるつもりで北京にいると、急に西域へ行けることになり、あわてて予定を変更した旅でした。
私たちからすれば、シルクロードという言葉よりも「天山」や「西域」といったほうが親しみがあります。しかし訪れた先の人々が「糸綢之路」(シルクロード)という言葉を強く意識していたことが印象に残り、書名も『シルクロードの旅』としました。
帰りの飛行機からは、私たちが走った陸路がよくわかりました。西のさいはてへの旅は、私の心を躍らせました。
玄奘がインドから持ち帰った経文をおさめるため、大慈恩寺に塔が建てられた。七層六十四メートルの甎(せん)(煉瓦れんが)造の巨塔は現在も西安郊外にのこっている。それは大雁塔と呼ばれ、永徽(えいき)三年(六五二)の建立である。
現在の大慈恩寺境内の建物は、この大雁塔を除いて、後代に改建されたものだ。大雄宝殿(本堂)の仏像、羅漢像も、すべて清代につくられたという。
本堂の両脇(りょうわき)の本棚(ほんだな)に、日本から贈られた大正新修大蔵経がずらりと並んでいる。
私は二度西安を訪れたが、二度とも大慈恩寺に足をはこんだ。
この寺の大雁塔の前に立つと、そよ吹く風さえ西域やインドとつながっているような気がする。いや、道昭、智通、智達など、この寺で玄奘の教えをうけた日本僧もいる。風は日本へも吹いて行く。--万水千山を越えて。
-『新西遊記』下巻 「万水千山を越えて」(1980年・読売新聞社)より
日本でもなじみの深い「西遊記」。その物語の舞台となる西安からトルファンまでの道を辿りながら、ユーモアあふれる小説風に著した異色の紀行記。玄奘三蔵への畏敬の念、歴史と仏教への造詣が随所に綴られる。
敦煌の旅の前、1973年に私はトルファンまで行っています。その時は北京から3日間かけて汽車で行きました。中日友好協会会長の寥承志さんが知り合いで、その力添えがあったからできた旅でした。
トルファンは『西遊記』で重要な場所ですが、この『西遊記』をベースに、私自身の旅を記したものが『新西遊記』です。
玄奘三蔵は国の法律を犯して国の外へ出てインドまで行こうとします。
当時は唐が建国して10年たっていない頃で、国境を巡って隣の突厥と交渉していた時代でした。突厥は唐から何万人も自国へ連れていっていました。遊牧民族は農作業をしないので、そのため労働者を連れて行き、天候の具合で羊が何万頭と死んでしまう時に備えて畑仕事をさせたのです。
唐は国ができたので、自国の人民を返してくれと言いますが、突厥はその代わりに銀何万両と何万もの絹で問題を解決しました。その話し合いの場に玄奘三蔵が行こうとしたのですから、唐としても困るわけです。
隋から唐に移る時代で、人々は過酷な犠牲を強いられていました。そうした姿を見て、玄奘の心の中では、こうした人々を助けないといけないと考えたのではないかと思うのです。私は玄奘三蔵のことを何回も書きました。どんなに苦労して経典を求めて行ったか、彼を突き動かしたものは何であったかということを、皆さんに知ってほしいからです。
※単行本
私が宮古島に最初に興味を持ったきっかけは、柳田国男先生の「海上の道」だった。ここはタカラガイの一大産地で、三千年ぐらい前、中国の●●が貨幣としていたタカラガイを獲りに宮古へやってきていたという壮大な仮設だ。ーインタビューより


私がこの宮古に興味を持ったというのは、柳田国男先生の「海上の道」からだ。3千年ぐらい前の中国の殷の時代、タカラガイが貨幣で、この貝が良くとれるのはここ宮古島だった。柳田先生は、殷人はここへ来て貝をとって本土に送ったと想像して仮説をたてている。(インタビューより)

宮古島が歴史に登場するのは1500年の八重山のオケヤアカハチの乱の頃からだ。仲宗根豊見親は琉球王府軍の先鋒をつとめ、その後、宮古、八重山を支配下に納めた。戦勝凱旋記念に築いた漲水御嶽の石垣や父のために建てた仲宗根豊見親の墓などが今も残る。(インタビューより)

オトーリは宮古島独特のもので、人が集まると“口上”と称して、今日はなぜ飲むのかということを順番に述べてから泡盛を回し飲みしていくものだ。このような文化が育まれたのは、この島にハブがいないからだと私は思っている。(インタビューより)

宮古には島最高の拝所である漲水御嶽をはじめ約900もの御嶽がある。(インタビューより)

ここの人たちの体の中にリズムが入っている。音楽が鳴り出すと自然に肩から先にいくような感じで自然に踊りに入っていく。おそらく、私の体の中にもかすかにそのリズムの記憶がわずかに残っていて楽しいのかも知れない。(インタビューより)

宮古の海はエメラルド色で本当に美しい。沖縄でも有数の美しさを保つ理由はこの島には川がないためといわれている。(インタビューより)

宮古上布は芋麻(ちょま)を原料とする麻織物で16世紀頃から織られ、宮古島唯一の物産だった。薩摩が琉球王国を侵略してから宮古の人々は重い人頭税として課せられるようになった。(インタビューより)

1771年にこのあたりを襲った「明和の大津波」で宮古島は壊滅的な被害を受けた。
その生き証人として、今も海や陸に巨石が残っている。(インタビューより)

サツマイモを中国から伝えたのは野国総官だといわれているが、宮古にはそれ以前に久松の漁師によって種芋が持ち込まれたという伝説がある。このイモが島の人々の飢えを救った。(インタビューより)

柳田先生の「海上の道」に賛成する人が少ないのは、その仮説に証拠がないからだ。何かそれを証明するものはすべて台風で飛ばされた。また、反対する証拠も同じく台風で残っていない。だから、私はこの仮説には賛同している。(インタビューより)

重かった税を象徴するもので、この石より背の低い者は子供だから課税されないが、約140㎝あるこの石より高い者は課税されたと伝わっている。人頭税は1637年から1903年まで続いた。(インタビューより)

ここの人たちはもてなしの心を持ち本当にやさしい。そして、我々は万国の渡し橋になるんだというグローバルな発想。そこが私を惹きつける。また、宮古島は台湾的な生活をしてきた私とよく似た気風を持っている。

はい。私がこの宮古に興味を持ったというのは、柳田国男先生の「海上の道」からです。大変大胆な仮説で、今ではあまり賛成者はいないですけれど…。
戦後まもなくの、ちょうどタブーがはずれて自由に仮説も立てられるようなそういう空気の中で、柳田先生の「海上の道」が出たんです。
それは、3千年ぐらい前の中国の殷の時代、殷の国の貨幣は貝で、タカラガイというその綺麗な貝が良くとれるのはここ宮古島なんです。沖縄でも少しとれますけれど、大きくとれるのはここで、貨幣ですから、殷の財産がここにあるわけです。
だから、殷の人はここへ来て、貝をとって本土に送っただろうと想像しているんですね。というのは、殷の遺跡からタカラガイが随分出るんですよ。それで、ここに来たんじゃないかというね…私は、この説に初めから賛成で今でも賛成なんです。…
記録ではだいたい13世紀くらいが一番遡れる上限なんですが、その前から人はいたと僕はそう思うんですよ。
記録にはないんですが、住んでいた形跡が台風に飛ばされただけで、その以前から人は住んでいたと私は思います。…
例えば、鑑真さんが来る時に台風に遭ってここで避難しているんですよ。そこの人たちに助けてもらったっていうのね。…
それに、時代は遡りますが、殷の時代に造り出され貨幣がね、沖縄に一つあるんですよ。それ持ってきた人が大陸から来た人に違いないんです。…
ここは、中国も近いし、南方とも北方ともつながっている一つの中心だと思うんですよ。もちろんその中心とは偉そうな意味でなくってね。
それは、沖縄が本土復帰してまもなくで、復帰の年に2回来ているんですよ。1回は随筆書くために石垣島に来ました。それから、文春の講演旅行でも来ました。それからは数え切れないぐらい来てますね。
ここへは何かが呼ぶんですよね。行きたいなと思うと何か用事ができるんですね。沖縄というと断らずに来たんですよ。
宮古は歴史から見るとちょっと悲しい歴史ですね。あまり物産がない土地で、非常に苦心して生きてきたんです。そんな時に1600年代の初めに琉球は薩摩藩に支配されるんですよ。薩摩藩が何も物産がないところなのになぜ狙ったかというと、琉球は中国と貿易をやっていたからで、その貿易の利益をとっていくんですね。ここは、中継貿易でかろうじてしのいでいた所なんですね。…
昨日、民謡を見ましたが、あれは体の中にリズムが入っていると思うんですよ…沖縄の人たちは音楽鳴り出すと自然に肩から先にいくみたいな感じですね。それでだんだんと踊るんですね。非常に自然ですね。私たちの体の中にもそういうリズムがあったはずなんですが、そのリズムを忘れたんですよ。ここの人たちはそのリズム覚えているから、リズムがあるんですよ。だけど、私たちがかすかに覚えている記憶で楽しいんです。私はそう思いますね。
宮古にはオトーリがあります。オトーリは宮古独特のもので、みんなが集まって…5、6人集まると、今日はなぜ飲むのかという理由を1人ずつ言うんです。口の上と書いてね、口上を言うんです。今日は孫が生まれて嬉しいとかね。その次の人は、昨日はお腹が痛かったのが治ったのが嬉しいとかね。みんな飲む理由を言ってね、オトーリ、乾杯するんです。
宮古にはハブがいないんですよ。沖縄の他の所はハブがいるでしょ。だからオトーリをしていい調子になって寝ころんだりすると、ハブに咬まれるからそんなにごろっと寝ころんだりしない。この宮古ではできるんですよ。ハブがいないんですから。おそらくそれが大きな原因だと思いますね。
八重山はハブがいるんですよね。だからわりと用心深いんですよね。宮古の人みたいにばーっとやらないんです。…
八重山は中国と非常に関係が深かったと思うんですよね。これは明治維新の前の頃に、アメリカが中国から苦力(クーリー)っていって奴隷と同じような労働者を連れてきてアメリカで働かせるんです。…
その苦力を乗せた船から苦力が脱走して石垣島に上陸したんですよ。百人ぐらい…ここに上がって。
幕末ですから、外国人とは付き合ってはいけない時代ですが、島の人たちは親切に食物をあげるんですよ。
幕末の頃、だんだんとこの辺にもたくさん外国船が来まして、でも外国船は打ち払えと幕府の命令が来ているんです。ところが沖縄の王朝から命令があり、外国船がきたら親切にしろと…もしもそれを薩摩の役人に見つかったら、薩摩の役人にお金をあげて、口を封じなさい、とそういう記録が残っているんですよ。沖縄の人たちは優しいんですね。あの頃に沖縄に立ち寄った人たちは「こんなにいい人たちはいない。」とほめているんです。
ここの人たちは、はじめから世界人だったんです。みんなと仲良くするんですね。…
そういうことが私を惹きつけるんです。国境がないことですよね。…だからここには万国の匂いがすると。それがいいんですね。これを失わずにやってほしいと思いますね。
それはね、時代によっていろいろ違いますけどもね。沖縄本島から搾取もされるんですよ。人頭税も取られましてね、宮古には石が建っていましてね、この石より背の低い者は子供だから構わないけど、それより高い者は税を取られる。ひどい搾取ですよ…それから、宮古島唯一の物産という宮古上布を何反納めないといけないというそういうひどい搾取がありました。だから、本島はまた薩摩に吸い上げられ、玉突き現象なんですね。
基本的には、ここには国境を超えた何かがあるんですよ。海上の道の時代、ここには何か人が流れる渦があって、その渦の中にいたんですね。その渦のできた時代にここに来た人は、台風に流されたりして…いろんなことで流されてきたんです。
その渦を、記憶を思い起こして昔を思い出すと、世界に国境なんかあるのは不自然だと…自然とみんなここに寄ってきたんだという気持ちを起こさせます。
そういう忘れた記憶を取り戻して世界の平和のためにやってほしいですね。それが本当なんですけどね、人間というのはね。何人(なにじん)でもないんですよ。世界人ですよね。地球人ですね。
ええ、そうなんです。ただ、テレビの『琉球の風』と原作の私の『琉球の風』とは違いますが、私の書いた原作はそうです。そういう世界人としての視野からものを見るということをね…伝わったかどうかはわかりませんけど、それを狙って書いたんです。
作品の中のいろんな歴史的なものは間違いないです。ただ出てくる人物は、架空の人物はありますしね。小説ですからね。…
とにかく、私は国境というものは、いずれなくなるという気持ちでいますからね。そこに引き寄せるように努力したいと思って作品を書いたんです。
九州には作品を書くための取材や家族旅行でよく訪れた。ここはアジア、中国と密接に繋がり、多くの海商たちが活躍した舞台だ。
ーインタビューより

私の作品で海ということになると長崎や平戸が登場してくる。はじめに平戸に外国商館があって後に長崎に移った。当時の正式な貿易点は大陸に近いこの地だった。
長崎に出島もなかった頃は日本人と外国人が雑居していた時代が随分長かった。小説にもとりあげたが、その時代は隣組として付き合っていてとても面白い。(インタビューより)

平戸にはオランダ人や中国人、日本人が混在して住んでいた。そういう環境のなか、半分武士で半分海賊である松浦氏と、半分商人で半分海賊の鄭芝龍など中国系の商人が、似たもの同士で結びつき、海商達が活躍をした。(インタビューより)

海商たちは、刀を振り回すような海賊ではなく、明の宮廷にお金を貰って物を買う半ば役人のようなものだった。(インタビューより)

鄭成功は、父、鄭芝龍が日本人の女性と結ばれ、ここ平戸で生まれた。平戸と中国との関係は歴史があり、ここには彼のような国際人が生まれる素地があった。十数年前、私は千里が浜など鄭成功のゆかりの地を作品の取材のためよく歩いた。この児誕石を含め鄭成功のいろんな史跡は後から出来たものが多い。(インタビューより)

子供の頃、鄭成功のことは親しみをこめて“シンコンペアー”(我々のおじさん)と呼んでいた。彼は混血児で日本的なものと中国的なものと両面を持っていたので内面にその葛藤があった。(インタビューより)

居宅跡には、鄭成功が植えたと言い伝えられているナギの木がたっている。観音堂にある媽祖像は、父、鄭芝龍が成功誕生の記念に奉納したと伝わっている。私は港を見ると船はどこに行くのか夢想する。鄭成功も子供の頃この海を見て、親から聞いた中国のことを夢想したことだろう。(インタビューより)

当時、権力者は江戸や大阪に住んでいたのでここまで目が届かなかったため、島津氏は鎖国のような状態にしていた。他の国の人は入れず、もし来ると江戸の隠密だと疑われ消されたりしていた。(インタビューより)

薩摩と琉球について作品「琉球の風」にも書いたが、すべての旨みは薩摩が持っていき琉球は薩摩に押さえられた。しかし、薩摩が琉球に入ってからの方が琉球は栄え、琉球は日本と大きく繋がった。琉球の組踊りなども薩摩と繋がってからのものだ。(インタビューより)

琉球は何年かに一回“江戸のぼり”と称して江戸へ行った。琉球人はその行列に加わる時、日本人の姿をすることは認められず“琉装”と定められていた。
(インタビューより)

望嶽楼は、19代島津光久の代に琉球国王から献上され、藩主が琉球使者と面接する際に使用していた。(インタビューより)

奈良時代、日本には戒律を与える律師がいなかったため、栄叡と普照は、律師を招くために渡唐した。要請された鑑真は、弟子に問いかけたが誰も希望しなかったので、日本は仏法有縁の土地だと鑑真自ら渡日することを決意した。日本への渡海を5度試みたが失敗。ようやく6度目にここ坊津へ上陸できた。(インタビューより)

当時、鑑真和上が日本にくるのにパスポートは必要なかった。これからの新しい時代はパスポートのいらない時代にしたい。そのために、昔、国境のない世界があったことを伝え、これからの時代をボーダーレスの時代にしたいという願いを私は持っている。
(インタビューより)

阿蘇に身を置くとちょっと大陸的な感じがして中国を感じる。ここのエネルギーが私に作品を書かせてくれそうだ。

友人の葉祥鼎(ようしょうてい)君がお兄さんの葉祥明(ようしょうめい)君の美術館を故郷熊本の阿蘇に作った。葉祥明君の絵の風景そのままのこの美術館では、絵だけでなく草原の散歩もでき、ゆったりとした気持ちになる。
葉祥明阿蘇高原絵本美術館



−九州というか、鹿児島にしろ長崎にしろ、そうやって昔から海に 開かれて大陸の方に向いていたというような所ですけど。今、それから今後ですね、どんな風になって行くと…。
陳舜臣それは今までの歴史を顧みて、非常に先人・先輩達が苦労して 二つの国を結び付けたということを知らないといけないですね。 この縁(えにし)というものが、非常に大切なものだということ を考えて、両国の関係をよくしていかないといけないんですよ。
−そのために果たすべき役割というのが、この九州にはありますか…?
陳舜臣私はあると思いますね。その歴史を持ってるのですから。こことの関係は古いです。私はこんな歳になったからちょっと無理かもしれないけれどね、余力があれば書きたいこともあります。


−これからの作品にこめたいメッセージというのはどういったことですか。
陳舜臣鑑真和上を連れてくるのに昔はパスポートがいらない。ですか ら、これからの新しい時代はパスポートのない時代にしたいんで すよね。それを実現するために昔のいろんな話をしてね、国境の ないボーダーレスの世界があったんだと。新しい時代もボーダー レスの時代にしたいということですね。


−ここ熊本の阿蘇、こんな風な大自然に身を置くというのは・・・。
陳舜臣私は九州が大好きでよく子どもを連れて九州に遊びに来たものです。今でも九州は大好きです。長崎とか鹿児島そしてこの熊本の阿蘇の麓・・・。ちょうど友人の葉祥鼎(ようしょうてい)君がお兄さんの葉祥明(ようしょうめい)君の美術館をこちらに作りまして・・・。ここは大変いい所で、ちょっと大陸的な感じで、中国を書くときにはここに身をおくと参考になるような気が致します。


葉祥明美術館
ここは、私の友人の葉祥鼎(ようしょうてい)君が手がけている、彼の兄、葉祥明(ようしょうめい)君の美術館だ。阿蘇山のふところにこの美術館はある。ここでは、大自然と絵が交差し、作品はもちろん、建物、そして自然そのものが葉祥明君の世界だ。少しみなさんに阿蘇の大自然と葉祥明君の世界を私と一緒に感じていただこう。


−鹿児島の話もちょっとお聞きしたいんですけども。ここもやっぱり、海商たちが登場します。
陳舜臣これはもう島津氏そのものがこういう所に住んでいて、権力者は江戸、秀吉の場合は大阪に住んでいる。ここは権力者の目が届かないですね。そして、ここは鎖国みたいにしているんですよ。直木賞の直木三十五が「南国太平記」という作品でそういうことを書いています。他国の人を入れないようにして、他国の人が来ると江戸からの隠密と思われてすぐに消されたりして…だから、隠密に入って来る人はお父さんが来て、そして子供生んで、その子供が隠密になるんですよ。その子は完全な鹿児島弁を使うからバレないというんでね。
−そんな鎖国をしていたけれども、やがて琉球との繋がりができてきて・・・。
陳舜臣琉球との繋がりは、私は「琉球の風」に書きましたけどね、薩摩と琉球は前から繋がっていたんですが、今度は直接薩摩が乗り出したということですね。表面的には琉球を使っていますけど、全部うまみは薩摩が持っていったということです。でも薩摩が琉球に入ってからの方が琉球は栄えたんです。薩摩に押さえられたけれど、薩摩のおかげで日本と繋がったんですよ、大きくね。


−中国からやって来たものもたくさんありますが、鑑真和上のことなんですけど・・・。
陳舜臣鑑真和上はさきほどの時代より大分前ですけどね・・・。実は「正式にお前を坊さんにする」という役割をする律師というのがあって、本当は律師が何人かいて戒律を与えなきゃいけないんですけども、その頃、まだ8世紀の頃ですけど、日本に律師はいないんですよ。みんな坊さんと称している人がいるだけで・・・。
それで、正式に律を授けるために人を呼んで来るんです。そのために何回も交渉したんだけれど


−まずは長崎の話から。長崎を舞台にした小説というのは結構多いと思うんですが・・・。
陳舜臣歴史小説で海ということになると、とにかく長崎が出てくるんですよ。長崎以外のもちろん港ありますけどね、外国との貿易の場合はたいてい長崎あるいは平戸ですね。初め平戸に外国商館があって、それが長崎に移ったんですけどね・・・。この2つが正式な貿易点です。他の貿易はあちこちで非合法的にやっています。兵庫でもありますね。
−長崎や平戸の何というか、気風と言いますか、そういうのはどういう風に・・・。
陳舜臣そうですね、平戸と言えばね、鄭成功(ていせいこう)の生まれた所です。生まれたということは、その前に父親が日本へ来て日本の女性と結婚して鄭成功が生まれたのですから、中国とはその前からずっと歴史があるわけです。そこで鄭成功とかいうような国際的な人物が生まれるんです・・・非常に有名になったのは鄭成功だけど、彼ほど有名にならない第二の鄭成功、第三の鄭成功というのはいたはずです。


−陳先生は、鄭成功(ていせいこう)や鄭芝竜(ていしりゅう)、また海商たちの話などをお書きですけども、そういうのに関心を持ったところはどういうところなんでしょう。
陳舜臣私は、日本と中国の関係と聞くとすぐに関心を持つんですけどね。この海商たちの本をはじめて読んだ時から関心を持ちましたし、子供の頃はよく鄭成功の話を親がしているんです。鄭成功のことは、子供のときから「シンコンペアー」といって、「我々のおじさん」と呼んでいたんです。
−あと、その海商達、他の海商達はどうなんでしょう・・・。
陳舜臣鄭成功(ていせいこう)のお父さんで鄭芝竜(ていしりゅう)がいるでしょ。それから鄭芝竜の親分が顔思斉(がんしさい)といいます。私の小説にも出てきますけどね・・・。その前にもいるんですよ。よくわからないけど毎回この辺に来てね、おかしな商売をしていて、時には正式の貿易商になるし、時には海賊まがいのこともするというような連中がこの辺にいるんです。
−陳先生ご自身はそういう海商たちとどこか似通った所があるなって思うところってありますか。
陳舜臣中国人で日本に住んでいるということは非常によく似た所ですけどね、その他はそんな・・・。海商にもなってみたいけれど、世界の海をまたにかけてやってみたいということを子供の頃は思いましたね。私は港のそばで育ったものですから「方々へ行きたいな」ということを考えました。港を見ると「この船はどこ行くんやろう」ということでね・・・。

兵庫県神戸市で生まれ、在住。兵庫県が舞台の作品に『神戸ものがたり』 『六甲山心中』『枯草の 根』等がある。 大正13年(1924) 神戸生まれ、第一神港商業学校(現・神戸市立神港高校)を経て、昭和18年 (1943)、大阪外国語大学インド語科に入学。1年後輩に司馬遼太郎がいた。卒業後、家業の貿易に 従事。昭和36年(1961)、『枯草の根』で第7回江戸川乱歩賞を機に作家生活に入る。昭和43年 『青玉獅子香炉』で直木賞、昭和45年『孔雀の道』で日本推理作家協会賞、昭和51年『敦煌の旅』 で大佛次郎賞など、受賞多数。平成5年(1993)にはNHK大河ドラマ『琉球の風』を手がける。中国 を舞台にした歴史小説作家というイメージが強いが、神戸を舞台にした現代小説や自伝的小説も多 い。神戸市在住。
|
|
|---|---|
|
|