展示構成
I. 文化の復興
II. 建築の原点
III. 未来を育てる
IV. 芸術の館
青りんご
青りんごまでの行き方

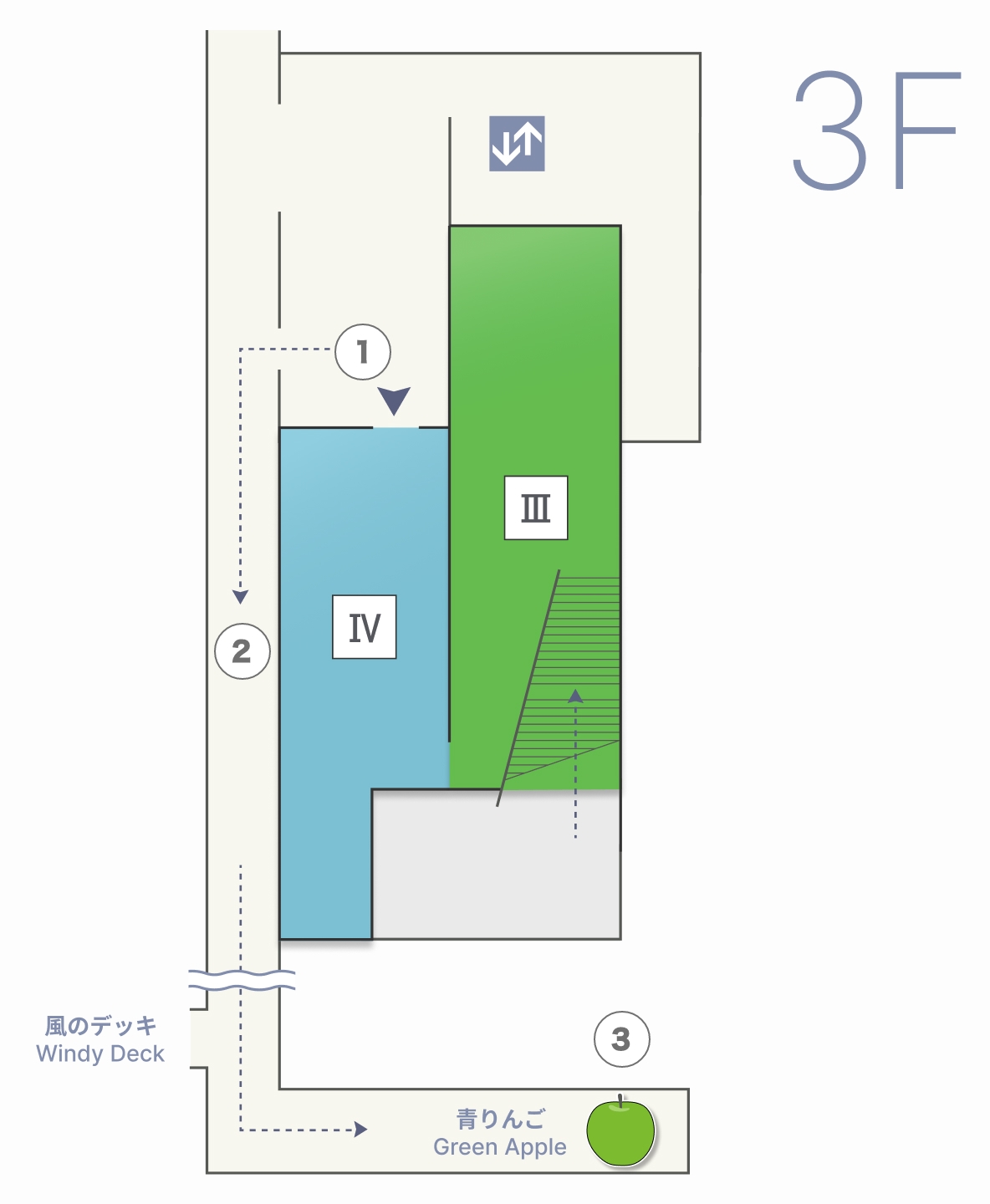

① Gallery 上階の出口から外に出て、左に曲がります。

② Ando Gallery を左手に見ながら、真っ直ぐ進みます。

③ 通路の先、左に見える海のデッキに「青りんご」があります。

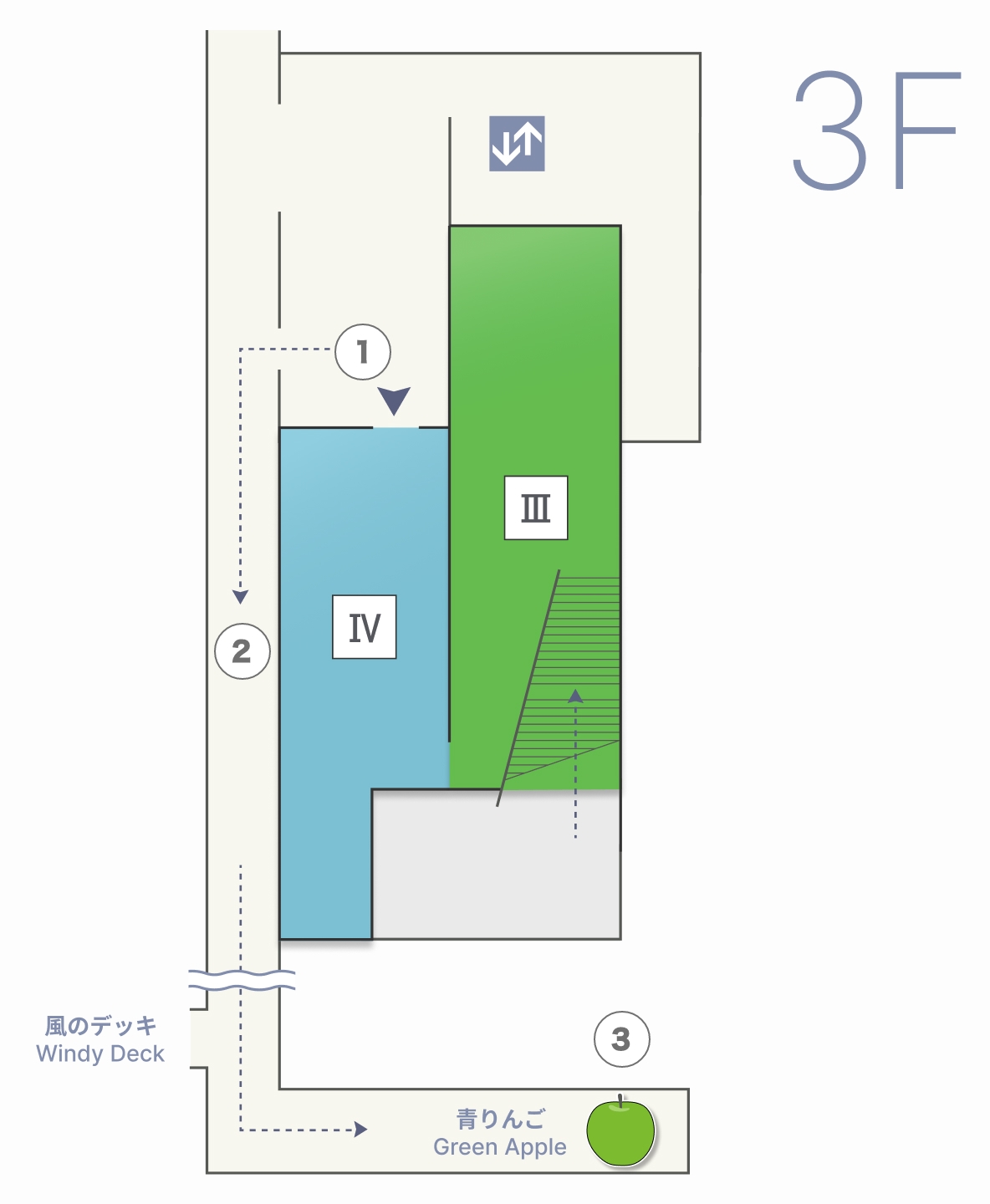

① Gallery 上階の出口から外に出て、左に曲がります。

② Ando Gallery を左手に見ながら、真っ直ぐ進みます。

③ 通路の先、左に見える海のデッキに「青りんご」があります。