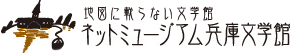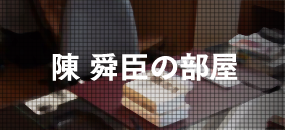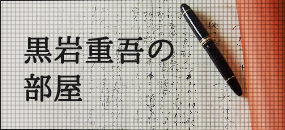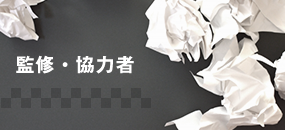けいちゅう契沖
-
寛永17~元禄14
-
ジャンル:
古典学者・歌人
- 出身:尼崎
PROFILE
【兵庫県との関係】
父の下川元全(もとたけ)は摂津国尼崎の青山大蔵少輔に250石で仕え、のち浪人した。契沖はその三男で尼崎に生まれた。兄、元氏(号、如水)は松平直矩に仕え、松平直矩が慶安2年(1649)姫路から越後村上へ転封になり、寛文7年(1667)再び姫路に戻るのに従った。契沖の母は、晩年、長子元氏のもとに居り、母を訪ねて姫路に下った折りの詠歌が契沖の歌集『漫吟集』に載る。
母がもとに、播磨の国へまかりて、帰らんとする時、ある人に詠みて遣しける、
天雲のけふは行くとも飾磨河(しかまがは)影見し水は今かへりこん
また、門人に摂津国武庫郡入江に住した野田忠粛がおり、契沖逝去の際、追悼の和歌「此の夕べおくる野原の煙さへはかなや雪のあはときえにき」を詠んだ。
【略歴】
慶安3年(1650)11歳で出家して大坂今里の妙法寺(現:大阪府東成区)のかい定(かいじょう)の弟子となり、13歳で剃髪して高野山に上る。23歳、大坂生玉の曼陀羅院の住職となる。その頃、下河辺長流を知り、古典研究を始めた。その後、寺を捨てて旅に出て長谷寺・室生寺・吉野・葛城等を遍歴した後、高野山に戻り、円通寺快円から菩薩戒を授けられた。その後延宝6年(1678)、かい定の求めに応じて妙法寺に戻り、かい定の没後、元禄3年(1690)、性寂如海に寺を譲って高津の円珠庵に移って古典研究に没頭。元禄3年(1690)に著した『万葉代匠記』を皮切りに、『正字類音集覧』、『和字正濫抄』など、古典研究の成果を続々と世に送った。契沖はこれまでの中世風の研究方法ではなく、実証を重んずる研究方法を樹立し、『万葉集』や仮名遣いの研究において見事な成果をあげた。その精神はその後、荷田春満、賀茂真淵、本居宣長に受け継がれ国学を生み出す基盤となった。
- 逝去地
- 大阪
- もっと詳しく知るために
-
契沖全集 久松潜一ほか 1976 昭和51年 岩波書店
契沖伝 久松潜一 1976 昭和51年 至文堂
代表作品
| 作品名 |
刊行年 |
和暦 |
備考 |
| 『自撰漫吟集』(『契沖和歌延宝集』とも呼ぶ。歌集) |
1681 |
|
収録:『契沖全集』岩波書店 |
| 万葉代匠記(注釈書) |
1690 |
|
収録:『契沖全集』岩波書店 |
| 古今余材抄』(注釈書) |
1691 |
|
収録:『契沖全集』岩波書店 |
| 『厚顔抄』(注釈書) |
1691 |
|
収録:『契沖全集』岩波書店 |
| 『勢語臆断』(注釈書) |
1692 |
|
収録:『契沖全集』岩波書店 |
| 『百人一首改観抄』(注釈書) |
1692 |
|
収録:『契沖全集』岩波書店 |
| 勝地吐懐編(名所研究) |
1692 |
|
収録:『契沖全集』岩波書店 |
| 『和字正濫抄』(語学書) |
1693 |
|
収録:『契沖全集』岩波書店 |
| 『河社』(歌学書) |
1695 |
|
収録:『契沖全集』岩波書店 |
| 『源註拾遺』(注釈書) |
1696 |
|
収録:『契沖全集』岩波書店 |
| 『漫吟集』(歌集) |
1787 |
|
収録:『契沖全集』岩波書店 |
| 『類題漫吟集』(歌集) |
1814 |
|
収録:『契沖全集』岩波書店 |
文学碑
Copyright © Net Museum Hyogo Bungakukan All Rights Reserved.