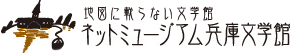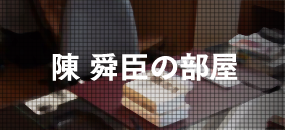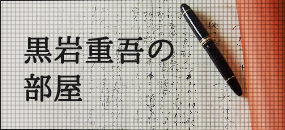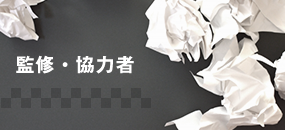ぶそん蕪村
-
享保元~天明3
-
ジャンル:
俳人・画家
- 出身:大坂
PROFILE
【兵庫県との関係】
はじめは、四十代のとき、京から讃岐に赴く際に通過した程度の関わりだった。ところが、俳諧宗匠となった五十代半ば以降に、灘・兵庫地方(神戸市)や但馬地方(出石町)に門人を持つようになってさらに関係が深くなった。とくに、弟子の大魯が大坂から兵庫の地に移り住んだあと、安永7年(1778)3月には、几董と見舞いの小旅行を果たし、同地の俳人と俳諧の座をともにした。3月12日まず脇浜・敏馬(みぬめ)を訪れ、14日兵庫来屯(きたむろ)亭、15日和田岬隣松院、16日に再度来屯亭、17日脇浜に戻り、18・19日は大石滞在、そして21日に帰洛した。
また、10点余り描いたとされる「奥の細道」の屏風・絵巻のうち2点は、灘の松岡士川と兵庫の北風来屯の依頼によったものである。
【略歴】
初号に宰町、別号に紫狐庵・落日庵・夜半亭・夜半翁など、画号に朝滄・謝長庚・謝春星・謝寅など多数を数える。本姓谷口氏、のち与謝氏。摂津国毛馬村(現・大阪市都島区毛馬)に生まれる。
20歳ころに江戸に赴き、師巴人から俳諧の手ほどきをうける。師の没後、雲水のようなかたちで、江戸および北関東を点々とする。その間奥州にも足を運ぶ。画業もこのころより始まる。36歳に上洛、さらに宮津や讃岐にも遊歴し、55歳の春、ようやく俳諧宗匠となる。これ以降は、小旅行を除いて、ほぼ京都に住み続け、俳諧・南画の両面ですぐれた作品を生み出していった。
ときは蕉風復興の時代であったが、その風潮に染まることなく、独自の俳諧活動を繰り広げ、多彩で想像力豊かな作品をのこし、芭蕉とは一味異なる俳諧の面を打ち出した。
また絵画においては、中国風の南画の技法に基づく文人画を旨とし、山水画や花鳥画に秀でていた。それのみならず、俳人である特徴を活かして、俳諧ものの草画(俳画)に飄逸味あふれる独特の画作を残した。
几董とわきのはまにあそびし時
――筋違(すぢかひ)にふとん敷たり宵の春――(『蕪村句集』)
- 逝去地
- 京都
- 兵庫県との関係
- 訪問
- もっと詳しく知るために
-
蕪村事典 松尾靖秋・他/編 1990 平成2年 おうふう
蕪村全集 尾形仂・他/編 1992? 平成4年? 講談社
蕪村書簡集 大谷篤蔵・他/編 1992 平成4年 岩波文庫
蕪村全句集 藤田真一・他/編 2000 平成12年 おうふう
蕪村 藤田真一 2000 平成12年 岩波新書
代表作品
| 作品名 |
刊行年 |
和暦 |
備考 |
| 此ほとり一夜四歌仙(連句集) |
1773 |
|
収録:『評釈此ほとり一夜四歌仙』 |
| 夜半楽(俳諧撰集) |
1777 |
|
収録:『蕪村全集 3』 |
| 蕪村句集(俳諧句集) |
1784 |
|
収録:岩波文庫 |
文学碑
| 場所 |
碑文 |
|
伊丹市伊丹5丁目3 有岡センター横
|
追啓 酒一樽いな河の小魚 右両品共に六月六日夕かた 京着いたし神事之間ニ 合忝存候。しかしいな河の魚ハ 腐れたゝれて臭気 甚しく一向やくニ立ず 四ツ辻へすてさせ申候。捨テニ 行者 鼻をふさき 貌を背け候て持出し、飛脚屋より 持参り候男も道 ゝくさきニ こまり候よし小言を申候。いか様炎熱時節 所詮京迄ハ持かたく候。向後暑中ニ河うをなと 御登セ被下候義 御無用ニ御座候。折角御親切にこゝろを 御つくし被成候もても用に立不申 其上駄賃の費 彼是以 無益之事に御座候。御存意之ほとハ甚かたじけなく候。右の義申進候事いかゝニ存候へ共 向後御心得のためニ御座候故 無遠慮申進候。以上 蕪村 六月十九日 東瓦様
牡丹切て気おとろひしゆふへ哉 |
|
神戸市須磨区一の谷町須磨浦公園
|
須磨の浦にて
春の海終日のたりのたりかな 蕪村 |
|
神戸市須磨区須磨寺町4須磨寺源平の庭
|
笛の音に波もよりくる須磨の秋 蕪村 |
|
神戸市灘区住吉神社
|
畑打の目に離れずよ摩耶ヶ嶽 |
|
神戸市灘区摩耶山町天上寺
|
菜の花や月は東に日は西に 蕪村 |
|
宝塚市中山寺2丁目中山寺梅林
|
やぶ入は中山寺のおとこかな 夜半翁 |
Copyright © Net Museum Hyogo Bungakukan All Rights Reserved.