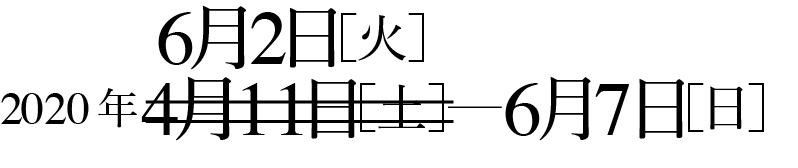I 時代をさかのぼって
調査・研究によって再評価された作品、新たに発見され作家の評価に再考を促した作品、めぐる時間の中で変らぬ魅力を発し続ける作品などを中心に展示し、明治中頃から明治末・大正初頭までの意外に幅広い作品を紹介します。

高橋由一《豆腐》1877年 油彩・キャンバス 金刀比羅宮蔵
由一の代表作は、やっぱり豆腐?
この絵のあとにも先にも、豆腐を描いた絵にはほとんどお目にかかりません。高橋由一(1828-1894)は、みんながよく知っている物や風景を絵に描いて毎月展覧会を開いていました。本物のように描ける油絵のスゴサを知ってもらいたかったからです。お焼き豆腐の焼き加減が激しすぎるようでもありますが、豆腐は今の私たちにも身近なので、その本物らしさは、花魁より新巻鮭(塩引き鮭)よりもよく分かるではありませんか!1877年に由一が奉納して以来「こんぴらさん」こと香川の金刀比羅宮にあり続けていることにも、感激。50年前の「開館記念 近代100年名作展」にも展示された名品です。
小山正太郎《濁醪療渇黄葉村店》1889年 油彩・キャンバス ポーラ美術館蔵
この絵で、正太郎、一発逆転!
「濁酒が渇きを癒してくれる、黄葉の村の小店」といった意味のタイトルがついています。教育者としてよく知られる小山正太郎(1857-1916)ですが、永らく絵の実力の程はよく分かっていませんでした。それどころか、政治好きで一徹な面が強調されすぎて、日本の近代美術史上でなんとなく「損な役回り」の人でした。しかし、近年出現したこの絵は彼への評価を一変させました。そうです!小山正太郎は自然へのロマンティックな憧憬をもち、それを表現しうる確かな技術を持った人だったのです。この絵がきっかけとなって、小山正太郎だけでなく、彼の周囲にいた画家たちが同じ頃に描いた作品の魅力もよりよく分かるようになってきた、そんな一発逆転のエピソードをもつ作品です。
和田三造《南風》1907年 油彩・キャンバス
東京国立近代美術館 重要文化財
でかした、三造、重要文化財だ!
兵庫県生野町(現朝来市)生まれの和田三造(1883-1967)が第1回文展に出品し、見事、最高賞を射止めた作品です。文展とは、文部省が主催してはじめた「官」の展覧会で、やはりそれなりの「権威」でした。三造、弱冠24歳、並みいる先輩画家をさしおいての受賞です。「人物の関係がよくわからん」「船と海がつながっていない」「風は本当に吹いているのか?」といろいろ言う人もいたのですが、大勢の見方は「小さな欠点はあるが、これでいい。いや、むしろこれがよい」という方向に落ち着いたようです。おりしも、1904年に開戦した日露戦争での勝利の直後とあれば、世間は右肩上がりのイケイケムード。そうした雰囲気を作品に重ね合わせる人もいたことでしょう。というわけで、今や、注目度アップの三造《南風》、見逃す手はありません!II 芸術と芸術家の時代
大正期を語る定番ともいえる個性派の作家の作品、1980年代以降の調査・研究によってその存在がはっきしりしてきた新興美術運動渦中の作品を展示し、あわせて新しい芸術家像のもとに、作家と作品の関係が整理されていく様をうかがいます。

柳瀬正夢《五月の朝と朝飯前の私》1923年 油彩・キャンバス
武蔵野美術大学 美術館・図書館蔵
ああ、青春の大正期新興美術運動
十代の頃から絵を描いて郷里松山や育った門司で有名だった柳瀬正夢(1900-1945)が24歳の時、東京で描いた絵。「マヴォ」という変わった名前のグループが1923年7月に開催した展覧会に出品されました。その1か月余り後、関東大震災に遭遇し、助けられるどころか逆に憲兵隊に逮捕された柳瀬は、これをきっかけに無産者階級の立場から制作することをはっきりと決意したので、この絵は「運動」に本腰を入れる前の最後の作品だとも、いやすでに運動に向っている作品だとも、いろいろ言われ、それに応じて画面に描かれたものがさまざまに解釈されています。もちろん、五月の朝が感じられ、始まりつつある運動に希望の予感を見ていた若い柳瀬の情熱がよくわかる、青春の一枚という側面もあります。ただ、1900年生まれで、東京大空襲で戦災死した作者にとっては、人生半ばを過ぎた時期の作品であり、没収等を恐れて柳瀬が自宅に巧みに収納、というか隠していたために現在の世に残った作品であることも忘れてはいけないでしょう。
佐伯祐三《リュクサンブール公園》1927年 油彩・キャンバス
田辺市立美術館蔵
ずっと、人気もの
30歳で死んだ佐伯祐三(1898-1928)の一生はとても短く、死ぬ間際の面妖な状況などを知ると悲劇的な画家と思ってしまいます。しかし、大阪の裕福な寺の息子として生まれ、東京美術学校卒業後も東京に住んで結婚し一家を構えてアトリエも建て、家族連れでパリに渡った、と聞くと、アレアレ?ずい分恵まれているな、とも感じます。これは、彼がまだ芸術家でない段階から、彼を芸術家として遇し、愛していた周囲があってこそのことでしょう。にもかかわらず、悲壮感と焦燥感のつきまとう1927年夏からの2度目のパリ生活での生活と制作は、私たちを芸術家とその人生への深淵な思いへと誘います。本作はこの2度目のパリ生活の前半に描かれました。木立の境目から見える高い空と一部見えている青さが、2度目のパリの佐伯の嬉しさを物語るようです。慎重、強靭な造形力も感じられ、没後すぐの発表当時から注目された作品のひとつです。旧蔵者も見巧者で佐伯の作中、画集収録の最も多い有名作でもあります。III 大衆と巨匠の時代
昭和期に入って美術の独立ジャンルとして認知され、かつ大衆的人気の的になった写真や版画を交えながら、やはり大衆に支持されることで明確に出現した巨匠・大家の作品を展示します。

安井曾太郎《座像》1929年 油彩・キャンバス 個人蔵
巨匠の精進に瞠目!
キレイな若い女の人が美しいキモノを着て行儀よく座っている。この絵を、そうした「ありがちな」絵の中の単なる一枚だと思ってはいけません。この絵には、自身の様式(絵の描き方、といった意味です)をすみずみまで貫こうとする画家の執念がつまっています。試しに、頭の中でこの絵を8~10㎝四方の碁盤の目に区画して、一区画ごとに順番に見ていけばよい。スゴイ集中力で隅から隅まで手を抜かず、描きに描いたことが分かるから。うーん、これ以上描けない、つまり終わるべきところで終わっている絵、ということでもあります。「そんな変な絵の見方をわざわざすることないではないか」というご意見はもっともですが、本作の数年前から始まる安井曾太郎(1888-1955)の様式確立へ向けた精進ぶりは、常識的な絵の見方ではとてもとらえきれません。
安井仲治《公園》1936年 ゼラチンシルバープリント・紙
アマチュアたちのラディカルな精進
昭和期に入ると、芸術の大衆化現象は、作り手の裾野の広がりとしてはっきりと現われます。学校で学ぶとか徒弟奉公するとかいう正式なルートで技術を学ぶことなく、自分の楽しみを目的に、いわば我流でモノゴトに進んでいく人が増えてきたのです。彼らは「アマチュア」と呼ばれ、時に揶揄の対象になったりもしますが、美術の分野では深淵かつ強靭な創作活動は、実はこのアマチュアリズムによって支えられてきました。彼らは表現を成り立たせている形式に果敢に踏みこんでいきます。例えば、安井仲治(1903-1942)は、浪華写真倶楽部、丹平写真倶楽部などでの活動を通じて「写真とは何か、写真が芸術であるということはどういうことか」を問うていました。熟達、完成、確立といった、精進の先にある実りを示す言葉から遠い果敢な挑戦として、今一度、彼らの作品を見るべきではないでしょうか。IV 美術館と歴史化の時代
戦後まもない頃から当館が開館した1970年までの作品を展示します。現在の美術を歴史的に解釈しようとする態度から、その逆説性や現在いっそうクリアになった同時代性のゆえに評価され、名品の位置にかけのぼった作品群です。

草間彌生《No.B White》1959年 油彩・キャンバス 千葉市美術館蔵
毀誉褒貶のはてに
作者の草間彌生(1929- )は、前衛美術家として平成28年度の文化勲章を受章しました。その際の赤いお河童頭と水玉模様のワンピースといういでたちで、さらに有名になった感のある作者ですが、その歩みは自己自身の内部での不断の闘いと、そのような自己と他者との闘いを含む非常に複雑なものでした。人々の理解などとは別のところで展開した彼女の人生を、いまや、わたしたちは流行として消費しているのではないかと心配になるほどの人気です。しかし、たとえ流行と人気をきっかけに接したとしても、人々は、草間の作品から一貫する何かを受け止め、感動につなげているようです。その何かとは、人間の不確かな生と、そこから派生して私たちにしつこくつきまとう不安、なのかもしれません。とすれば、草間の作品は今日の私たちに最も身近かなもので、従って高齢になってからの最大級の賛辞と評価はむべなるかな、です。
篠原有司男《女の祭》1966年 蛍光塗料、油彩、プラスティック・板
当館蔵
派手な蛍光色、プラスティックの簪、テンガロンハットと祝の手拭い。いまや日本のポップアートの代表作といえる本作です。作者の篠原有司男(1932- )はそれまで、頭をモヒカン刈りにし絵具をしみこませた布の塊を両手にはめ、広げた布をボカスカ殴って描いたボクシングペインティングやネオ・ダダ・オルガナイザーズの仲間たちと繰り広げたパフォーマンスなど、自身の肉体を核にした制作を展開していました。人の真似をしてつくるイミテーション・アートを経て、明治初期の錦絵をヒントにしたのが本作。繊細で上品な北斎や広重や歌麿ではなく、血なまぐさい物語や事件を題材にしたこの時期の錦絵を直観で選択したところ、そしてそれを見事に料理しえたところ、そして何よりそれまでの牛ちゃんこと篠原有司男の「前衛の道」上のこの時点での集大成であったところが名品たるゆえんで、いまやモニュメンタルな風格さえ漂う作品です。