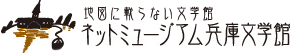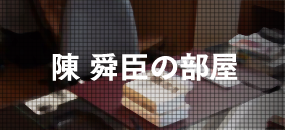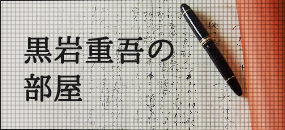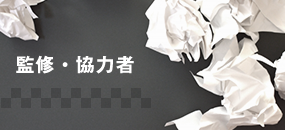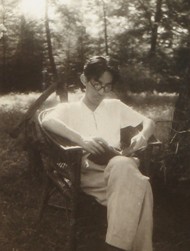
ほり たつお堀 辰雄
- 明治37~昭和28(1904~1953)
- ジャンル: 小説家
- 出身:東京
作品名
旅の絵(初収単行本「物語の女」)
刊行年
1934
版元
山本書店
概要
……なんだかごたごたした苦しい夢を見たあとで、やっと目がさめた。目をさましながら、私は自分の寝ている見知らない部屋の中を見まわした。見たこともないような大きな鏡ばかりの衣裳戸棚、剥げちょろの鏡台、じゅくじゅく音を立てているスティム、小さなナイト・テエブルの上にしわくちゃになって載っている私のふだん吸ったことのないカメリヤの袋(私はそれを何処の停車場で買ったのだか思い出せない)、それから枕もとに投げ出されている私の所有物でないハイネの薄っぺらな詩集、――そう云うすべてのものが、ゆうべから私の身のまわりで、私にはすこしも構わずに、彼等の習慣どおりに生き続けているように見えた。今しがた見たことは確かに見たのだが、どうしても思い出せない変にごたごたした夢も、それまで自分はぐっすり眠っていたのだという感じを私に与えはしているものの、同時に、まるで他人の眠りを借りていたかのような気にも私をさせないことはなった。……
私はベッドから起き上ると、窓を開けに行った。しかしその窓のそとはすぐ高い石囲いで、石囲いの向うには曇った空と、隣りの庭のすっかり葉の落ちきった裸の枝先きが見えるきりだった。が、その窓を通して、しっきりなしに汽船のサイレンがはいってきた。その聞きなれない異様な叫びは、自分がいま東京から離れている、目に見えない長距離を、一瞬間、私の目に浮び上らせそうにした。そういう喧騒の中からひょっくり生れてきかかった一種の旅愁に似たもの、――私は再び窓を閉じた。……
(中略)
小さなトランクひとつ持たない風変りな旅行者の一種独特な旅愁。――私はさっぱり様子のわからない神戸駅に下りると、東京では見かけたことのない真っ白なタクシイを呼び止め、気軽に運賃をかけ合い、そこからそうしつけている者のように、元町通りの方へそれを走らせた。もっとも通行人を罵る運転手の聞きなれないアクセントは私をちょっとばかり気づまりにさせたが。……
元町通り。店店が私には見知らない花のように開いていた。長い旅のあとなので、すっかり疲れきり、すこし熱気さえ帯びていたけれど、それでも私は見せかけだけは元気よくコツコツとステッキを突きながら、人々の跡から一体どんな方角へ行くのかわかりもせずに歩き続けていた。今夜何処へ泊ったものやらまだ目あてのない旅行者で自分があることに誰からも気づかれまいと思って……。私はとある珈琲店の中へ気軽そうにはいって行った。ただその店の名前が東京で私の行きつけている珈琲店の名前に似ていたばっかりに。私はそこから須磨のT君のところへ電話をかけた。T君はすぐ私のいる店へ来ると言った。そうして私がまだ一杯のオレンジエードを飲んでしまわないうちに、そのT君が元気よくはいって来た。彼はベレ帽をかぶり、なんだか象の皮のような外套(がいとう)を着込んでいた。
それから私たちは薄ぐらい山手通りを、狭い坂を上ったり下りたりしながら、小さなホテルから小さなホテルへと歩き廻っていた。しかし私の気に入ったホテルはひとつも無かった。私たちは再び中山手通りへ出た。しかしそのだだ広いだけ、かえって薄ぐらい感じのする電車通りには、ほとんど人影がなかった。T君が突然立ち止まった。そうして電車通りの向う側にある一つの赤ちゃけた小ぢんまりした建物を指さした。その家の上の、煤けたなりに白白とした看板には、
HOTEL ESSOYAN
という横文字が、建物と同じような赤ちゃけた色で描かれてあるのが、ぼんやりと読めた。遠くからそれを一目見たきりで、その小さなホテルは私の気に入った。――と見ると、その電車通りに面した二階の窓の一つが開かれていて、それが細長い光りを暗い鋪道の上にくっきりと落していた。そしてその窓からは、逆光線を浴びているので、年よりなのか若い女なのか見当のつかない、そして髪の毛だけがきらきらと金色に光っている、一つの女の顔が、そのホテルの方へと電車の線路を横切りつつある私たちの方を窺うようにしていたが――それはちょっと無気味な感じだった――私たちがその窓の下までくると、向うでも私たちを恐れるかのように、その窓は閉されてしまった。
私たちは小さな石段を昇り、そこのベルを押した。しかし、いつまでも、誰も出て来そうな気配がしない。そこでT君が再びベルを押したり、ノッブを廻してみたりしている間、私は石段を下りて、もう一度それがホテルであるかどうかを確かめるため、さっきの看板をふり仰いで見た。そうしてその赤ちゃけた横文字をホテル・エソワイアンと読みにくそうに口の中で発音しながら、今度はその大きな横文字の下方に、ずっと小さな字で TEL.と描かれてあるのまで認めた。しかしその電話番号のあるべき場所は空虚のまんまだった。そしてそこだけが気のせいか他処より一そう白白と見えるのは、そこに最近まで書かれてあった電話番号がいまは白いペンキで塗りつぶされてあるのかも知れなかった。
やっとのことで表扉が大きく軋みながら開かれた。そしてその内側には、そのホテルの主人らしい、すこし頭の禿げかかった、私たちよりも背の低いくらいな毛唐が、ノッブを握ったまま突っ立っていた。T君が英語でもって部屋はあるかと声をかけた。するとその主人はそれよりもっと下手糞な英語でそれに応じた。(私はへんに重々しげなアクセントによって彼が露西亜人らしいのを認めた。)――いま自分のところには階下に小さな部屋が一つ空いているきりだ。それも丁度いまその部屋の借り手が東京へクリスマスをしに行っているので、その間だけなら貸すことが出来る、というような意味のことをT君に言っているらしかった。そんな部屋の交渉は一切T君に任せたきり、そこの玄関口に無雑作にほうり出されてある埃まみれの本棚だの、錆びかかったタイプライタアだのへ目を注いでいた私は、やっと顔を持ち上げながら、どうせ私も二三日ぐらいしか泊らないつもりだからそれを見せて貰おうじゃないかとT君を促した。T君がそれを主人に通訳してくれた。さっきからT君の方をばかり見ていたその主人は、今度はそのおずおずしたような視線を私の方へ注いで、ではひとつその部屋を見てくれと言いながら、先きに立って、便所やらコック部屋やら浴室やらの前を通りぬけながら、ずっと奥まった部屋へ――そんな奇妙なところに二つばかり小さな部屋があるのだが、その一つのなかへ私たちを導き入れた。
そんな奥まった小さな部屋へはいると、いきなりT君が仏蘭西の何処とかの田舎で泊ったことのある古い旅籠の部屋にそれがそっくりだと言い出したので、私もそうかなあと思いながら、そこにある古ぼけた寝台だの、いやに大きな鏡ばりの衣裳戸棚だの、剥げちょろな鏡台だの、小さなナイト・テエブルだのを眺め廻しているうち、それがいかにもそんな外国の片田舎にありそうな旅籠屋のような気がしだした。そしてこの悲しげな部屋がいまの私の心に不思議なくらい似つかわしいように思えた。
その小さな部屋が朝飯つきで一泊三円だという。そこで私はともかくも十円札を一枚だけ渡しておいた。そうすると、その時までともすると、小さなトランクひとつ持っていない私たちを妙に不安そうな眼つきで見がちだった、すこし頭の禿げたその主人は急にそわそわし出したように見えるくらい愛想よくなって、私の方を向きながら、それではお前もこちらにクリスマスを送りに来たのかなどと問い出した。私はまた私で、やがてその主人のかかえてきた大きな宿帳に、露西亜人や波蘭人らしい名前ばかりの並んでいる下へ自分の名前をぶきっちょな羅馬字で書きつけているうちに、クリスマスなんかを一向楽しいとも思ったことのない私であったが、なんだか不意に、明日からのクリスマスを楽しく送りに、わざわざこんな神戸くんだりまでやって来たかのような気にさえなり出したほどであった。……
(中略)
夕方、私たちは下町のユウハイムという古びた独乙菓子屋の、奥まった大きなストーブに体を温めながら、ほっと一息ついていた。そこには私たちの他に、もう一組、片隅の長椅子に独乙人らしい一対の男女が並んでよりかかりながら、そうしてときどきお互の顔をしげしげと見合いながら、無言のまんま菓子を突っついているきりだった。その店の奥がこんなにもひっそりとしているのに引きかえ、店先きは、入れ代り立ち代りせわしそうにはいってきては、どっさり菓子を買って、それから再びせわしそうに出てゆく、大部分は外人の客たちで、目まぐるしいくらいであった。それも大抵五円とか十円とかいう金額らしいので、私は少しばかり呆気にとられてその光景を見ていた。それほど、私はともすると今夜がクリスマス・イヴであるのを忘れがちだったのだ。
私はなんだかこのまんま、いつまでも、じっとストーブに温まっていたかった。しかし私は旅行者である。何もしないで、こうしてじっとしていることも、後悔なしには、出来ないのである。
やがて若い独乙人夫婦は、めいめい大きな包をかかえながら、この店を出て行った。JUCHHEIMと金箔で横文字の描いてある硝子戸を押しあけて、五六段ある石段を下りて行きながら、男がさあとこうもりがさをひらくのが見えた。私は一瞬間、そとには雪でも降りだしているのではないかしらと思った。ここにこうしてぼんやりストーブに温まっていると、いかにもそんな感じがして来てならなかったが、静かに降りだしているのは霧のような雨らしかった。
インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)より一部抜粋