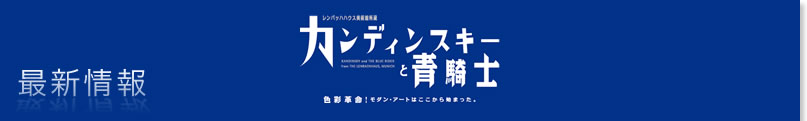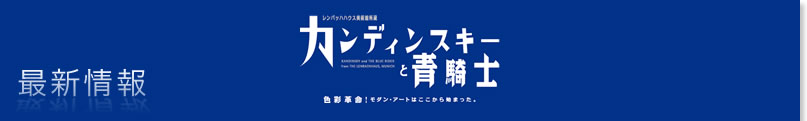|
�W����̉�����A����I�ɊJ�Â��Ă����w�|���ɂ������A18���i�y�j�ɍŏI����J�Â��܂��B
20���I�ő�̋����̂ЂƂ�Ƃ��āA��̔��p�ɑ傫�ȉe��������ڂ����J���f�B���X�L�[�B�ނ��R�m�Ƃ����O���[�v���������A���ɂ͒��ە\���ɓ��B������j�I�ɏd�v�ȉߒ���S���w�|�����킩��₷���������A�W����i�̌����A�y���ݕ����A�X���C�h���f���Ȃ���Љ�܂��B
�ߌ�4����背�N�`���[���[���ɂāA����͖����A��45���̉���ł��B�����͖�ԊJ�ٓ��i��8���܂ŊJ�فj�B������������������������ł��������W������������������܂��B
�w�|���ɂ��{�W�̉����͂��ꂪ�Ō�ł��B���Ђ��Q�����������B
|
 |