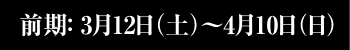展覧会構成

第1章
万里の路
全国を行脚し、実景を前にしての体験や感興をもとに描かれた真景図、各地で目にした風俗など、鉄斎独自の空間構成で描かれた雄大な山水画を中心に展示。富士山を描いた一連の作品も紹介します。《三老登嶽図》1901年
清荒神清澄寺 鉄斎美術館蔵(前期展示)
清荒神清澄寺 鉄斎美術館蔵(前期展示)

第2章
万巻 の書
中国・日本の故事、古典から取材した人物画、文人の理想郷を描いた山水画や神仙画などを中心に展示。奔放な筆致で表現された迫力ある人物像や、ユーモラスな表情の人物、群像表現など、鉄斎の多様多彩な絵画表現に迫ります。
《擬土佐又兵衛筆法遊戯人物図》1912年
清荒神清澄寺 鉄斎美術館蔵(前期展示)
清荒神清澄寺 鉄斎美術館蔵(前期展示)

第3章
画祖となる
鉄斎の傑作と言われるものは主に70 代〜 80 代にかけて生み出されています。晩年に至るとともに筆力は逞しさを増し、80 歳を超えて画境は一段と新鮮な感覚を加え、85 歳をすぎてさらに進境を見せたとも言われた鉄斎の70 歳代から80 歳代の名作を展示します。《西王母像》88歳 1923年 清荒神清澄寺 鉄斎美術館(前期展示)
第4章
文人・鉄斎の娯 しみ

《狸香合》1920年
清荒神清澄寺 鉄斎美術館蔵(全期間展示)
第5章
−鉄斎をめぐる言葉

梅原龍三郎《富士山之図》1946年
京都文化博物館蔵(全期間展示)
大正期以降、鉄斎に関心を寄せた画家たちが様々な言葉を残しています。展覧会の最終章では、これらの画家たちの言葉と作品を紹介、鉄斎が近代の画家たちに及ぼした影響や、鉄斎がどのように受容されていたのかを考察し近代絵画史上での位置を再考します。
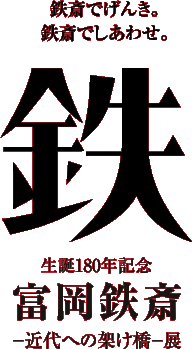
![会期は2016年3月12日[土]から2016年5月8日[日]。](img/detail_t02.gif)