
 |
昔、日本人が西洋の油絵を採り入れたのは、何よりもまずその写実性に感心したからです。でも、どんな絵をリアルに感じるかは、時代や場所、人によって違うかも知れません。あなたにとってどの絵がいちばんリアルでしょうか。

 |
|
岡田三郎助 《萩》 1908年 |
|


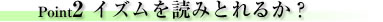
 |
モダンアートでは、写実でない絵のスタイルが次々と生まれました。キュビスム、フォーヴィスム、シュルレアリスム、未来派・・・。絵だけを見て、どれがどのスタイルか、違いがわかるでしょうか。
|



 |
美術は出来事を記録して伝えます。ここではどんな出来事が表わされているでしょうか。でも、これは全部、普通の記録ではありません。作者の体験、見方、感じ方が伝わってくるでしょうか。

 |
|
阿部合成 《見送る人々》 1938年 |
|


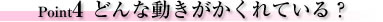
 |
20世紀後半、画家は、これまでにない大胆な方法で絵を描きました。ここで注目したいのは、画家自身や道具などの大きな動き、運動の跡が、作品の表現になっていることです。画面をじっくり見て、どんな風に作られたのか推理してみましょう。

 |
|
金山明 《作品》 1957年 ©Ryoji Itoh |
|


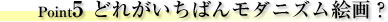
 |
モダニズムの絵画は、絵から必要でない要素を取り去り、絵でしかできないことを求めます。そして、絵が平面であることを強く意識しますが、画面からそれが感じられますか。抽象絵画でも、そこには奥行きや動きがあるでしょうか。
|


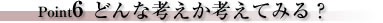
 |
アーティストがいろいろな思考や問いかけをそのまま純粋なかたちで表わした作品があります。それは作品を見る私たちへの問いかけでもあるでしょう。どんな考えがそこにあるのか、アーティストの思考の過程を想像してたどってみましょう。

 |
|
河口龍夫 《DARK BOX 2007》 2007年 |
|



 |
現代のアーティストは、身のまわりにあるいろいろなイメージ(画像)を作品に取り入れます。どんなイメージでしょうか。そして、もとのイメージをアーティストはどう変えているでしょうか。

 |
|
横尾忠則 《葬列Ⅱ》 1969-1985年 |
|


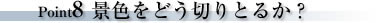
 |
ここでは絵の画面の端に注目します。どんな風景画もトリミングされたものです。景色をどう切りとっているか。これは、画面のかたち、画家の視点や構図の工夫に関わっています。

 |
|
桜井忠剛 《壺と花》 1900年頃 |
|



 |
当館の収集の柱のひとつである彫刻から、西洋近・現代作品を展示します。また、当館の設計者である建築家・安藤忠雄の関西でのプロジェクトを模型、写真、映像などで紹介するコーナーを併設しています。
|



 |
神戸出身のふたりの洋画の巨匠を顕彰するため、それぞれ代表作を展示しています。
 小磯良平記念室 小磯良平記念室  金山平三記念室 金山平三記念室

 |
|
小磯良平 《斉唱》 1941年 |
|
| |
|
|
 |

