|
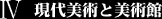

|
|
最後の章では第2次大戦後のいわゆる現代美術と美術館の関係を考えます。
戦後まもなく始められた無審査、自由出品の現代美術展、日本アンデパンダン展(通称 「読売アンデパンダン展」)は、次第に若い美術家たちの実験的で過激な作品が会場の美術館側と対立関係を生み、ついに中止となります。
当時の最先鋭の美術家が出品していたこの伝説の展覧会の雰囲気を、赤瀬川原平、工藤哲巳らの代表的な出品作を展示することにより再現します。 また、当時注目を集めた出品作、田辺三太郎のドラム缶を使った巨大作品「不調和音音階」
は、この展覧会のために再制作されます。 |
|
|
|

関根伸夫
《位相-スポンジ》
1968年
広島市現代美術館 |
大光相互銀行が母体となって1960年代、新潟長岡に日本で最初の現代美術館、長岡現代美術館
がオープンしました。
そのコレクションは内外の近代・現代美術を中心に質、量ともに優れたもので、日本に美術館
が満足になかった当時、最大のコレクションでした。 特に現代の美術に関しては美術館賞を設けて、同時代の優れた作品を買い取るなど活発な活動
を繰り広げました。
今は幻となったこの美術館を藤田嗣治、斎藤義重、加山又造、ダリ、ウォーホル、ローゼンクイスト、ステラなど大光コレクションの名品とともに紹介します。
この章では、その他兵庫県西宮市の現代美術の大コレクター山村徳太郎の白髪一雄、元永定正ら具体グループ関係の特色あるコレクションや、現代日本を代表する美術家のひとり山口勝弘による、美術館に代わる新しい概念イマジナリウムを具現した作品を展示します。 |
|
| |
|