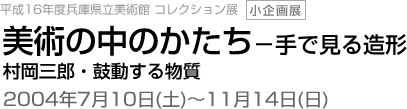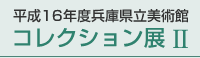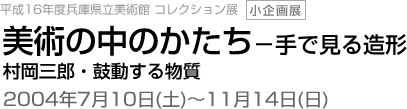


「美術の中のかたち-手でみる造形」展は、立体的な作品に手で触れて鑑賞する展覧会です。当館の前身である兵庫県立近代美術館で1989年から継続的に開催されており、本年で15回目となります。この展覧会は、視覚に障害のある方々にも美術館を訪れる機会を増やしてもらいたいといという思いと、触覚による鑑賞によって美術鑑賞のあり方そのものを問い直すという目的から始まりました。
これまでの展覧会では、館所蔵の彫刻と現存作家による作品を併置して展示していましたが、今回は、滋賀県大津市在住の作家、村岡三郎氏の作品のみで構成しています。
村岡三郎氏は、1954年に鉄を素材とした作品を発表、鉄にはじめて着目した作家として知られています。「生命」、「死」という人間が抱える根源的な問題を、鉄、塩、硫黄などの物質を通して問い続け、目にみえないもの、例えば、熱、振動といった生命の象徴としての現象を痕跡として作品のなかにとどめ、表現しようとしています。身体あるいは人間に与えられた感覚をとおして知覚される現象を、物質とのあくなき格闘によって表現した作品は、見る者に圧倒的な存在感と力強さをもって迫ってきます。物質と身体との関係を問い、目で触れる彫刻と自ら呼ぶその作品には、制作に要した時間の流れや身体感覚が織り込まれています。
村岡三郎氏の作品は、酸素ボンベなどに代表されるモチーフを用いて構成した、インスタレーション的なもの、視覚的に構成した作品が主体ともいえますが、この「美術の中のかたち」展では、物質そのものを直接提示しているもの、例えば熱や、空気などの目に見えないものを「封印」したり、「痕跡化」した、比較的触覚的傾向の強い作品を村岡氏の提案もいただきながら展示しています。氏の作品を「美術の中のかたち」展のなかで展示することにより、氏が素材に選んだ様々な物質の手触り、熱や空気によって変化した物質の触感をとおして、物質の中に沈潜する作家の思想を読みとることを狙いとしています。
今回は館蔵の彫刻は展示していませんが、村岡氏の作品を鑑賞する前に、あるいは鑑賞した後に彫刻室であらためてそれらを見るとき、同じ立体作品でもその構成原理―素材や技法あるいは具象抽象という違いだけでなくその構成原理、歴史性や文化との関わりかた、視点や狙いの違いが浮き彫りになるでしょう。本展において、村岡氏の作品との触覚を通じた「出会い」により、作家の思索の一端に触れ、
その世界を感じ取り、また同時に現代美術に親しむ一契機ともなれば幸いと考えます。 |
 |
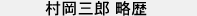

1928年
大阪に生れる

1950年
大阪市立美術研究所彫刻部修了 二科展に出品(1967年まで)

1960年
二科会会員となる(1969年まで)

1965年
第一回現代日本彫刻展:K氏賞受賞

1969年
信濃橋画廊で初個展「砂」

1981年
滋賀大学教育学部教授となる

1987年
「国際鉄鋼彫刻シンポジウム・YAHATA'87」に際し、《鉄の墓》を東田高炉記念広場(北九州)に永久設置
大阪府立現代美術センターにて回顧展「村岡三郎1970-1986」が開催される

1990年
遠藤利克とともに「第44回ヴェネツィア・ビエンナーレ」日本館に出品

1993年
滋賀大学教育学部を退官、京都精華大学教授となる

1994年
《OXYGEN》を滋賀県立近代美術館に永久設置

1997年
東京国立近代美術館、京都国立近代美術館にて展覧会「熱の彫刻―物
質と生命の根源を求めて」が開催される
第2回光州ビエンナーレに出品

1999年
第40回毎日芸術賞受賞

2000年
第1回越後妻有アートトリエンナーレ2000に出品

2001年
横浜トリエンナーレ2001に出品

2002年
京都精華大学を退官
現在滋賀県大津市在住 |
|
|